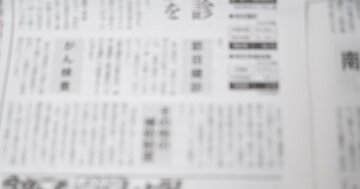いくつかの候補が浮上しては立ち消え、最終的に移住が現実のものになったのは、長野県が主催する移住フェアがきっかけだった。オンライン形式ながら、県内から複数の自治体関係者が出展するこのフェアで、2人は青木村の存在を知る。
「青木村はロケーションも最適でしたし、相手をしてくださった役場の方の対応も親切で、2人ともすぐにピンと来ました」
何より、青木村はかつてビールの主原料の1つであるホップを栽培していた歴史があることにも、不思議な縁を感じた。ここから移住まではトントン拍子。住まい探しも地域の協力を得て、築150年の古民家の購入が決まった。
3800坪の広大な土地に建つ、100坪の古民家
よく晴れた初秋のある日、中村さん夫妻が移住して3年目を迎えた青木村を訪ねた。
まず驚かされたのは、敷地の広さである。山間部を含むと、なんと3800坪。そこに現在住まいとして使っている100坪の母屋に離れ、そして厩舎が建っている。
 敷地の半分は山。草むしり役として、3頭のヤギも一緒に暮らしている Photo by S.T.
敷地の半分は山。草むしり役として、3頭のヤギも一緒に暮らしている Photo by S.T.
試しに圭佑さんに母屋の間取りを尋ねてみると、「どうなんだろう。いまは間仕切りを取り払ってしまいましたが、もともとは1階と2階を合わせて18部屋くらいあったのではないでしょうか」というから、想像を絶するものがある。
「これで680万円ですから、都会では考えられない買い物ですよね。ただ、改修しながらなので、活用できているスペースはまだまだごく一部。離れのほうは昔ながらの農機具などがどっさり詰め込まれていて、掃除すらできていません。母屋の2階も最近は醸造に追われて放置したままですし……」
と言う圭佑さん。もう少し人を呼びやすいよう片付けたいとは思っているそうだが、「なかなか手が回らない」と笑う。
確かに、現場を直接目にした立場から言えば、古民家を改修しながら暮らすというのは、とてつもない労力が必要なのだと実感させられる。
 家の中の様子。DIYしながら暮らしやすい環境を整えている Photo by S.T.
家の中の様子。DIYしながら暮らしやすい環境を整えている Photo by S.T.
さらには最近、次女を授かったことで、育児にかかる労力は倍増した。敷地内では植物や農作物を手広く栽培し、ビールの醸造もある。時間はいくらあっても足りない状態で、気忙しさは東京にいた頃以上なのではないかと思える。
しかし、タスクにまみれる中にあっても、夫妻の顔はどこまでも穏やかで明るい。これも求めていた自然との共生、そして人間らしい暮らしがあればこそなのだろう。
 生後1カ月の次女と、中村さんご夫婦 Photo by S.T.
生後1カ月の次女と、中村さんご夫婦 Photo by S.T.