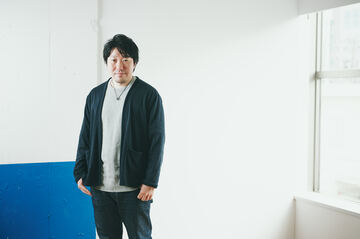また、新規事業を通じて事業が成長するワクワク感を会社の中に作り出し、新しい風を呼び込みたい。そんな意図もあったという。
「結果的には2016年から動画事業をやっていたから、今動画の波に乗れています。数年前から『動画が来る』と言われていたものの実際はなかなか成功したとは言えなくて、ようやく2019年ごろになって手応えを掴めたような感覚です」(須藤氏)
翌年の2017年にも須藤氏は大きな決断を下した。もともとはアメリカ法人でスタートしたところを、4月に設立した日本法人(現在のKaizen Platform)を親会社とする形でインバージョン(組織再編)を実施。新体制のもと、国内事業を一層強化する方向へと舵をきった。
ただ、この手続きには税務、会計、法務などの様々な論点をクリアする必要があり、膨大な時間とコストを要する。前例も少ない中、手探りで手続きを進めつつ、並行してプロダクトや組織の課題とも向き合い続けなければならない。複数の大型案件が終了するタイミングとも重なって、数カ月後にはキャッシュアウトするような状況だった(須藤氏の話では毎回思い切って投資をするため、資金調達の直前は常にそのような状態にはなるそう)。
その状態を好転させたのは、現場で働くメンバーたちの“解像度の高い”改善案やアイデアだった。
役員会議やマネージャー会議で対応策を検討するだけではなく「ダメな状態も含めて」社内にシェアすることを決めた。現場からのフィードバックを経て当時細分化していたサービスを一本化し、社内リソースを注力。特別な手法を使ったわけではないが、まさに全員でできることに集中した。
その年の12月には、2016年2月のシリーズBラウンド以来となるシリーズCラウンドで総額5.3億円の資金調達も実施。再び大きく投資ができる体制を整えた。
“DX推進を支援するプラットフォーム”へと進化したKaizen
長い年月をかけて地道に磨いてきたプロダクトは、ここ1〜2年で様々なシーンで実を結び始めた。顧客の悩みに応える形で機能拡張を続けていった結果、エンタープライズの「DX支援」に関する案件も着々と増えている。
特に大企業ではビジネス部門とIT部門の間にギャップが生じてしまうケースが多い。エンジニア不足の影響もあってIT部門はほとんどの時間を「既存システムの保守運用」に使わざるを得ない一方、ビジネス部門は事業を成長させるためにさまざまな施策にチャレンジしたいがそれを実現できずにいる。
“基幹システムを直接触ることなく”サイトにタグを設置するだけでUI改善やパーソナライズの施策に取り組むことができ、なおかつ外部のグロースハッカーたちの力を借りられるKaizenの仕組みは、大企業のニーズにピタッとハマるそうだ。