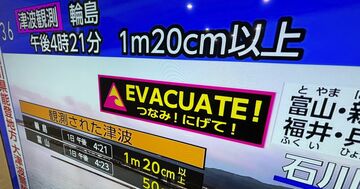進んだ分断、党派性がにじむデマも
「拡散しない」ためにできること
もう一つ指摘しておきたいのは、東日本大震災のあった2011年と比べ、現在のインターネットは党派性による分断が進んでしまったことだ。
たとえば、森友問題に言及すれば左翼、ウイグル問題に言及すれば右翼のように、あるテーマやキーワードに言及するだけで即レッテルを貼られる状況がある。好き・嫌いの域を超えて、もはやプロフィールを見るだけで「敵」と「味方」を見分けるような殺伐とした雰囲気が、一部には確実にある。
このような状況の中で、「敵」とみなした陣営に対するデマを流そうとしたり、あるいはそのデマを易々と信じてしまう人が現れたりすることは想像に難くない。
関東大震災時の在日朝鮮人に対するデマと、その結果起こった虐殺は語り継がなければならない教訓だが、令和の今、このような過去が決して「過去のこと」とは思えない状況がある。
人は信じたいものを信じる。デマはその心理を利用して作られる。またSNSのタイムラインは、そもそも自分にとって都合が良く、自分が信じ込みやすいような投稿が表示されやすいことに留意するべきだ。
「親しい友人が拡散しているから本当だろう」とか、「フォロワー数の多いインフルエンサーの投稿だから信頼できる」という基準は大変危険だ。
相互フォローの人々がしきりに投稿を続けているからといって、自分も何か投稿しなければいけないわけではない。情報が錯綜しやすい今回のような緊急時は、「あえて何も投稿しない」「SNSを開かない」という自衛方法も必要なはずだ。