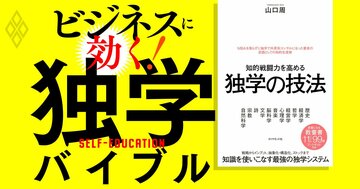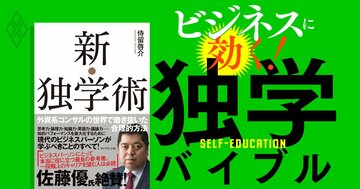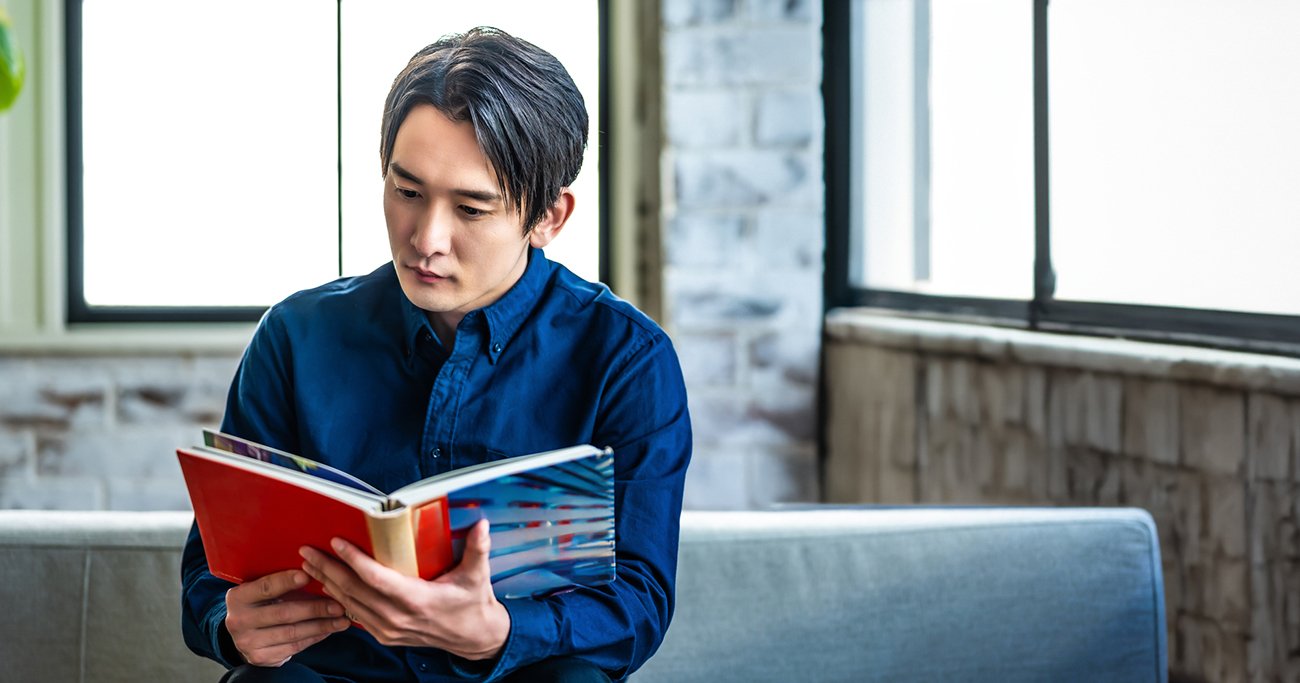 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
本を読むのは好きだけど、面白かった内容を人に伝えようとするとうまく説明できない…そんな読書好きは意外と多いのではないだろうか。頭のいい人がやっている知性を鍛える本の選び方と伝え方を知れば、読書がさらに面白くなるはずだ。本稿は、齋藤孝『本当に頭のいい人がやっている思考習慣100』(宝島社新書)の一部を抜粋・編集したものです。
読書は知を鍛える
最適な手段
知性を鍛える方法として、最も大切で効率がいいのが読書です。
湯川秀樹をはじめとして、科学者の多くは幼い頃から推理小説や古典などの、サイエンス系ではない本も読みながら、心を豊かに育ててきました。科学者が新たな研究に踏み出すときに必要なのは、ひとつには想像力。そうした科学に不可欠な力を読書は育ててくれます。
また、スティーブ・ジョブズ氏が、禅僧である鈴木俊隆氏の著書をむさぼるように読んだ話は有名です。禅の精神性はアップル社のデザイン哲学に強い影響を与えました。そこには「文系と理系」といった単純な線引きは存在しません。
動画や音楽でわかりやすく伝えてくれるユーチューブは、私も好きで見ることがあります。しかし、流れるものを受け止めるだけの思考に終始していると、読書のような能動的に想像を働かせる力が劣化していくおそれもあります。
また、読書はそのやり方によって、脳全体を満遍なく鍛えてくれます。ヒトの脳というのは、「思考系」や「記憶系」「伝達系」「視覚系」など、役割によっていくつかのエリアに分かれており、どの部分を鍛えるかは、どんな本をどう読むかで決まってきます。
たとえば、作者の意図や気持ちを知ろうと意識して読むと、理解系が働いて発想が生まれやすくなりますし、気持ちを乗せて小説に触れると、感情系が揺さぶられて認知症予防につながるといいます。また、音読すると運動系が刺激され、さらには本をいったん閉じて思い出す行為を繰り返すと、長期記憶が鍛えられるそうです。
読書は私たちの知的水準を上げてくれるだけでなく、時間的かつ空間的な視野を広げ、心を豊かにしてくれるのです。
優れた本の選び方
注目すべきは目次?
頭がいいといわれる人は、友人との会話や職場の会議などで、流れの全体の構造と大事なポイントを素早く把握する力に長けています。会話や会議だけでなく、書店で本を選ぶときも同様で、無駄なく短時間でその本の内容、すなわち全体の構造を知る術を知っています。それは目次を活用するという方法です。
目次は、その本の内容が見出しで要約して示され、章ごとに分けて並んでいるため、その本に何がどんな順番で書かれているかが一目でわかります。実は、目次だけで内容がわかる本というのが、いちばんいい本ということでもあるのです。
ニッコロ・マキャヴェッリの『君主論』などは目次が秀逸で、それを見るだけで内容のおもしろさが伝わってきます。ユヴァル・ノア・ハラリ氏の『サピエンス全史』なども、目次を読んでいるだけで頭がよくなっていくのがわかります。