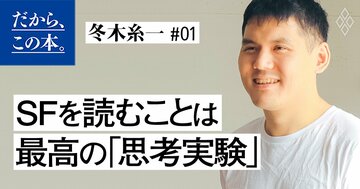「幸福の王子」が出版されたのは1888年。「銀の燭台」(*)の時代から50年ほど後のヨーロッパですが、貧しい人たちの悲惨さは変わっていないようです。「銀の燭台」のミリエル司教も、ジャン・バルジャンに銀の食器だけでなく、銀の燭台まで与えますが、幸福の王子も同じようにすべてを捧げてしまいます。
読者に複雑な思いを残す
ハッピーエンド
ここに描かれているのは、ミリエル司教と同じ、キリスト教的な博愛、自己犠牲、献身であることに間違いないでしょう。しかし、それだけではありません。
幸福の王子の頼みを断り切れず、宝石や金箔を運び続けるのはツバメです。このツバメは、茶目っ気があり、優しい男の子です。特に、熱にうなされている少年の額を冷たい翼で冷やそうとする場面には、愛らしい優しさがあふれています。ツバメはエジプトへと旅立つことなく、冬が来ても王子の使者として飛び続け、やがて最期の時を迎えます。目が見えず何も気づかない王子は、「わたしのくちびるにキスをしておくれ。わたしがおまえを愛した、そのしるしに」と言います。そして、キスをしたツバメは力尽きて死んでしまうのです。
王子を愛したツバメは、王子の願いを叶えるために自分の命を捨てました。ツバメのしたことも、王子と同じく自己犠牲です。でも、かけがえのないツバメが死んだとわかった瞬間、王子の心臓は真っ二つに割れてしまう。大切な存在を失った悲しみからでしょうか。またそれは、本当の愛、すなわち自らの命を捧げる愛を知った瞬間でもあります。単に博愛の美しさを称えるだけではない物語の深さが生まれている場面だと思います。
外国の童話は、主人公が死んでも悲劇ではないことがよくあります。「マッチ売りの少女」や、「フランダースの犬」がそうです。主人公が天国に召されるのです。神さまが救ってくれるのですね。「幸福の王子」でも、ツバメと王子は、神様に遣わされた天使に選ばれて、天国でいつまでも幸せに暮らします。しかし、読者の心には単なるハッピーエンドだけではない、「無償の愛って何?」という複雑な思いが生まれることでしょう。