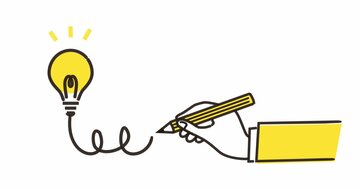価値観が多様化し、先行き不透明な「正解のない時代」には、試行錯誤しながら新しい事にチャレンジしていく姿勢や行動が求められる。そのために必要になってくるのが、新しいものを生みだすためのアイデアだ。しかし、アイデアに対して苦手意識を持つビジネスパーソンは多い。ブランドコンサルティングファーム株式会社Que取締役で、コピーライター/クリエイティブディレクターとして受賞歴多数の仁藤安久氏の最新刊『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』は、個人&チームの両面からアイデア力を高める方法を紹介している点が、類書にはない魅力となっている。本連載では、同書から一部を抜粋して、ビジネスの現場で役立つアイデアの技術について、基本のキからわかりやすく解説していく。ぜひ、最後までお付き合いください。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「社内のイベントを開いても参加者が集まらない」
という悩みをどう解決するか
私は大学院生の頃、地域づくりや文化人類学について学んでいました。そのためか、あらゆるビジネスの事象を「地域の中での事柄」に置き換えて考えることが多くあります。
たとえば、先日の話です。とある企業の人事部の方から「社内のイベントを開いてもどうしても参加者が集まらない」という悩みを聞きました。
「周年でビジョンも変えることも決まったし、自分たちの会社のことなんだから、もっと一人ひとりが積極的に参加してくれたらいいのに、なぜか、いつも同じメンバーしか集まらない……」というのです。
こういう悩みを持たれている方は、実は多いのではないでしょうか。
しかし、「地域の中での事柄」に置き換えてみると、参加者が集まらないのが当たり前のことのようにも思えます。この悩みを、お祭りにおける参加の募り方に置き換えてみましょう。
いくつもの町内をまたがって開催されるような大きなお祭り。その祭り全体を盛り上げるために、「みんな積極的に運営に参加してください」というような呼びかけをするでしょうか。
そうではなく、小さな単位での呼びかけが行われています。町内の神輿の担ぎ手を募集したり、神輿(みこし)に参加してくれた子どもにはお菓子をあげたり、大人には途中途中での振る舞い酒や打ち上げなどを誘い文句にしながら、「自分たちの町内」を盛り上げているのではないでしょうか。
自分が所属している小さなコミュニティを盛り上げることを直接の動機にしながら、その熱量が集まって、ひとつのお祭りの熱量になっていることが多いように思います。
とすると、「会社全体を盛り上げるためにみんな参加してください」という動機のつくり方は、ちょっとハードルが高すぎるような気がします。
アナロジー的思考(類推思考)とは
たとえば、部や課やチーム単位でまず盛り上がり、会社のイベント自体が成り立っていくような仕組みをつくれないか、と考えたほうが勝算がありそうです。
このような考え方は、アナロジー的思考(類推思考)と呼ばれています。物事の間にある援用できそうな構造を見出し、応用する思考法です。
一見するとまったく異なるように見える課題にも、A→とB→というように類推し、援用できそうな構造を見出せることが多々あります。このようなアナロジー的な思考を身につけることができると、新しいアイデアを生みだすときにとても役立ちます。
私も解決策を考える際には、先ほどの例のように、「何か(これと)似ているようなことはないか」「類似性を持っているものはないか」と探すようにしています。
この考え方は、前例がない課題や、思考しはじめたけれど、取っ掛かりがないように思えることに取り組むときにも、とても役立ちます。
アナロジー的思考で問題解決した事例
ひとつの例を挙げましょう。詳細はお伝えできませんが、とある企業において、会社の根幹を揺るがすような大きな危機があり、その事実とその後の対応について、どのように伝えることが適切なのか「社内コミュニケーションを設計してほしい」という依頼を受けたことがあります。
多くの社員にとっては、一生この会社で安泰に勤めていくことを疑いなく信じていたはずなのに、それを大きく覆すような危機でした。その企業にとっては、企業を存続させていくためには、一時の大量出血はやむを得ない、という苦渋の決断となるものでした。
この経営者の判断は、どのようにしたら社員の一定の理解を得るところまでいけるのでしょうか。
同様の事例を当たってみたところ、特に、定石と言えるようなものはありませんでした。危機管理コンサルタントのような専門家にヒアリングしても、明確な答えは持ち合わせてはいませんでした。
そこで、アナロジー的な思考で、違う分野から応用可能なものはないか、手当たり次第に探しました。大きなショックに直面したときに、人にはどのような心理的な変容が起こるのか、ということを考えてみると「余命宣告を受けたとき」と似ているのではないか、と考えました。
自分では、どうすることもできない大きな流れを前にして、どのようにその運命を受け入れていくのか、というところに今回のヒントがあると思ったのです。
「死の受容の5段階」のプロセス
そこで参考にしたのが、『死ぬ瞬間』(中公文庫)の著者である精神科医、エリザベス・キューブラー=ロスの「死の受容の5段階」というプロセスです。それは、すべての患者に当てはまるわけではないとしつつも、次のような段階を経るというものでした。
私は、そのときまでこの説を知りませんでしたが、看護の分野などにおいては、とても有名なもののようです。これは、次のような5段階となっています。
①否認・隔離‥自分が死ぬということは嘘ではないのかと否認する
②怒り‥なぜ自分が死ななければならないのかという怒りを周囲に向ける
③取引‥なんとか死なずにすむように取引をしようと試みる。何かにすがろうとする
④抑うつ‥絶望を感じて何もできなくなる段階
⑤受容‥最終的に自分が死に行くことを受け入れる
この5段階を参考にしながら、その会社や社員にとって危機的な状況にある、今回の社内へのコミュニケーションに転用していきました。
一度に全部の情報を伝えるのではなく、この5段階のように段階的に情報を開示し伝えていくように設計しました。
通常であれば、最初の発表のときに、事業撤退の事実に加えて、既存部門に対する考え方、人事的な方針や処遇をすべて最初に伝えるのが通例のようです。
しかし、このキューブラー=ロスの説に則れば、衝撃的な事実を伝えられたときの最初の反応は「①否認」となります。ですから、説得的な情報をいくら重ねたところで受容には至らない。そこで、伝達を複数回にわたって時系列で組み立てました。
「②怒り」のフェーズにおいては、なぜ、このような結論となったのかを経営的な視点から丁寧に伝えながら、会社が存続していくに当たっては「合理的でいちばん正しい決断」だったことの理解を求める説明を行いました。
「③取引」のフェーズにおいては、一人ひとりに対して最悪な結末ではなく、考えられ得る最善の選択肢を用意していくことを提示。
「④抑うつ」のフェーズでは、ひとりで思い悩むことなく、チーム、同僚、家族などにおいて対話が生まれるような情報提供を行いました。
結果として、経営対現場での軋轢や断絶が露骨に生じることなく、会社としての危機を乗り越えることができました。
もちろん、一人ひとりにフォーカスを当てれば、大きな負担を強いるものでした。しかし、何を伝えても「否認」されるフェーズを超えて、丁寧にコミュニケーションをとっていくことによって、従業員のことをいちばんに考えて、あらゆる決断を行った経営陣の思いを届けることができました。
(※本稿は『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』の一部を抜粋・編集したものです)
株式会社Que 取締役
クリエイティブディレクター/コピーライター
1979年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業。同大学院政策・メディア研究科修士課程修了。
2004年電通入社。コピーライターおよびコミュニケーション・デザイナーとして、日本サッカー協会、日本オリンピック委員会、三越伊勢丹、森ビルなどを担当。
2012~13年電通サマーインターン講師、2014~16年電通サマーインターン座長。新卒採用戦略にも携わりクリエイティブ教育やアイデア教育など教育メソッド開発を行う。
2017年に電通を退社し、ブランドコンサルティングファームである株式会社Que設立に参画。広告やブランドコンサルティングに加えて、スタートアップ企業のサポート、施設・新商品開発、まちづくり、人事・教育への広告クリエイティブの応用を実践している。
2018年から東京理科大学オープンカレッジ「アイデアを生み出すための技術」講師を担当。主な仕事として、マザーハウス、日本コカ・コーラの檸檬堂、ノーリツ、鶴屋百貨店、QUESTROなど。
受賞歴はカンヌライオンズ 金賞、ロンドン国際広告賞 金賞、アドフェスト 金賞、キッズデザイン賞、文化庁メディア芸術祭審査委員会推薦作品など。2024年3月に初の著書『言葉でアイデアをつくる。 問題解決スキルがアップ思考と技術』を刊行する。