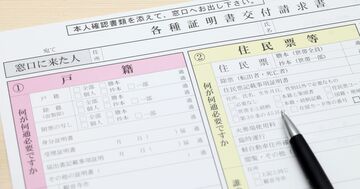これについて松本総務大臣は、閣議後の記者会見で「再発防止策を着実に実行するとしていたのに、修正プログラムの適用漏れなどによって誤交付が発生した。率直に申し上げてがく然とし、極めて残念だ」と強く批判しました。その上で「信頼回復につながる実効性ある再発防止対策を来月15日までに報告するよう求めているが、不十分な場合には、追加的な対策を求めることもある」と述べました。
さらに「マイナンバーカードを活用することで自治体の業務改革なども進めてきている。我々としても、国民の制度への理解が深まるように取り組んでいきたい」とまで豪語しています。なんだか、すべて富士通のせいにされています。
マイナンバーカードが利便性を向上させるのは間違いないと思います。本人確認が1枚で済む唯一のカードでもあります。証券口座などの開設やコンビニでの住民票、印鑑登録証明書の取得も可能です。
それだけではありません。2023年6月9日に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」によれば、政府は「運転免許証との一体化」「障害者手帳との連携の強化」「資格情報のデジタル化」「引越し手続きのデジタル化推進」「在外選挙人名簿登録申請のオンライン化」まで推進していく計画のようです。将来的には、マイナンバーカードの全機能をスマホに搭載できるようにしていく方針だといいます。
しかし、これほど急速に、計画性もないまま、マイナンバーを肥大化させていいものでしょうか。
みずほどころではない巨大システム
悲惨な結果を生まないか
太平洋戦争で、日本は兵站システムの破綻により餓死者や病死者を大量に出しました。日清、日露の戦争では、餓死者が出るような軍隊ではなかったのに、想定外の勢力範囲となる中国大陸と太平洋の島々という巨大な戦場には、従来の兵站組織では対応し切れなかったのです。失敗は認めずに「勝った勝った」で、あの戦争は突き進みました。
そして、軍の暴走を監視するシステムもなくなってしまいました。みずほ銀行はもう随分前に興銀、富士銀、第一勧銀を統合し、システムを共通化しましたが、いまだにトラブルが続いています。
マイナンバーカードシステムは、みずほ銀行どころではない巨大なシステムであり、いくつものシステムを統合して実行されます。構想時からどんどん肥大化し、さらに工期は限定され、予算が増えるというわけでもないシステム構築が、悲惨な結果を生まないことを祈るばかりです。
(元週刊文春・月刊文芸春秋編集長 木俣正剛)