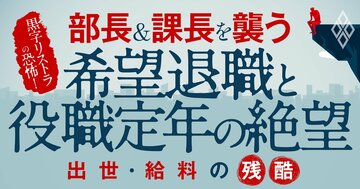その後、新たに当該地域に参入してきたタクシー会社が台頭してきたうえ、外国人観光客が減少するなどの事情もあり、Y社のタクシー需要が大幅に減り、乗務員が過剰になりつつあった。そのような中、Y社の営業係(無線配車の補助などの業務)に従事していた社員が退職することになった。そこで、社長は、過剰になっている乗務員を適切に配置すべく、Xを営業係に異動させることを考えた。
社長は、Xに対し、「営業係の社員が1名退職することになった。当社の状況が厳しいことは分かっていると思うが、乗務員を辞めて営業係に異動してくれないか」と伝えた。これに対し、Xは、「事情は分かりますが、私はタクシー運転手として採用されており、他の業務に従事することは考えられません。運転手の仕事にもやりがいを感じていたんです。営業係に異動することになれば、歩合給から固定給に変わることにもなり、自身の給与にも大きな影響が出てしまいます。営業係への異動はお断りします」と述べた。
社長は、「新たに人員を補充することなど考えられない。就業規則にも、業務上の必要がある場合に、他の業務への変更ができる旨が定められているし、営業係への異動に従ってもらえない場合には、相応の処分を検討しなければならない」と述べた。
Xは、タクシー運転手から離れることに納得できなかったが、社長の命令に従わないことで、解雇され路頭に迷うことだけは避けたいと考えた。そこでXは、「営業係への異動には納得できませんが、会社からの命令ということであれば、いったんは営業係の業務に従事します。ただし、弁護士にも相談して、今後の対応は検討したいと思います」と述べた。
その後、Xの代理人弁護士から、タクシー運転手への業務に戻すことを求める内容証明郵便が届いた。しかし、社長はこれに何ら対応せずに放置していたところ、裁判所からY社に訴状が届いた。Xが営業係での就労義務不存在確認訴訟を提起したということであった。