じゅんは高校が外国語科だったため、英語科目の時間が多く、政治経済や倫理の授業は受けていないという。その影響について、じゅんは次のように話している。
筆者:倫理とか政経とか、(高校の授業で)やらなかった影響はあった?
じゅん:あったよ、大学入ってから。あったよ。倫理とかさ(高校の授業でやらなかった影響が)。これはでも、選んだ学部によっては、影響はなかった人ももちろんいると思うけど、自分の場合は、(大学で)哲学系(の授業)とか取ってたから。(高校のときに倫理の授業で扱うはずだった)哲学、なにもやったことないのに、「知ってるでしょ?」っていう体(てい)で、倫理はやったってこと(前提)で話が進むから。その(大学の授業で登場する哲学者の名前が)「誰も分かんないんだけど?」みたいな。
じゅん:あったよ、大学入ってから。あったよ。倫理とかさ(高校の授業でやらなかった影響が)。これはでも、選んだ学部によっては、影響はなかった人ももちろんいると思うけど、自分の場合は、(大学で)哲学系(の授業)とか取ってたから。(高校のときに倫理の授業で扱うはずだった)哲学、なにもやったことないのに、「知ってるでしょ?」っていう体(てい)で、倫理はやったってこと(前提)で話が進むから。その(大学の授業で登場する哲学者の名前が)「誰も分かんないんだけど?」みたいな。
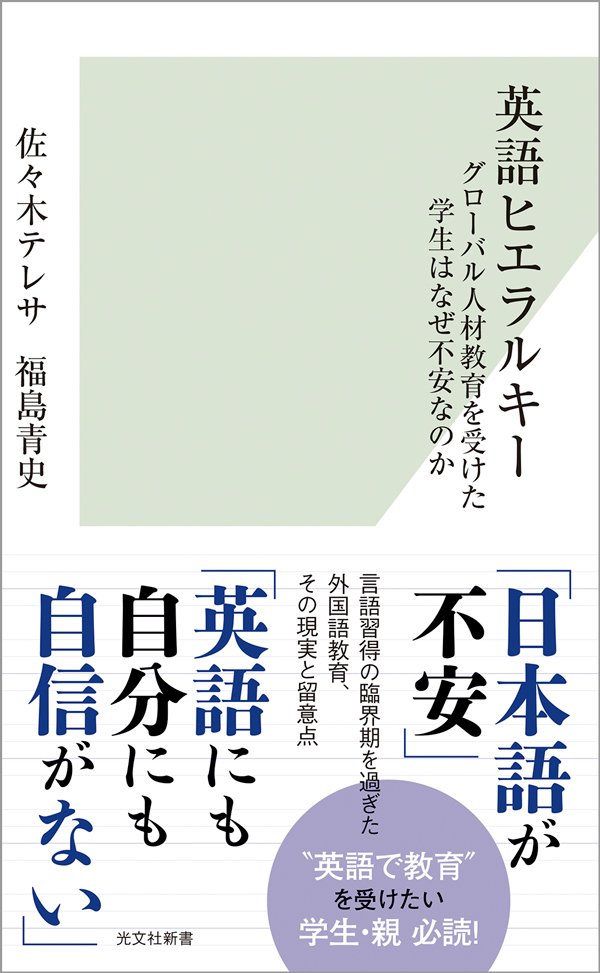 『英語ヒエラルキー,グローバル人材教育を受けた学生はなぜ不安なのか』(光文社新書) 佐々木テレサ 福島青史 著
『英語ヒエラルキー,グローバル人材教育を受けた学生はなぜ不安なのか』(光文社新書) 佐々木テレサ 福島青史 著
じゅんは、事前知識の全くない状態で受ける英語の講義は、かなり苦痛だったと語った。じゅんのように、授業が全く理解できないという場合もあれば、英語力が足りないと判断したり、事前知識が全くないことを勘案して、そもそも自ら、授業の選択肢の幅を狭めることもある。
一方の、帰国子女であるみずきの語りから分かることは、言語の壁がなかったため、自分の興味のある授業を、自分の英語能力と照らし合わせて断念するということはなかったということだ。当該学部の環境が、どれだけ英語に支配されているかが分かる。
このように、EMI実施学部の環境では、英語ができる人とできない人との差がはっきりしており、その明確な能力の差を日々感じることで、英語ができないと感じている人の劣等感が強まっていく。入学当初に保持していた自信はどこかに消えてしまうのである。







