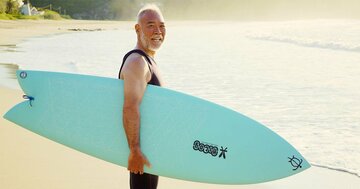たとえば、親しい友だちとおいしいものをつつきながらイッパイやっているとき、とか、胸が熱くなるようなファンレターを読むとき、とか、ひと仕事終えて、お風呂に入り、髪を洗って、清潔なシーツにホカホカの体を横たえるとき、とか、次々とそういうシーンが浮かんできて、調子よく書けそうな気がして気軽に引き受けてしまったのです。
が、いざ書こうとしてよく考えると、それらのシーンは、生きがいではなく生きがいを感じるとき、でしかないのです。テーマは、“本当の生きがいとは?”です。
これは難しいぞ、うーん。つまり、あちこちで生きがいを感じる、そのモトになってるもの、ということか。おおもとは、簡単、自分が生きていること。生きているから生きがいを感じられるのですもの。
思えば、わたしが生きがいを感じるのは、日常のごくありふれた幸福感、充足感なのです。――多分、他の人には見過ごされて感じられないものかもしれません。いや、こうした日々の平凡な暮らしから得られるささやかな歓びを、わたしと同じようにギュと心につかんで、それらをまた知らず知らずのうちに生きるエネルギーとしている人たちが多いに違いない、とも思うのです。
仲間はずれにされていた
学校生活で見つけた“光”
目をつむって、よく考えてみると、わたしはそれらの小さな生きがい感をつかまえて、自分の好きなマンガや詩、というもので表現しようとしているのです。見過ごされてしまう日常のキラキラしたものをマンガにすくいとって、まずは自分自身がもう一度味わってみたい、というのがはじめ。
幼いころに母を亡くし、わたしは性格がズボラなこともあって、とにかく汚い子でした。勉強はあまり好きでなく、運動神経も鈍い。その上に、髪なんかとかしたこともないような女の子でしたから、当然先生や同級生たちから疎まれ、仲間はずれにされていました。
でも、図太かったから、“いいよ”という感じで、ひとりでしゃがんで好きな絵などを描いていました。絵を描きながら、じっと、みんなを見つめていました。しゃがんだ位置から。――そういう姿勢でじいっと見ていると、いろんなものが見えてきました。
すると、クラスのヒーローやヒロインよりも、うしろにいるなんでもない子たちのほうが光って見えたりしました。これはわたしがひねくれているせいかな、と思ったけれど、わたしの心に共鳴するのは、いつもその他大勢の脇役たちでした。
そして、そのころ、放課後は長く、日暮れギリギリまで外で遊んでいましたから、自然の中で、たくさんの密かな発見をしました。