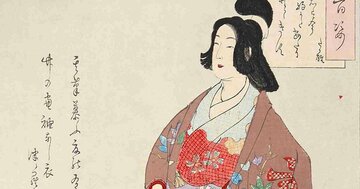噺によって多少の違いはありますが、著名な廓噺の一つですから、落語好きな方でなくとも、一度は耳にしたことがあるかもしれません。
遊廓の天国でも
地獄でもない日常
この噺の元となったという新内節「明烏夢泡雪(ゆめのあわゆき)」や人情本「明烏後正夢(のちのまさゆめ)」では、この時次郎と浦里は真剣に想い合い、さまざまな苦難を乗り越え、なんとか夫婦として結ばれる、という筋書きになっています。父が息子に望んだある種の「社会勉強」どころの話ではなくなってしまったという訳ですね。
世間知らずの息子を遊廓に行かせろという定型句は、江戸時代当時の史料を読んでいても、よく目にするものです。嘘か実か、女性のことのみならず、世の中を知るには遊廓がちょうどよかったとか。時次郎の父・半兵衛も、まさか時次郎が遊女にもてるとは思わず、ちょっと女性や酒宴に馴れたらいいといった、軽い気持ちで息子を送り出したに違いありません。
遊廓に行くことで世間を知る。「明烏」と似たような話は、昭和が終わる頃まではしばしば聞かれたといいます。かつては買春=「男が一度は通る道」だったというイメージは根強く、今も時代小説やドラマや映画作品などで、遊廓、特に吉原を目にする機会は少なくありません。
これまで私は日本近世史のなかでもとりわけ遊廓を研究し、それをまとめた『近世の遊廓と客 遊女評判記にみる作法と慣習』という書籍を2020年に上梓しました。タイトルのとおり、そこで私が注目したのは、遊女や遊廓そのものというよりは、お客です。
身分・職業さまざまな客が遊廓においてどう迎えられたのか、あるいはあしらわれたのか。また客の扱い方に一定の「きまり」はあったのか。そうしたことを探りながら、遊廓=楽園というイメージに疑問を投げかけました。
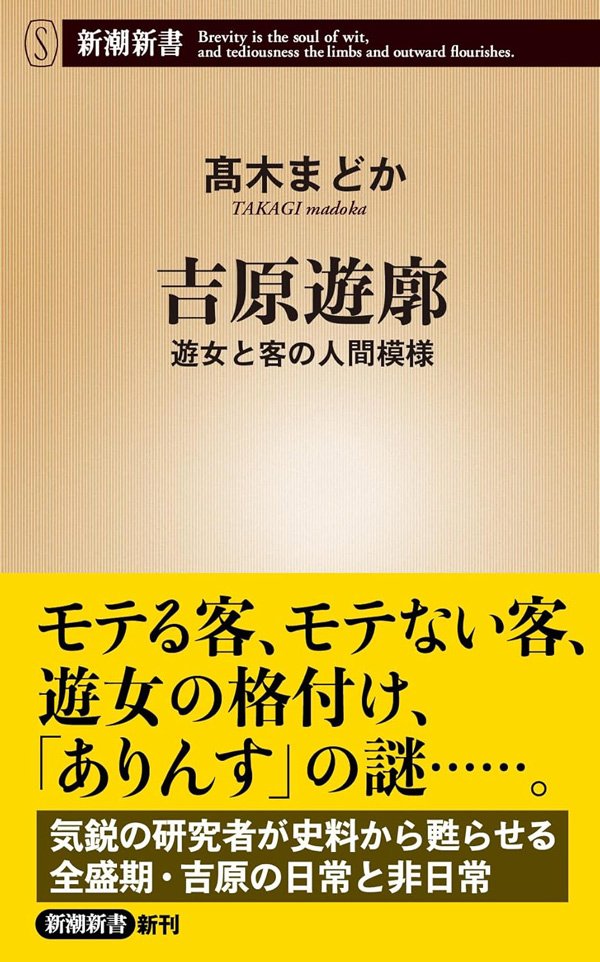 『吉原遊廓 遊女と客の人間模様』(高木まどか、新潮社、新潮新書)
『吉原遊廓 遊女と客の人間模様』(高木まどか、新潮社、新潮新書)
その過程では、とても興味をひかれるものの、研究という文脈でどう扱ったらいいかわからないような、遊廓の何気ない日常をめぐる記述も目にしてきました。
長い歴史を有し、数え切れないほど多くのひとが暮らした遊廓。沢山のひとが毎日を過ごしていたからこそ、そこには、映画のワンシーンになるような美しい光景ばかりでも、目を覆いたくなるような残酷な出来事ばかりでもない、いわば天国でも地獄でもない「日常」があったでしょう。それは程度の差こそあれ、いつの時代も人の世に共通しているはずです。