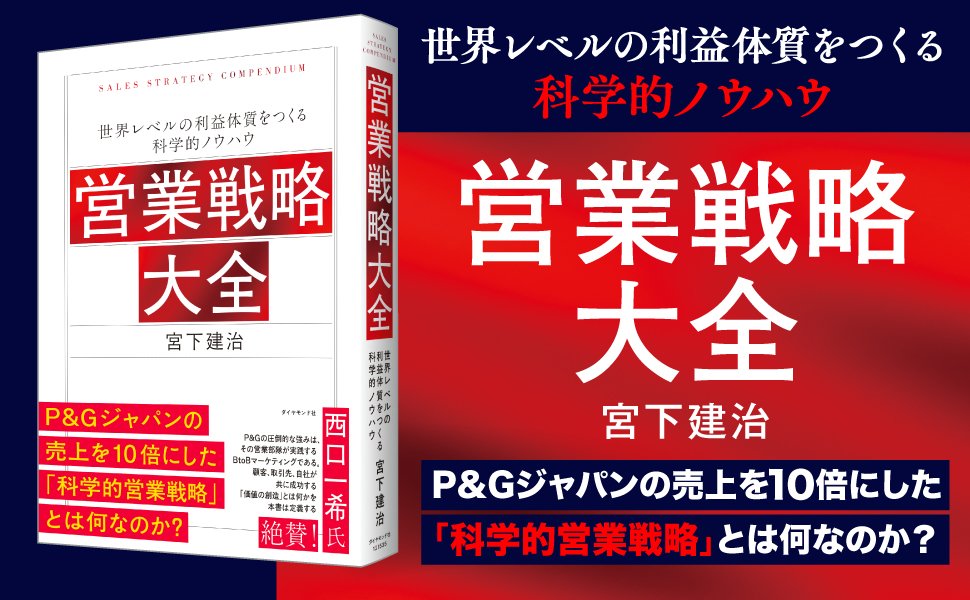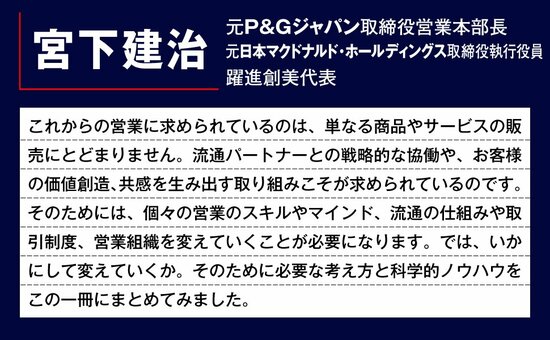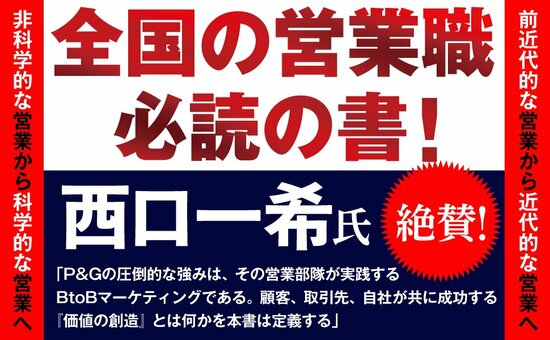営業がバイヤーと交渉をする際、バイヤーからさまざまな「要求」が寄せられることがあります。その背景にある「ビジネス環境からくる潜在的なニーズや課題」を理解することは、バイヤーとの理性的な対話を可能にし、成約率を向上することにつながります。
一方、感情面での理解も重要です。バイヤーの深層心理にはメカニズムがあり、その理解は、単発の商談のみならず、長期的にバイヤーとの関係を密にし、商談の成功率を高めていくことにつながると考えています。
バイヤーの心理、バイヤーの態度・行動変容のヒントについては、社会心理学や行動経済学の理論が参考になります。『営業戦略大全 世界レベルの利益体質をつくる科学的ノウハウ』宮下建治(ダイヤモンド社)から抜粋して解説します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
接触頻度が高いほど商談はうまくいく
1968年、米国の心理学者ロバート・ザイオンスによって提唱された「ザイオンスの法則」と呼ばれるものがあります。「単純接触効果(the mere exposure effect)」とも呼ばれます。個人は、何か(例えば商品やブランド、人)に繰り返し接触すればするほど、その何かに対して好意的な感情を抱く傾向がある、という心理学の原理です。
商売におけるザイオンスの法則の意義と目的は、営業がバイヤーと繰り返し接触する(連絡を絶やさない)ことにより、バイヤーはその会社、営業パーソンや製品に対して親しみや信頼感を持ちやすくなり、長期的なビジネス関係の構築へとつながることです。
やはり人間は、会う頻度が多ければ多いほど、愛着が勝手に湧いてくるものなのです。接触頻度は、ばかにできないということです。
ですから営業はコンタクトを絶やさないこと。面談だけではなく、電話でもメールでも飲み会でもサプライズでも、とにかく接触する。接触するうちに親和性が生まれてきます。
例えば、商談の最後には次回のフォローアップとアポイントを取得する。定期的にショッパー理解のデータ、ニュースレター、商談資料、カスタマイズされた企画(プロモーション、店頭イベント、留型)を活用して、一定のリズムを保ってバイヤーと接触する機会を創出することが大切です。
私はP&Gに勤務していた2000年代はじめ、主要カテゴリーの品揃え、価格、プロモーションなどのマーチャンダイジング戦略戦術を策定する「カテゴリーマネジメント」と、のちに解説する複数の協働取り組みを統合する「JBP(協働ビジネスプラン)」という新しい取り組みを複数の大手チェーンに提案、テストを開始したことがあります。
それまでのプロモーションや新製品を発売するたびごとの単発の商談とは違い、協働のビジネスプランで定例会議を持ち、進捗をレビューしたり、改善策を練ったりするプロセスを重ねていきました。
すると、いつしかバイヤーおよび得意先の関連部署が、この協働プロセスに積極的に関与してくれるようになり、その過程で接触頻度も増え、お互いのトップマネジメントも巻き込んだ会社対会社の「ダイヤモンド型」と呼ばれる関係に深化していったのでした。
※当記事は『営業戦略大全 世界レベルの利益体質をつくる科学的ノウハウ』宮下建治(ダイヤモンド社)からの抜粋です。