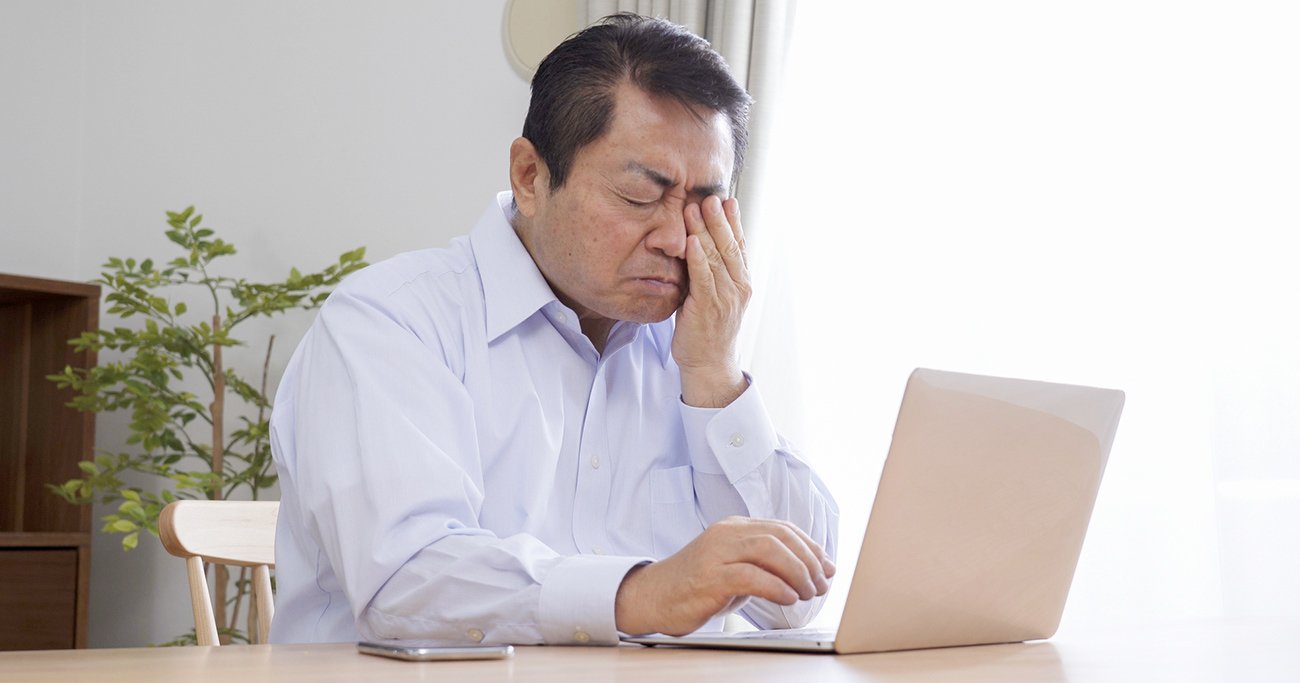 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
コロナ禍以降、認知機能障害に悩む人が増えてきているという。新型コロナウイルスの感染やリモートワークの影響などさまざまな要因が考えられるが、他人の意見を聞かずに自分の意見を押し付ける、知らないことや新しいものに否定的な態度をとる、飲み会で長々と説教や武勇伝を語る…など「老害」化が進んでいる人こそ注意が必要だ。老いと共に脳が老害化していく「老害脳」は一体なぜ発生するのだろうか。※本稿は、加藤俊徳『老害脳』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の一部を抜粋・編集したものです。
個人主義と集団主義の国では
「老害」の発生しやすさは違う?
ここまで、私自身の経験も交えて振り返ると、「老害」という現象自体をアメリカでは感じにくかった理由が、必ずしも日本が高齢化社会のトップランナーだから、というだけでは説明しにくいことに気づきます。
まず前提として、脳の老化の仕組みに人種差はありません。日本でもアメリカでも、ヨーロッパでもロシアでも、アフリカでも南米でも同じく、人の脳が老化していくこと自体に変わりはありません。つまり、脳の仕組みによって日本で「老害」が目立つという仮説は否定されるべきで、それ以外に、何らかの強い原因があると考えてみるべきでしょう。
アメリカで強く感じたのは、たとえ病人であろうと、身体障害者であろうと、あくまで個人主義だという社会のあり方でした。
厳しく言うなら、全ては個人の責任において、法に基づいて処理することを求められます。積極的に評価するなら、自分だけで生きていくことを支援する仕組みはそろっています。
対して、日本は集団主義的で、あらゆるシーンが組織化されていると感じます。しかもその組織は何重もの階層があり、家族や町内、学校や会社などの組織、果ては自治体や地方といった地域社会、そして最終的には天皇制に象徴される国単位においてまで組織化され、ほとんどの人が重層的に所属しています。また、企業の終身雇用制のように、多くの組織では長く安定的に所属することが前提で、所属する側もそれを期待していた面があります。
「すでに終身雇用制は崩壊した」という考えの方もいますし、かつてに比べれば雇用の流動性は高くなったと考えられますが、海外とは違い日本の法制度は簡単に解雇ができないルールになっているため、所属し続けたい人、所属することにメリットを感じる人には引き続き有利になっています。この中では合議制、チームワークが重要視されるため、1人の飛び抜けた意見を重視するよりも、できる限り集団の意見を包摂しながら伝統的な秩序を残そうとします。
日本社会はプーチン氏のような独裁者が出ない代わりに、そこら中の小さな組織に「老害」が温存されうるわけです。







