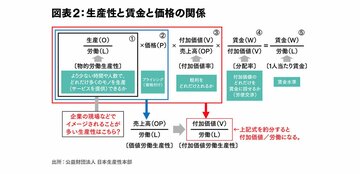顧客満足度と収益性を
バランスさせるアルゴリズム
(3)デジタル技術を活用した価格戦略(ダイナミック・プライシング)
サービス分野では、製造業と異なり、売れ残ったものを在庫として繰り延べることができません。そのため、デジタル技術を活用して、需要の変動に応じて価格を弾力的に運用する販売(ダイナミック・プライシング)で、空席や空室を減らし、収益を最大化させる方策が進んでいます。
先行しているのは、ホテルや旅客事業です。空室率や空席率が高いオフシーズンには販売価格を下げて利用を促し、年末年始や夏休みなど利用者数が多い時には価格を上げて収益性を高めます。
こうしたダイナミック・プライシングは広がりつつあり、例えばJリーグでも横浜F・マリノスや川崎フロンターレなどが活用しています。人気があまりない対戦カードの場合は客席がガラガラにならないように価格を下げて販売し、超人気のカードやシーズン終盤で勝敗が重要になってくると観客数は増えますから価格を上げて収益増を図ります。年間を通してダイナミック・プライシングで販売すると収益性は上がっていきます。
ただし、短期的に過剰な利益を求めると、ブランド価値を落とす危険性もあります。例えば、大雪で交通機関が運休してしまったような時、あるホテルが通常平均単価1万円の客室を3万円で売ることで収益性を改善させたとしても、そうした行為はSNSで拡散され、ホテルチェーン全体のレピュテーション(評判)を落とし、当該地のホテルだけでなく全国で敬遠されるということになりかねません。
利用状況のビッグデータを活用して、顧客満足度と収益性をバランスさせるアルゴリズムを開発することが重要になりますが、上手く両立できれば収益性や生産性が大きく改善することが期待できます。
(4)B2B系のプラットフォーム・ビジネス
サービス領域において価値を生みにくい「非稼働」の時間は、サービス事業者の多くでどうしても生じてしまいます。そうした「隙間時間」を有効活用することで、サービスを提供する事業者の収益と生産性を高めるとともに、そうしたプラットフォームを提供する事業者も収益を生み出すことができます。
対消費者ビジネス(B2C)では、米国発のウーバー・イーツ(Uber Eats)が典型です。デリバリー(配達)を行わない飲食店の料理をウーバー・イーツの配達員が利用者に届けるシステムです。
日本の出前館も同様です。ネット上で商品選択や支払いが完結し、プラットフォーマーが手数料として自社の利益を得るほか、飲食店も料理代金を受け取ります。飲食店は、店内で飲食してもらわなくても売上が立つようになり、やり方次第ではありますが、生産性を向上させることができます。
メルカリ、ラクマ、ヤフオク!、Amazonマーケットプレイスなども、販売機会に乏しい個人や事業者と消費者をつなげ、各種の商品などの売買を可能にするプラットフォームを提供しています。
企業間(B2B)では、助太刀(建設業の職人や協力会社をマッチング)やラクスル(印刷業者のプラットフォーム)などさまざまな事業領域でサービスが提供されており、必ずしも大企業ではないスタートアップ企業でも積極的に事業展開を行っています。
プラットフォーム・ビジネスは、デファクトスタンダードを握ると、他社が参入しにくくなる特性があり、事業が一定規模を超えると収益性や生産性が飛躍的に向上します。日本でも、B2B系のプラットフォーマーでスタートアップ企業が成長してきており、利用者の利便性向上だけでなく、販路に乏しかった中小零細規模のサービス(各種業務)提供者の売上拡大などを通じて、生産性向上を実現しています。
こうしたビジネスモデルの根幹は、UberやAmazonマーケットプレイスなどとあまり違いません。異なる点は、米国企業は一気にスケールする、つまり巨大化することです。これにより規模の経済を活かし効率化・生産性を格段に高めます。そして、競合が出てくる前に先行することで独占・寡占化するのです。
一方、日本企業はスケールするスピードが遅い。理由は、経営者の慎重なマインドがまずあるかと思います。
また、積極的にリスクをとろうとするアニマルスピリットがある経営者がいても、その実現に必要な資金の調達ができないということもあります。リスクの高い事業へのファイナンスの基盤が日本は弱いという面があるのです。ここまで述べてきたデジタル技術の活用のためのシステム構築には、それなりの設備投資資金が必要で、それを確保するための仕組み作りや、金融機関のあり方も課題と言えます。
Amazonを米国で起業し、成長する過程で、創業者のジェフ・ベゾスは長年赤字が続いても、事業の基盤作りの投資を続けました。そのスピリットとその投資を支えたファイナンスが、米国にあって日本にはないものと言えるのではないでしょうか。
 木内康裕
木内康裕きうち・やすひろ。日本生産性本部 生産性総合研究センター 上席研究員。2001年に立教大学大学院経済学研究科修了し、公益財団法人日本生産性本部入職。16年から現職。24年から学習院大学経済学部特別客員教授を兼務。主な著書に『人材投資のジレンマ』(共著、日経BP)、『新時代の高生産性経営』(共著、清文社)、『PX:Productivity Transformation[生産性トランスフォーメーション]』(共著、生産性出版)。
Photo by Aiko Suzuki