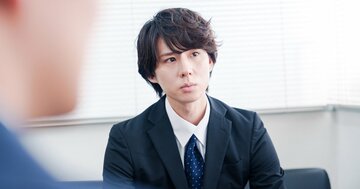「今の発言の重要ポイントを一つだけ挙げると?」
「その意見を三つのポイントにまとめてみると?」
といった質問をしてみてください。
多すぎても、少なすぎてもまとめにくくなるので、三つくらいが適当でしょうか。
数字はあくまで、部下が意見を整理しやすくするための道具にすぎませんから、こだわらないこと。「ポイントは四つです」と言われたら、四つで構いません。
「これ、奥さんに一回見てもらってごらん」
私がトヨタに勤めていたころ、企画書や稟議書を上司に持っていくと、「これ、奥さんに一回見てもらってごらん」「自分の子どもに教えるように書いてみよう」と、よくアドバイスを受けました。
当時、企画書などの書類はたいていA4サイズの紙でしたが、そこに文字をびっしり詰め込んで持っていくと、「“建ぺい率”が高すぎるよ」と書類を返されたこともありました。
建ぺい率とは、建築用語で敷地面積に対する建築面積(建物が覆う部分の面積)の割合を示すものです。書類の建ぺい率が高すぎるとは要するに、A4サイズの紙の上に乗っかっている文字の量が多すぎるということ。
つまり、無駄を削り、簡潔に書くように求められたのです。
シンプルでわかりやすいのが一番なのは、書類だけの話ではありません。会議での発言も同じです。
難しい言葉などを使ってくどくど説明するより、わかりやすい言葉でシンプルにまとまっているほうが、聞いている側の理解は早くなります。
だらだらと話が続いてしまう部下には、
「中学生が相手なら、どう説明する?」
「素人でも理解できるように説明すると?」
といったように聞いてみるのはどうでしょう。
子どもにわかってもらおうと思えば、専門用語は使えません。難しい言い回しも避けて、無駄な部分を極力削ぎ落とし、誰にでもわかる言葉に落とし込まなければなりませんよね。
それをやってみよう、と提案する質問です。
わかりやすさの基準として「高校生」「素人」などを提示しているわけですが、「あなたのお子さん」とか「ご両親」といった身近な人を想定させるのもいいと思います。わかりやすくどう表現すればいいか、よりイメージが湧きやすくなるはずです。
「今のあなたの意見を、1分でまとめてみると?」
といったように、制限時間を設けてみるのもおすすめ。
場合によっては、会議が始まる前に、「一回の発言は1分以内」とルールを決めておくと、まとまりのない意見が頻発せずにすみます。
一方で、このルールは自信のない人に対して、余計に躊躇させてしまう可能性もありますから、参加メンバーや会議のテーマに照らし合わせて、臨機応変に対応するようにしてください。