
中学受験塾における横綱といえば、東のSAPIX(サピックス)と西の浜学園だ。特集『わが子がぐんぐん伸びる!中高一貫校&塾&小学校』の#3では、この東西の横綱が初顔合わせ。SAPIXの広野雅明教育事業本部本部長と浜学園の松本茂学園長が、中学受験ブームから最強の理由、東西の違い、低学年の塾通い、来る2026年入試の予測まで熱く語る対談の前編をお届けする。(ダイヤモンド編集部 宮原啓彰)
「前受け」だった埼玉・千葉の学校が本命化で
東京の2月1日午前の受験率引き下げの要因に
――近年、首都圏と関西を中心に第3次中学受験ブームが起きているといわれますが、その背景をどう考えていますか?
広野雅明・SAPIX教育事業本部本部長 まず中学入試の過熱化を指摘する声が増えていますが、これには疑問を感じています。というのは現在、首都圏とりわけ東京都の中学受験率が高まってる一番の要因は、もともと中学受験率の高い東京都心部の人口が増加していることにあります。人口が増加しているエリアの中学受験率が高いが故、全体の中学受験率が高まっている、という現象にすぎないのではないかと。
実際は首都圏でも外縁部で少子化が進んでいますし、加えて一昔前のように公立の中学校、高校が荒れていたり、公立高校のトップ校の大学進学実績も私立校と比べて見劣りしたりするわけでもありません。なので、かつての中受ブームのように、ご家庭が「何が何でも私立中高一貫校へ」と、こぞって中学入試にシフトしているわけではないと思っています。
 ひろの・まさあき/SAPIX草創期から算数を指導、算数科教科責任者や教務部長などを歴任。現在は入試情報や広報、新規事業などを担う。
ひろの・まさあき/SAPIX草創期から算数を指導、算数科教科責任者や教務部長などを歴任。現在は入試情報や広報、新規事業などを担う。
一方、コロナ禍が下火に向かうにつれ、(東京の入試解禁日である2月1日より前の)1月受験に挑む東京の家庭が増えたことに伴って、特に埼玉と千葉両県の学校が非常に実力を付けています。
かつてのように単なる「前受け(お試し受験)」ではなく、実際の進学先の一つとして考えている家庭が増え、これまでは本命であった東京や神奈川県の2月1日午前入試の受験率を引き下げる要因になっていますね。
――2025年入試の受験率が過去最高になった関西はどうでしょうか?
松本茂・浜学園学園長 関西の中学受験は、首都圏で始まった動きが数年遅れで波及してくると常々感じているので、広野さんのお話は大変参考になります。
例えば、少し前に首都圏で流行した共学校人気が、関西では今まさにピークに達しています。具体的には高槻(大阪府)が台風の目となって、兵庫県など他府県でも学力上位校から中堅校まで共学化する学校が出てきた。ここから今の首都圏のように男女別学校の巻き返しが起きるのか否か、大変注目しています。
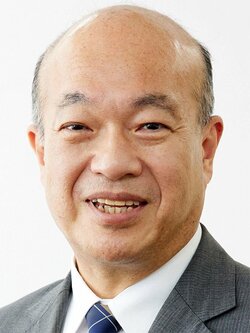 まつもと・しげる/浜学園学園長。同塾講師歴24年。社会科主席主管を務めたのち、2022年4月より現職。同塾は24年入試で、「関西最難関9校」における塾別合格者数で9校全てに最多の合格者を出す「グランドスラム」を達成した。
まつもと・しげる/浜学園学園長。同塾講師歴24年。社会科主席主管を務めたのち、2022年4月より現職。同塾は24年入試で、「関西最難関9校」における塾別合格者数で9校全てに最多の合格者を出す「グランドスラム」を達成した。
一方で、直近の25年入試において関西が首都圏と異なる点をざっくり言うと、「大阪の独り勝ち」の構図だったことです。ある程度予想はしていたけれども、それを大きく超える動きになってしまった。
つまり、首都圏では、広野さんのお話のように東京の受験生の「県またぎ」(県外受験)がコロナ禍の終息に伴って活発化しましたが、関西では逆に大阪府内の受験生の県またぎがコロナ禍のピーク時よりも減った結果、大阪府内の受験者数、受験率だけが突出して高くなったのです。
その理由は、大阪府が24年度より段階的に導入している高校授業料の無償化政策です。国の議論の行方を含めて、目下の関西の中受の流れがいつまで続くのか、大阪の隣接エリアの学校がどう巻き返してくるのか、ということは今後、注視する必要があるでしょう。
――東京でも高校授業料の無償化が大阪と機を同じくして始まりましたが、大阪のような影響は起きなかったのでしょうか?
広野 東京では、最難関や難関の私立校で志願者数が増加したり、あるいは大手中学受験塾の生徒数が急増したりといった動きは、まだ見受けられません。例えば、25年入試で、いわゆる男女最難関の「御三家」の志願者数を見ても、安全志向が強まったことでほぼ軒並み減少しています。
一方で、高校授業料無償化の影響が、志願者数に表れたと思われる学校群が二つあります。
次ページでは、東京の高校授業料無償化の影響で受験者数が増減したと目される具体的な学校名や、25年入試で人気を集めた注目校について、東西の最強塾の重鎮2人が明らかにする。







