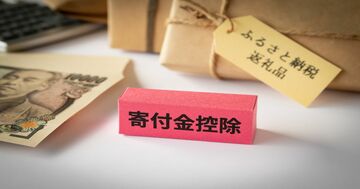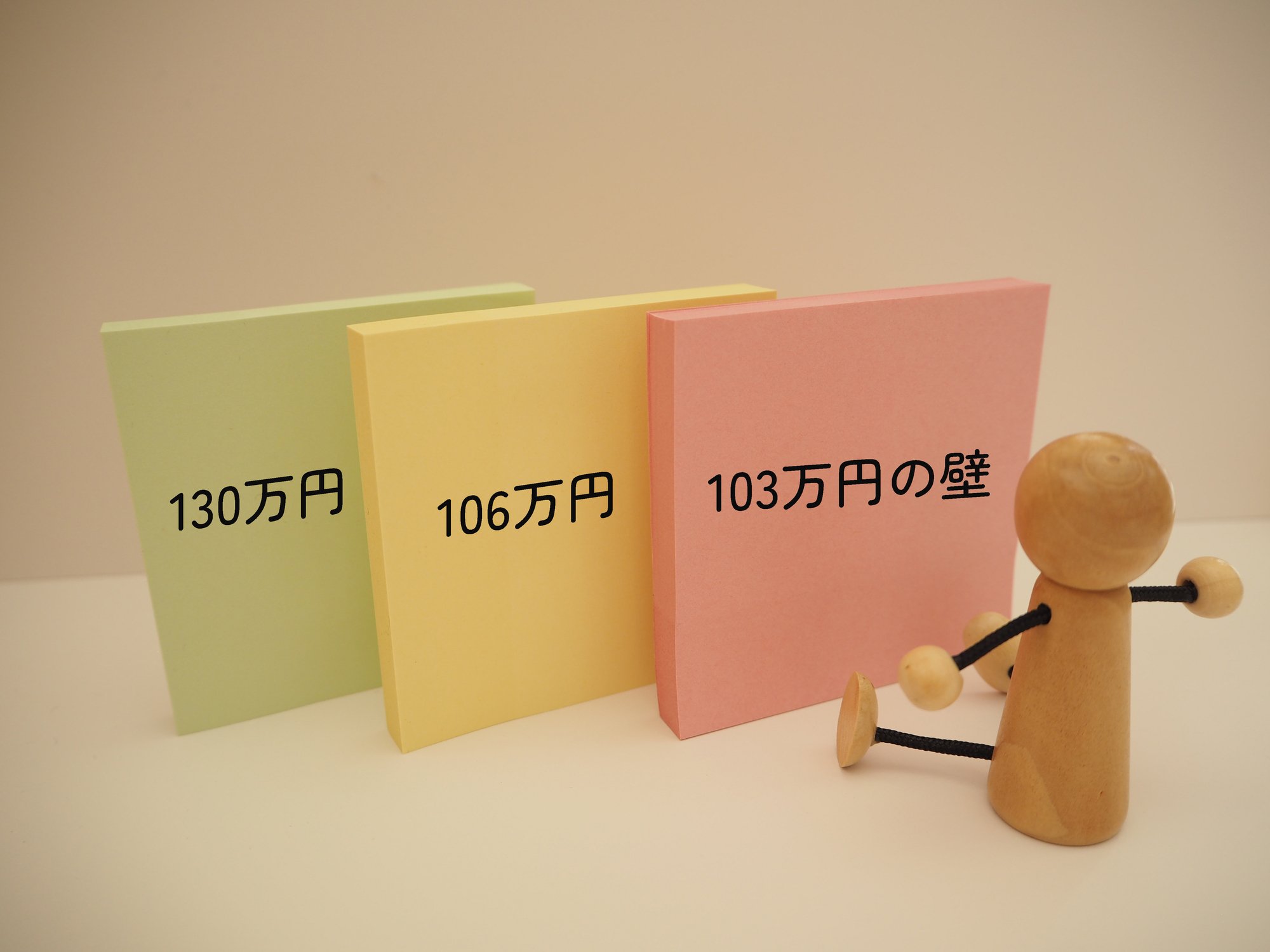 「年収の壁」は本当に「103万円」からなの?(写真はイメージ) Photo:PIXTA
「年収の壁」は本当に「103万円」からなの?(写真はイメージ) Photo:PIXTA
国会で審議されていた「年収の壁」問題が、「103万円」から「160万円」への増額で一応の決着を見た。「壁」にも色々あるが、今回は「税金の壁」について考えてみたい。所得税が年収160万円まで非課税になれば、たしかにパート労働者などに節税の恩恵がありそうだ。だが、「壁」が160万円になっても給与から税金は引かれる。なぜか。そこには意外に見逃しがちな、もう一つの壁があるからだ。(ZEIKENメディアプラス 代表取締役社長 宮口貴志)
所得税「年収の壁」は103万円から160万円へ
2024年の暮れから議論となっていた「年収103万円の壁」の見直し問題は、所得税の課税最低限を「160万円」に引き上げる与党修正案で一応の決着を見た。同修正案を含む税制関連法案が25年3月4日に衆議院を通過したことから、この先法案が正式に成立すれば、25年分の所得税から適用される。
国民民主党は、終始「年収にかかわりなく一律178万円」を要望していたが、自民・公明両党との折り合いがつかず、最終的には、政府案に修正を加えた「年収別の課税最低限」を設定する与党案が採用された格好だ。
「年収の壁」は、「税金の壁」「社会保険料の壁」「配偶者手当の壁」の総称で、「103万円の壁」は税金の壁、つまり「所得税」が課税される収入の最低額を意味する。現行では、個人の年収に関係なく103万円までを一律非課税としているが、今回の改正で「年収200万以下の人は160万円までが非課税」といった、年収別の非課税枠が再構築されることとなった(年収別の非課税枠は次ページの表参照)。
ちなみに、「社会保険料の(支払いが発生する)壁」には、勤務先の規模などによって年収106万円、もしくは130万円があり、また、共働き世帯で、パート労働者が(配偶者の勤務先から)配偶者手当を打ち切られるパート年収の基準額を「配偶者手当の壁」と呼ぶ。
ここでは「税金の壁」に絞って話を進めていきたい。まず、現行のルールで「年収103万円」と「年収160万円」を比較したとき、所得税額にはどれほどの差が出るのか。所得税額決定のプロセスを簡単におさらいしながら試算してみよう。
給与所得者の場合、勤務先以外からの収入がない場合の所得税額は、【1】年間の給与収入(給与、賞与、残業手当など)、【2】基礎控除額、給与所得控除額、【3】所得税率、【4】所得控除額の各要素で決まる。
現行ルールに従って計算すると、給与収入が年間103万円の人なら、基礎控除額(48万円)と給与所得控除額(55万円)の合計(103万円)を収入から差し引く。すると、課税対象となる「所得」は0円、つまり、所得税は0円(非課税)になる。
給与収入が年間160万円の人なら、基礎控除額と給与所得控除額の合計103万円を差し引くと、課税対象「所得」は57万円。「所得税の速算表」を見ると、課税所得1000円から194万9000円までの税率は「5%」、控除額は「0円」なので、57万円×5%=2万8500円(月額平均2375円)が課税される。