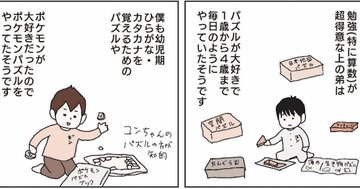漢字や言葉だけでなく、解き方についてもすぐには教えません。
たとえば、算数の問題集を解いていて「教えて?」と持ってきた問題が10問あった場合を考えてみます。
「問題文ちゃんと読んだ?もう1回問題文を読み直して、しっかり考えよう!」と声をかけます。もちろん難易度によりますが、大げさではなく、こう声かけするだけで半分の5問は自力で解けます。
次に「図を書いた?表にして書き出した?」と聞くと、さらに3問は子ども自身が図や表にすることで「わかった」となります。このように、たとえ10問わからないと子どもが言ったとしても、考え方のヒントを与えることで、本当にわからない問題は2問くらいまで絞り込めます。残りの2問は、一緒に考えます。
親が教えるのは一番最後で、まずは子ども1人で考えることを優先させるのです。
国語や理科・社会といった暗記系の場合は、前後の文章や情報から言葉の意味やイメージを類推したのか、自分で何を調べたのか、そこまで考えていなかったら教えません。そんなこともせずにオトクサに持ってきたら叱られます。
わからないことはまず推測する。その上で自分で調べて、確認する。それでもわからない場合のみ、親と一緒に考える。この繰り返しで、だんだんと考える力、調べる力といった自走力の一部が身についてきます。
子どもの「わかったふり」
を見逃さない
「わかったふりをする」とはつまり「理解していない」ということ。理解していないのであれば、親や塾の先生に「わからない」と正直に伝えることが大事なのですが、子どもたちは、なぜかわかったふりをします。もしかしたら本当に、暗記や理解をしたつもりになっているのかもしれません。