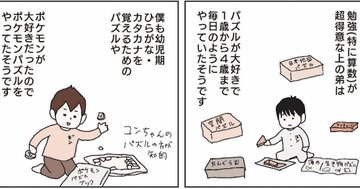最初のうちは
「ママ、この漢字なんて読むのぉ?」→お、えらいねぇ
「ママ、このことわざどういう意味?」→お、これはねぇ
「ママ、次のページもやるのぉ?」→お、早く終わったんなら次やっていいよ
ところが次第に
「あぁ!もう、自分でやってくれよぉ」と変わっていくのです。わが家はまさにこれでした。
子どもの「自走」で最初につまずくのは、わからない漢字や言葉が出てきた時点で手が止まることではないでしょうか。その対策として、次のことを実践しました、
●朝勉の漢字を徹底し、読めない漢字を減らしていく
●電子辞書を導入し、わからない漢字や言葉は「自分で」調べられるようにする
電子辞書は、機能が多すぎで逆に使いづらいのではと思いましたが、子どもたちは色々触って楽しみながら使っていたようです。
●理科や社会の用語は、電子辞書で画像つきの解説を検索する方法を教える
●YouTubeの解説動画の検索方法を教える
方法といっても、検索欄へのキーワード入力について教えるだけです。言葉の解説を読むのと画像や動画で見るのとでは全然理解が違うので、YouTubeも積極的に利用しました。
「考え方のヒント」を与えれば
大半の問題は自分で解ける
子どもが自分で調べるよりも、親に聞いた方が早いのはその通りです。ただ、1人で勉強している時にわからない言葉が出てきたらどうするのか。放置するのか、後で聞くのか、それともその時だけは自分で調べるのか。
オトクサ家の場合、最初の頃は、わからない言葉はチェックしておいて、勉強が終わったらすぐ聞くようにさせていました。しかし、結局確認することを忘れたり、文字の意味がわからないまま進んで無駄な勉強になってしまったりとうまくいきませんでした。子どもが自分で読めない漢字やわからない言葉を調べられるようになってからは、1人での勉強もかなりスムーズに進められるようになりました。