主体性がないことの一番の問題は
主体性を持っている人を批判したくなってしまうこと

三宅 私は「自分の言葉を作ること」だと思います。
田原 三宅さんは、著書『「好き」を言語化する技術』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)でも、自分の言葉で書くことを推奨していますね。
三宅 主体性がないことの一番の問題は、「主体性を持っている人を批判したくなってしまうこと」だと思います。
例えば、映画を見た後、まずはSNSで他人の感想を見てから、それに沿うような「自分の感想」を考える。そういう人が今はとても多いんです。政治について考えるときも、まずはほかの人がどう思っているのかを先に知った後に、「自分の考え」を持とうとする。空気を読みつつ、ものを言っていることがとても多い。それが現代日本の状況です。自分が主体的に考えるのではなく、ほかの大多数のまねをしようとするんです。まさに、田原さんが今、指摘された「みんなの言うことに同調していれば安心だ」ですね。
こうした風潮は私もとても危ういと思います。自分が同調圧力のままにみんなと同じように生きていると、「そうではない人」に怒りをぶつけたくなるのです。
みんなと違う行動をするのは大変かもしれませんが、自分の言葉を持つこと自体は、本来はそんなに難しくないと思うんです。私は小さいころから日記を書くのが趣味で、それによって自分の主体性が養われてきたと感じています。行動よりも先に言葉がある。
映画の感想を話したり、本の感想を書いたり、ほかの人がどう思っているかを調べる前に、自分の考えていることを言葉にしてみる。そこから主体性は生まれてくるはずです。
それにしても、日本ではなぜ同調圧力がこんなに強いのでしょうか。

田原 戦後から高度経済成長期にかけては、経済を成長させるため、みんなが同じ方向を向いて協力する必要があった。だから同調圧力というのができあがっていた。それに日本の会社では、みんなが考えているのと同じ論調の人が、偉くなっていきますよね。
三宅 そういう傾向が行き過ぎて、リーダーが生まれない社会になってしまっているのではないでしょうか。とはいえ、大勢の協力を得ることと自分の言葉を持つこと、両者のバランスをどう取ればいいのかは、たしかに難しい問題だと思います。会社に心を奪われないようにしたくても、会社に属していると、知らず知らずに自分の言葉を失い、心を奪われてしまう。
田原 自分で考えて話すのは難しいですが、他人が言っていることを受け売りで話すのは簡単ですからね。そうなると、自分の言葉は失われてしまう。
三宅 ちなみに、田原さんが自分の言葉を持っていると思う作家は誰ですか。
田原 五木寛之さんですね。三島由紀夫(1925-1970)は「自分自身の言葉を持て」と強く言っていましたね。
新時代の「言論の自由」
同調圧力に反することも言える社会にしよう

三宅 主体性を持つことに躊躇している人は、まず「自分の考えていることを言っていいんだ」と思ってほしいんです。
私もやっぱり昔は、人と違うことを発言するのに勇気が必要でした。中学生や高校生のときも、人と違うことは言ってはいけないような雰囲気があった。
ですから、まずは「自分の考えていることを言っていいんだよ」「自分の感情を言葉にしていいんだよ」と伝えていく。そうした雰囲気を醸成していく。それが、私たちにできる、みんなが主体性を獲得していくための第一歩かと思っています。
田原 僕も、考えていることを言葉にするというのは、ずっとやってきませんでした。
三宅 そうなんですか?
田原 そういう発想がなかったんです。中学生や高校生のときは作家になりたかったのですが、「文才」のある人だけが、自分で言葉を生み出せる人間であり、作家になれるものだと思っていた。そして、いろいろな本を読んでいるうちに、自分には文才がないと自覚しました(笑)。作家になるのをあきらめ、ジャーナリストになりました。
三宅 ニュースやテレビでたくさん発言されていて、多くの本も書かれている。それなのに、それらの言葉は、ご自分の言葉ではないと思っていらっしゃるんですか。
田原 「自分の言葉」って何でしょうね。自分で話しているつもりでも、本で知ったり、取材で聞いたりした言葉に、大きく影響を受けている。果たしてそれが自分の言葉と言っていいものかどうかは、いまだにわかりません。僕は発想力がないんです。
でも、世間で言われていることを疑い、世の大勢と逆の視点でものを見る。それが僕の仕事のやり方です。その方法がジャーナリストの仕事にはとても役立って、ありがたいことに注目されてきました。それでどうにかこれまでやってきたんですよ(笑)。
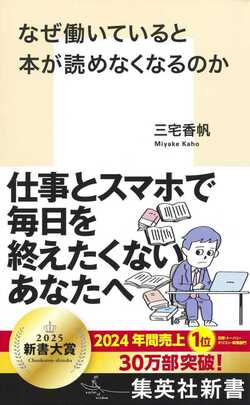 三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』 (集英社)
三宅香帆『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』 (集英社)
三宅 いつその術を身につけたんですか。
田原 テレビ局をクビになったときです。電通の批判をして結果的にクビになりましたが、それで逆に世間に注目され、いろいろなところから声がかかるようになりました。そのときに「自分の考えは間違いではなかった」と感じ、体制や主流とされる意見とは違うことも、どんどん言うようになりました。
三宅 冒頭でもおっしゃっていましたが、会社の中で偉くなりたいとは思わなかったんですか。
田原 まったく思いませんでした。会社の意見に従っていれば偉くなれるかもしれませんが、そうではない生き方もあります。社会を良くしたいと思ったんですね。そのために言論の自由が必要だとも思っていました。忖度(そんたく)なく、言うべきことは言う。
三宅 それがまさに「自分の言葉」なのではないでしょうか。言論の自由が大事なのはなぜですか。
田原 言論の自由があれば、つまり、言いたいことを言える社会になれば、世の中は必ず良くなるはずだからです。
三宅 同感です。言論が規制されないようにすることは当然大事ですし、それと同時に、同調圧力に反することを言ってもいい社会にしていく。これもひとつの「言論の自由」だと思っています。
田原 その通りですね。
三宅 今日はお話できて楽しかったです。ありがとうございました。
田原 こちらこそ、ありがとうございました。これからもどんどん「半身」で、執筆やご発言を続けてください。








