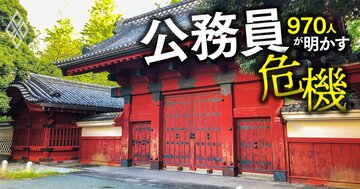Photo by Yoshihisa Wada
Photo by Yoshihisa Wada
霞が関の中央省庁からの人材流出が問題になっている。公務員の働き方改革のキーパーソンである村上誠一郎総務相は、人材獲得のための最大の課題として、役所を指揮する政治家の質の向上を挙げた。特集『公務員の危機』の#3では、村上総務相に、日本に求められるリーダー像や、政治家の卵の選抜方法などについて語ってもらった。(ダイヤモンド編集部副編集長 千本木啓文)
永田町の変化が、霞が関に波及…
公務員法の改正で、役人が萎縮してしまった
――官僚の働きぶりは10~20年前と比べて、どう変わりましたか。
私が衆院議員選挙で初当選した40年近く前、永田町では、「三角大福中(当時、自民党総裁候補だった三木武夫、田中角栄、大平正芳、福田赳夫、中曽根康弘の5人の名前の1文字を取った言葉)」が現役でした。私の師匠の河本敏夫・元経済企画庁長官も含め、素晴らしい先輩たちがいて、毎日が感激の連続でした。
時がたち、永田町も人材が減ったと言わざるを得ません。その要因となったのが、(選挙での公認などで党幹部が国会議員の生殺与奪の権を握ることになった)小選挙区の導入と、その後の郵政選挙です。同選挙では、郵政民営化に反対する候補者を自民党が公認しないばかりか、同じ選挙区に対立候補を送り込みました。あれによって、自由闊達に議論する自民党の美風が失われました。
――中央省庁以前に、まず政治家の質が落ちたと。
政策などに一生懸命に打ち込むより、党幹部が言っていることに黙って従った方がいいという風潮になってしまった。
それが、霞が関にも波及したのではないでしょうか。安倍政権のとき内閣人事局が設置されました。任命権は従来通り各省の大臣に残した上で、幹部職員の任命については総理、官房長官と協議することが法定化されました。これで公務員が、自分たちで担当する分野の実態を踏まえて議論し、政策立案を行う機会が減り、官邸の意向を待つことが多くなったという意見があります。内閣人事局が各省庁で合計600人もいる幹部職員をマネジメントし切れるのか、という問題を指摘する声もあります。
結果的に、永田町と霞が関の人材が薄くなって、能力が落ちつつあるのではないかと非常に心配しています。
――安倍政権、菅政権から岸田政権になり、さらに石破政権が誕生して、雰囲気は変わってきていますか。