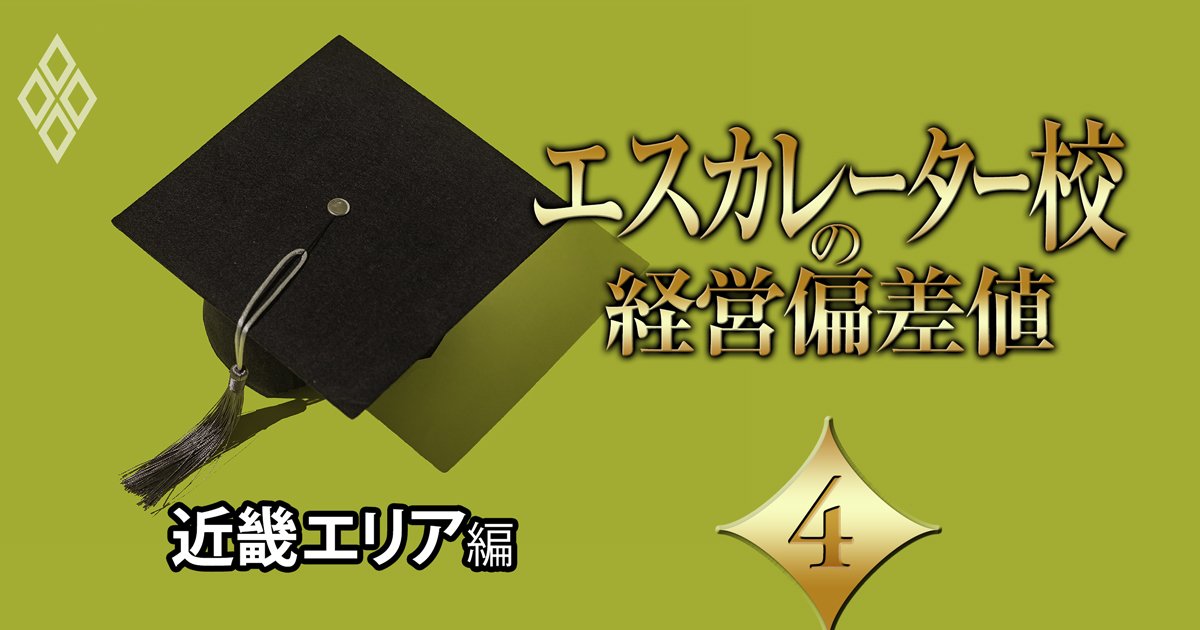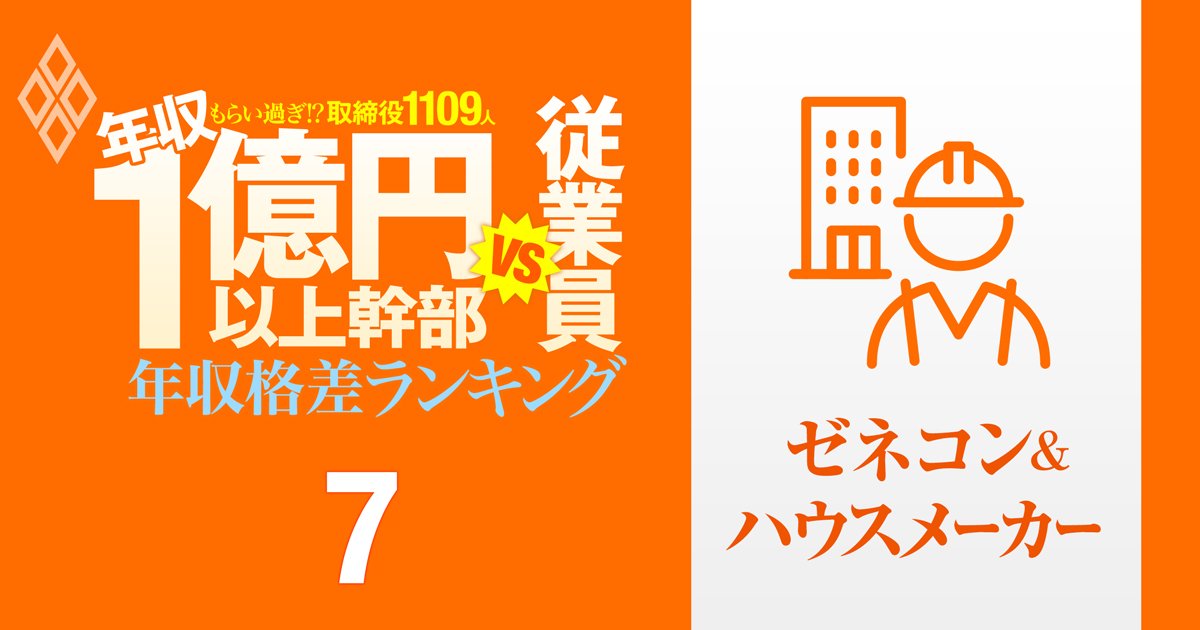日銀は利下げに向かうべき
ここからは、金融政策と財政政策のそれぞれについて、詳しく検討していきたい。
まず金融政策だが、日銀は5月2日に公表した「経済・物価情勢の展望(展望レポート)」において、26年度のCPIインフレ率(コアCPI)の見通しを1.7%へと下振れさせ、目標である2%を下回るとの見通しを示した。ただし、27年度には再び2%近傍(1.9%)に戻るとしており、IMFと同じく、関税ショックは一過性との見方を示している。
26年度のインフレ率が2%を下回るのはなぜなのか。次のようなメカニズムが考えられる。
まず、関税ショックによって輸出が減少し、貯蓄投資バランスが崩れる(貯蓄超過)。そして、その解消のために自然利子率(完全雇用の下で貯蓄と投資を一致させる実質の金利水準)が低下する。
一方、実質利子率(日銀の政策で決まる名目利子率からインフレ予想を差し引いたもの)は、日銀がしばしば指摘するように、現時点で低く、26年度も低い。しかし、26年度は、関税ショックによって自然利子率が低下する結果、実質利子率が自然利子率との対比で高過ぎる状況、すなわち意図せざる金融引き締めという状況が生じてしまう。そのため、インフレ率が2%の目標値を下回るのである。
日銀が昨年3月以降に進めてきた利上げのロジックは、実質利子率が自然利子率に比べて低過ぎるので、その差を縮める調整が必要というものだった。
しかし、26年度はそのロジックがもはや通用しない。関税ショックによって自然利子率が低下し、実質利子率が相対的に高くなるからだ。したがって、日銀はむしろ利下げによって、意図せざる金融引き締めという状況を解消する必要がある。
では、日銀に利下げの余地はどの程度残されているのか。
現在の政策金利は0.5%であり、利下げの余地が十分にあるとは言い難い。しかし、それでも今後2回程度の利下げは可能だ。これは昨年春以降、3度にわたって実施された利上げの成果だ。今後、関税ショックの影響が深刻化するとみられる25年度後半から26年度にかけて、GDP成長率とCPIインフレ率の実績値を見極めながら、段階的な利下げに踏み切る選択肢が現実味を帯びている。
もちろん0.5%の利下げでは足りない可能性もある。その場合は、量的緩和やマイナス金利といった、非伝統的な金融政策手法に頼らざるを得ない。
幸いにも、日銀はこれらの非伝統的手法について、失敗も含め多くの経験をしてきており、定量的な知見も豊富に蓄積されている。
例えば、昨年末に日銀が公表した「金融政策の多角的レビュー」は200ページを超える大部であり、そこには日銀の誇るリサーチ部隊の俊英たちが全力で取り組んだ知見と分析が凝縮されている。
筆者の理解では、非伝統的手法で日銀が犯した失敗の多くは、低過ぎるインフレ予想を、政策的に無理やり引き上げようとしたことに起因している。
しかし現時点では、家計や企業のインフレ予想はかなり高まっており、当時とは事情がまったく異なる。前回のような無理筋の政策対応は不要なので、着実な効果が期待できる。