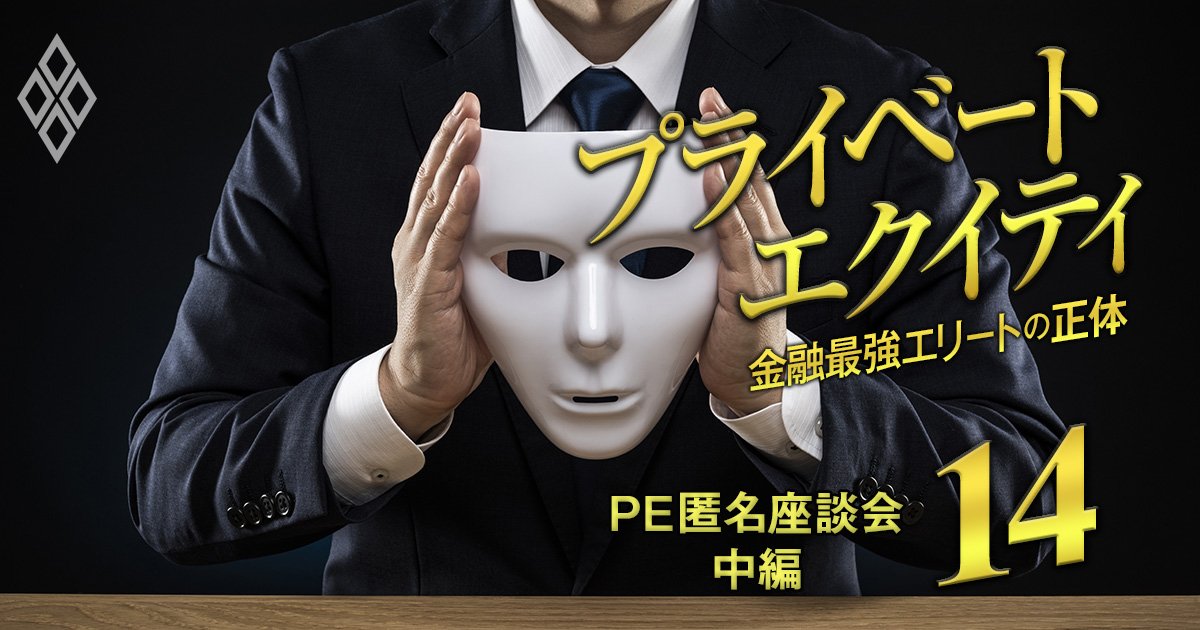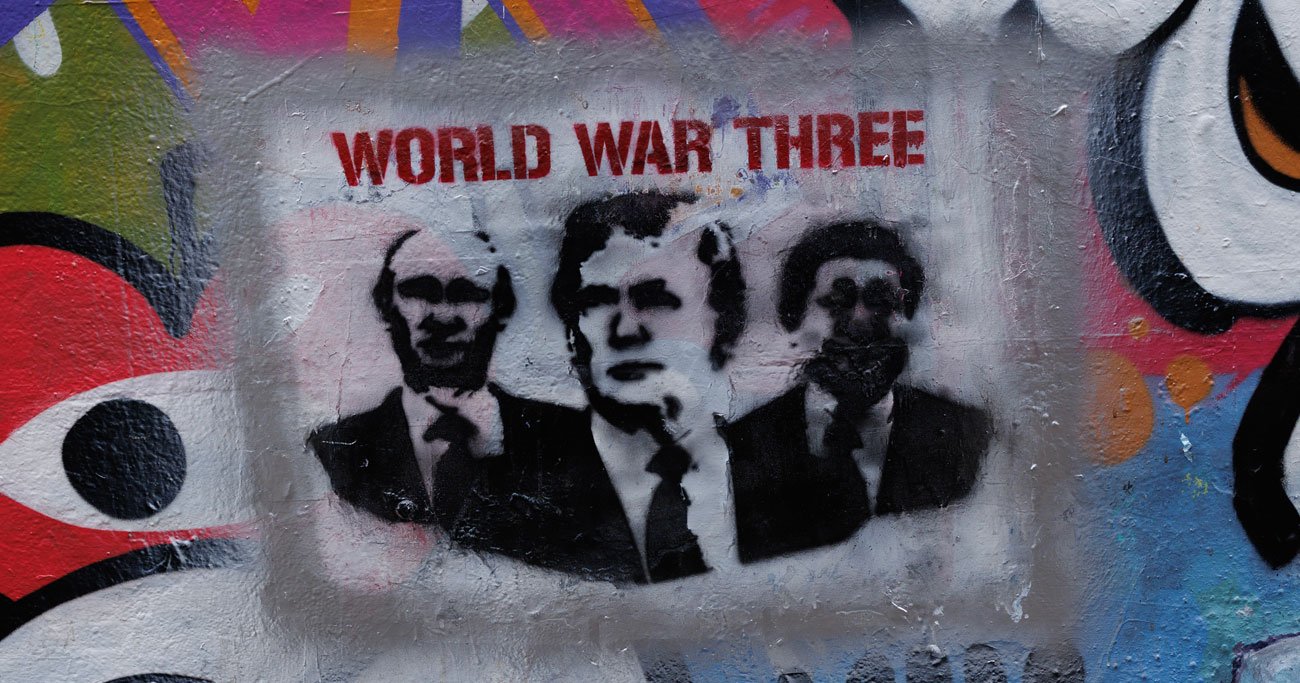一方で、大手企業や官公庁などでは、ズラッとたくさんの人が会議に出席することも多い。とにかく関係しそうな人は全員呼んでおく、全員出席することが重要な文化になっている企業や組織も存在する。
会議においては以前からどう効率化するか、どうやって会議を有効なものにするかといった観点からさまざまな組織で試行錯誤が行われている。
しかし、実はこの「会議」にもベストエフォートはすでに存在している。
今回はその中でも「会議に最適な人数」を例に、ベストエフォートを知り、車輪の再発明を行わないことの意義について考えてみたい。
実は会議の最適な人数というのは、経済学や経営学の分野で少ないながらも研究が行われていて、ほぼ結論としては同様の結果が出ているのである。
会議の最適な人数は「5人」
5人より少なくても多くてもダメ
何か意思決定をするための会議における最適な人数については、2010年に発表された研究が一つの答えを示している。この研究では、各国の中央銀行における金融政策委員会の会議の人数がその国のインフレ率の変動(ボラティリティー)に与える影響が検証された。
その結果、導き出された会議の最適人数は、ずばり「5人」だ。
75カ国のデータを用いて検証した結果、中央銀行の金融政策委員会の政策決定会議における人数が5人未満の場合は、その後のインフレ率の変動が大きかった。つまり、政策委員会が決めた政策の意思決定の質がバラバラであり、それによって不安定な状況が生み出されてしまったということだ。
会議人数が5人ピッタリのとき、このインフレ率の変動は最も小さくなる。つまり安定して質の良い政策決定ができているということだ。
反対に会議の人数が6人以上になったとしてもこの政策決定の質が上がることはなく、会議の参加人数を増やしていくことの効果は限定的であるということもわかっている。
さらに会議人数が偶数か奇数かによる効果の違いも検証しているが、奇数か偶数かによって有意な差は見られない。