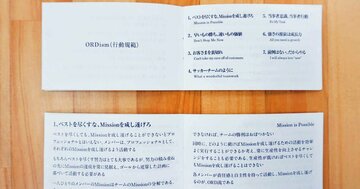アシックスからエンジニアを引き抜き
急成長したナイキ
いまや世界のトップブランドとして君臨しているナイキは、そもそもアシックスからスタートしている。1960年代、大学院を卒業して間もないフィル・ナイトが鬼塚氏を訪問。オニツカの靴をアメリカで売りたいと直談判し、販売代理店契約を結んだ。その後、アシックスからエンジニアを引き抜いてナイキブランドを立ち上げ、急成長していったのである。
2018年頃からは、ナイキの厚底旋風がランニングシューズ市場を席巻し、アシックスは窮地に追い込まれた。ちょうど、廣田康人氏(現会長CEO)が社長COOに就任したタイミングだ。廣田氏は、実は三菱商事で筆者と同期で、活躍を期待していた矢先の事態に、個人的にもやきもきした。
2020年12月期には営業赤字に転落。しかし、その後、収益が急回復している。ヨーロッパなどでランニングシューズの販売が好調で、2023年12月期の営業利益は2期連続で最高益を更新(※注1)、同年8月末には上場後初めて時価総額が1兆円を突破した。
アシックスはなぜ、廣田氏のリーダーシップの下で復活できたのか。大きく3つの要因があったように考えられる。
第一に、競技用の「パフォーマンス・アスリート」という激戦市場で、ナイキの向こうを張る厚底シューズ「メタスピード」をまさにスピード開発、シェア奪還を進めていったこと。その際に、アスリートの心に寄り添うことを最優先した。廣田氏は次のように語っている(※注2)。
「アシックスをあきらめずに履いてくれていた選手とは、頻繁にミーティングをしてもらいました。いまでもカラーは選手に決めてもらっています。例えば、この大会で履きたい色は何ですか、と聞いています。やはり気持ちが高ぶる色があるようです」
第二に、「履き心地」へのこだわり。高パフォーマンスを出す機能だけでなく、「心地よさ」を大切にするのも、アシックスならではだ。同じインタビューで、廣田氏は次のように続ける。
「素材は世界共通ですが、我々には長年培ってきた技術力があります。アシックスの強みはやっぱり日本ブランドだということですよね。日本の技術への信頼は非常に高いと思います。細部にこだわった靴づくりをしており、たとえばアッパーとソールをくっつけるところの仕上げは、非常に丁寧で細やかです。履き心地が違うといわれるところはそこだと思います」
第三に、人と人とのつながりを大切にすること。同じ場所にいないランナーたちが、「バーチャル・ラン」や「バーチャル駅伝」などの企画を通じてつながるようになる。さらに、あたかも一緒の場所にいるようにスポーツを楽しめれば、いままでにない幸せが生まれるはずだと考える。コミュニティをつくり、心を満たすためのツールとしてデジタルを活用しようとしている点に、アシックスらしいこだわりがある。廣田氏は「アシックスは足を止めない」と、茶目っ気たっぷりに語る。