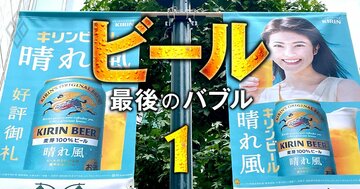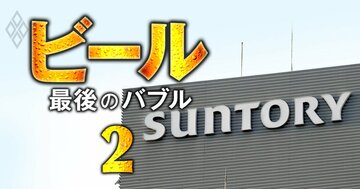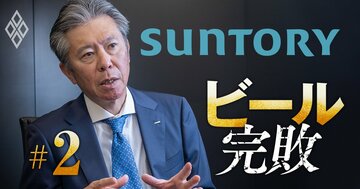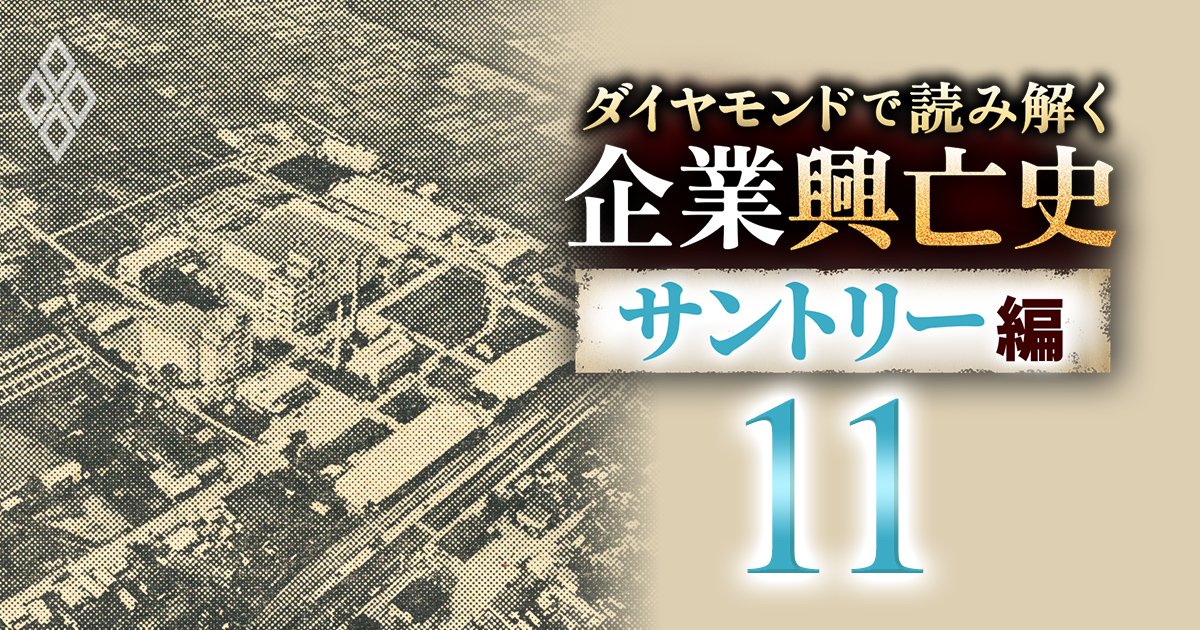
今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。1899年に「鳥井商店」として産声を上げ、創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』の本稿では、「ダイヤモンド」1966年11月14日号に掲載された特集『食品業界をめぐる20の問題点』内の記事「宝 サントリーのビール部門不振はどうなる?」を紹介する。ビール参入「後発組」の宝酒造とサントリーのシェアは共に2%に届かず、宝は工場売却のうわさが上がるなど苦戦が目立っている。両社共に“撤退”の意思はこの時点ではないものの、拡大へのアプローチは大きく異なっていた。記事では、両社の撤退が起き得ない「二つの根拠」に加え、サントリーの強気の拡大作戦について明らかにしている。(ダイヤモンド編集部)
サントリーのビール出荷は4.1%減
宝はビール工場売却のうわさも浮上
答「縮小、撤退の意思はない」
今年(編集部注:1966年)のビール界は、トップの麒麟を除いて、各社軒並み出荷が減少した。中でも後発2社である宝、サントリーの後退が目立った。
この両社が、年初に立てた販売計画は、相当、強気のものであった。昨年に比べ、宝は30%増、サントリーは80%増を狙い、不況と天候不順にたたられた昨年の不振を一気に挽回する計画を打ち出していた。
それが1~10月までの出荷は、前年同期に比べ宝が14.1%のマイナス、サントリーも目標を大幅に下回る4.1%減になっている。
宝がビール事業に進出したのは9年前の1957年である。その間、63年の木崎工場(群馬県)に続いて京都に二つ目の工場を建設した。
一方のサントリーが、ビールへ進出したのは、63年である。
両社がビール部門に投下した設備資金は、それぞれ60億円を超える。両社とも、ビール部門は、まだ大幅な赤字を出している。
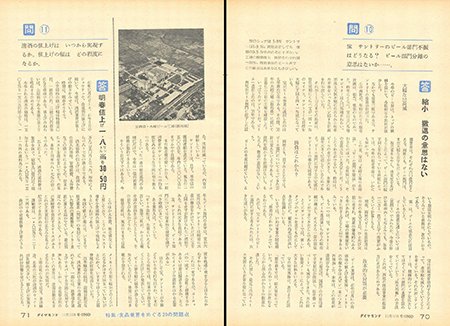 ダイヤモンド「1966/11/14号」
ダイヤモンド「1966/11/14号」
販売量を増やし、操業度を上げることによって、ビール部門の収支向上を狙っている両社にとっては、今年の販売不振は、いかにも痛かった。
この夏、宝は“木崎工場の売却説”“ビール部門分離説”がうわさに上った。会社側では、その意思はないと否定したが、こうしたうわさが出るのも、結局は、ビールの赤字が大きく、本業の収益を大きく圧迫しているためである。ビール部門に対する不安感はサントリーの場合も同様である。
両社とも、目下のところでは、ビール部門について取ってきた方針は変えないようである。ビール部門を縮小する計画はないし、もちろん、撤退の意思はない、という。
ビールの生産は続けていく、という態度を明らかにしているが、そうみている根拠は、次の通りである。