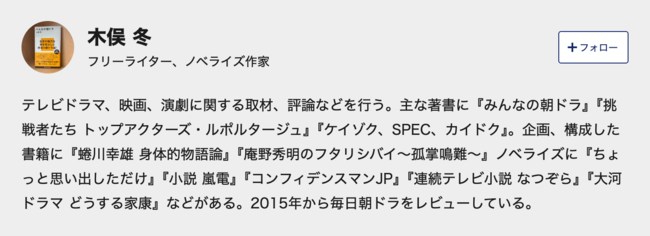東海林(津田健次郎)に叱られるかもしれないが…

高知に帰った4人は原稿作成に励む。
のぶが書いた原稿は薪のことを一文字も書いておらず、知らない人物・八木のことばかりで、東海林は眉をひそめる。今号の目玉は高知出身の薪鉄子だったからだ。
だが、のぶは「今伝えるべき記事はこういう隠れた善意の人のことらあやないかと」と反論した。ここで薪をたたえる記事を書いたら、むしろ薪の意に反すると。ここで、街の人が薪を知らないと言っていたのは、薪があえて目立たないようにしているからだったのではないかと解釈することができる。街の人たちも、あやしい新聞記者から薪を隠そうとしていたのかもしれない。
のぶたちにも素性を隠していたのは、代議士先生としてではなく、一市民として市民のために活動したいからなのだろう。
嵩はのぶの気持ちを理解して「この記事は没にしないほうがいいと思います」と援護射撃。東海林ももともと、市民の声を取り上げていこうとしていたから、採用することにする。ただし、書き直し。
「熱うなって自分の書きたいことを書きゃあええってもんやない。ダラダラ書くな。区切れ。わかりやすい言葉で書け」
ライターとしてならいたい東海林のお言葉であった。
ところで、のぶは次郎(中島歩)のカメラを使って撮影している。戦時中はフィルムが高いのであまり撮れないと言っていた。戦後はどうなのだろう。
昭和21年のフィルムの値段はいくらか。『戦後値段史年表』(朝日新聞編)を見ると、9月の時点で24円10銭とあった。国産の白黒フィルム、12枚撮り。写真館で撮影したら一枚50円〜100円(北海道地区の写真館での名刺判サイズで6×9cm)であったそうだ。
『月刊高知』が2円だから、写真はまだまだぜいたくな代物である。でも撮影に関する経費は当然新聞社持ちで、ある程度自由に撮れるんじゃないだろうか。
東海林編集長だったら「自分の書きたいことを書きゃあええってもんやない」と、この写真に関する一文はカットするかもしれない。でも書きたいから書いちゃいました。