「究極の安全」の追求を
経営の最優先事項に
「勇翔」が事業活動の基盤に据えるのが「信頼」だ。パンフレットに「ひとたび不正・不祥事・重大な事故などの事象を発生させてしまうと、ステークホルダーからの信頼を失い、グループの事業の基盤が崩壊しかねない」と記しているように、「究極の安全」の追求を経営のトッププライオリティに置いている。
「究極の安全」の追求とは「一人ひとりが力を伸ばし、チームワークで安全を先取る取組みを継続し、不断に安全レベルを向上させること」と定義されており、「グループ安全計画2028」のもと、「これまでは想定外であったリスク」を本質の理解により想像し、安全を先取ることで、安全レベルを向上させていくとしている。
しかしながら2024年以降、中央省庁など向けの委託事業及び補助金事業に関する不正な人件費請求、輪軸組立作業における圧入力値の不適切事象、独占禁止法に抵触するおそれのある行為に対する公正取引委員会からの警告などグループ内で不祥事が相次いでいる。
これを受けて7月1日、コンプライアンスの確保とグループ全体のガバナンスの改善と強化のため「グループ全体のガバナンスの改善と強化に向けた有識者委員会」の設置を発表した。
一方で東北新幹線は2024年以降、郡山駅での過走、E5系「はやぶさ」とE6系「こまち」の走行中の分離、E5系を中心としたパンタグラフ破損などトラブルが相次いでいる。
今年6月17日には宇都宮~那須塩原間を走行中のE8系「つばさ」が走行不能となり、5時間半にわたり運転を見合わせるというトラブルが発生。検査の結果、同日に別の3編成でも同様の不具合が発生したことが判明した。これによりE8系の単独運転を中止し、ほとんどの「つばさ」が福島駅折り返しになるなど、1カ月以上にわたり混乱が続いている。
JR東日本は調査を進めてきたが、7月22日になって原因は取り入れた電気を変換する補助電源装置の半導体素子の損傷と発表した。E8系は2023年から導入を開始しているが、2024年11月以降に搬入された車両の半導体素子制御基板に不具合があり、回路の周辺温度が上昇。さらに6月17日が高温となったことが相まって、保護装置が誤作動し電流が遮断されたという。
E8系は川崎車両と日立製作所の2社が製造しているが、どちらの車両でも不具合は発生しており、特定メーカーの製造ミスとは考えにくい。だが、JR東日本は2024年11月以前、以降の車両とも「当社が指定する仕様については同一」と説明する。
補助電源装置の温度試験は通常、メーカー側で実施しており、素材を変更した場合は電気的特性などの確認も実施しているというが、今回はメーカーが「半導体素子の変更と認識しておらず、変更点を考慮した試験を実施していなかった」とのことだ。
現在、営業運転を見合わせているE8系だが、2024年11月以前に搬入された補助電源装置に問題のない編成を8月1日から復帰させ、定期列車の運行を再開する。何とかお盆輸送に間に合った格好だが、臨時列車の運行本数は予定より削減されるため、混雑や混乱が心配される。
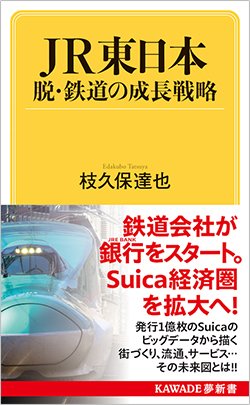 本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
本連載の著者・枝久保達也さんの『JR東日本 脱・鉄道の成長戦略』(河出書房新社)が好評発売中です。
これらのトラブルはそれぞれ原因や背景が異なるが、いずれも最初のトラブルで十分に原因究明ができず、別の車両で再発したという共通点がある。JR東日本はそれぞれのトラブルは別個の事象であり、共通の要因があるとは考えていないとの立場で、輸送障害(列車の運休、旅客列車の30分以上の遅延など)の発生頻度自体は減少傾向にあると説明する。
同社は「グループ安全計画2028」で、5カ年で1.8兆円という過去最大規模の安全投資を進めており、安全については「鉄道をないがしろにしている」との指摘は正しいとは言えない。E8系のトラブルにしても、必ずしもJR東日本のみに責任があるわけではないように、同社にも言い分はあるだろう。
だが、これらは紛うことなき「想定外であったリスク」の顕在化である。また「ヒト起点」で考えれば、利用者の「信頼」はマイナス(とまではいかなくてもあるべき水準から明らかに低い状態)であり、「勇翔」が目指す姿には達していない。「勇翔」を掲げた以上、現状を直視し、信頼を回復するのがJR東日本の務めである。







