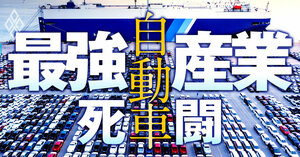もっともそれらは調査会社が把握できる商品コードが登録されたものだから、町の定食屋などの値上げはカバーできない。外食も各店のメニューが値上がりしていると強く感じるようになった。なお、新商品の場合は過去の価格と比較できないが、従来価格より高めに設定される傾向が強い。
各社の価格改定の発表を見ると、値上げの要因は原材料・人件費・水光熱費・物流費のアップ、そして円安だ。これらは独立した事象ではない。円安はガソリン価格を上げ、それが物流高につながっていく。この市況が続けば、基本的には全商品のコストが上がる(その全てを販売価格に反映するかは別だが)。だから特別な割引セールや戦略的な低価格販売は別として、今後、商品が急に安くなることは考えにくい。
一方、私たち生活者としては食品以外の、次の2つの値上がりも見逃せない。
電気代の「いってこい」に騙されるな!
まずは電気代だ。今夏、7月~9月は「電気代補助金」なるものが出ている。7月と8月はkWhあたり2円、9月は2.4円の補助があり、ざっくりだが平均的な家庭であれば3カ月で3000円ほどの恩恵を受けるだろう。
しかし忘れてはならないのは、25年度からは「再生エネルギー発電促進賦課金」(再エネ賦課金)なるものが取られている。これが24年度のkWhあたり3.49円から、3.98円に上昇しているのだ。そのため月に300kWhほど利用している家庭なら、相殺されてしまうかもしれない…。
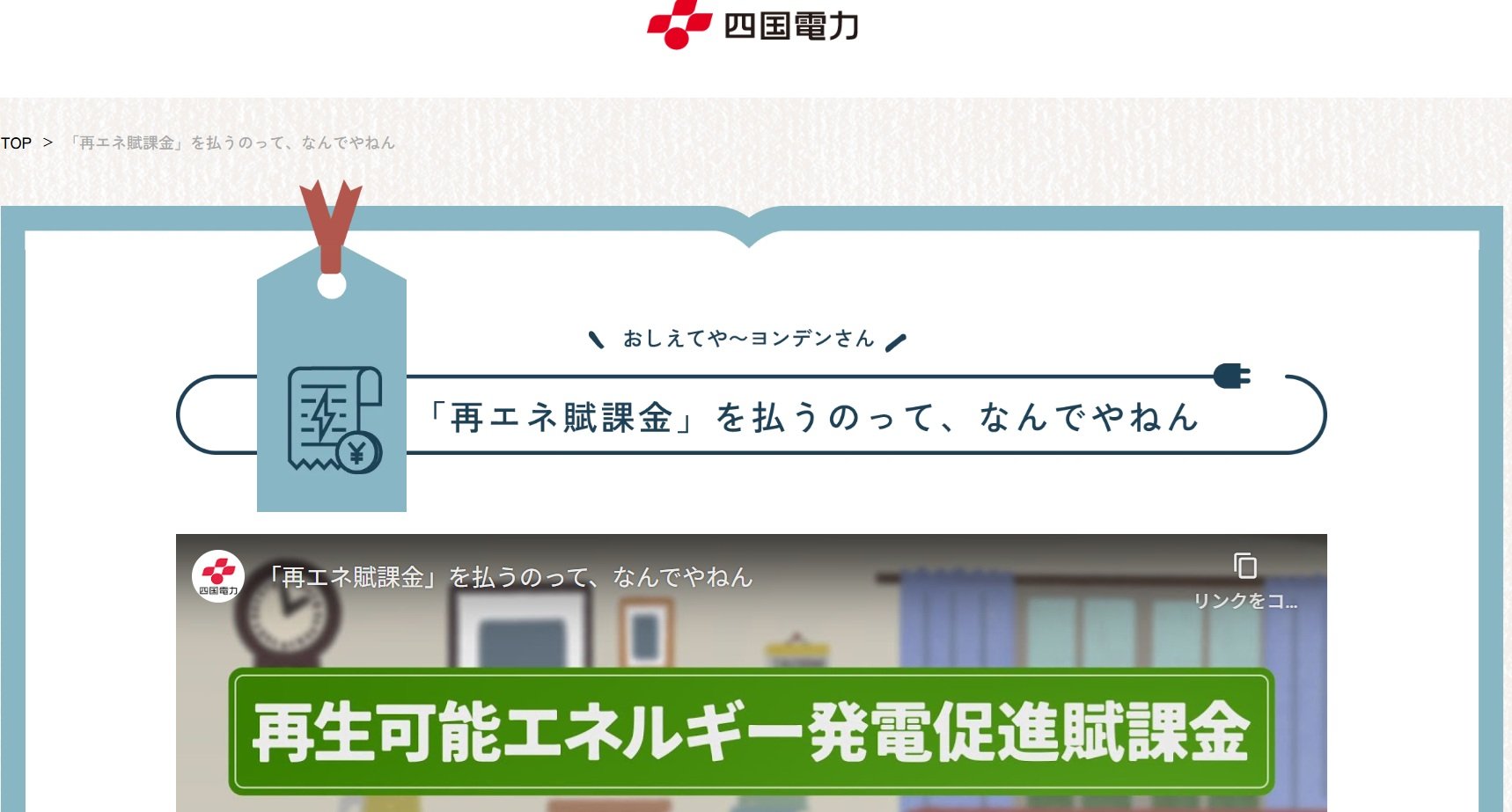 電力会社は「再エネ賦課金」に理解を求める告知をしているが……。画像は四国電力のHP
電力会社は「再エネ賦課金」に理解を求める告知をしているが……。画像は四国電力のHP
「OTC類似薬」が保険適用から除外される?
次に、「OTC類似薬」が保険適用から除外される方針が調整されている。OTC類似薬とは、処方箋が必要だが公的医療保険が適用されるため、自己負担は一部で済むもの。市販薬(OTC医薬品)と成分や効果が似ているものを指す。これが、膨れ上がる医療費を抑制するためのターゲットにされたのだ。
具体的には、湿布薬、保湿剤、ビタミン剤、うがい薬、解熱剤や咳止め、抗アレルギー薬などが検討されている。軽度な症状については市販薬で(自らの責任で)対応してほしい、というのが意図らしい。実際に除外が決まったら丁寧な説明が求められる。
現時点では、日本医師会や一部の団体が「健康被害のリスクがある」と反対している。慢性的な疾患の患者も、自己負担が増えるので猛反対している。ちなみに私の息子はアレルギーがあるため、家計に直撃するだろう。そのうえで個人的な見解としては、うがい薬やビタミン剤くらいはもう、仕方がないのかもしれないと考えている。