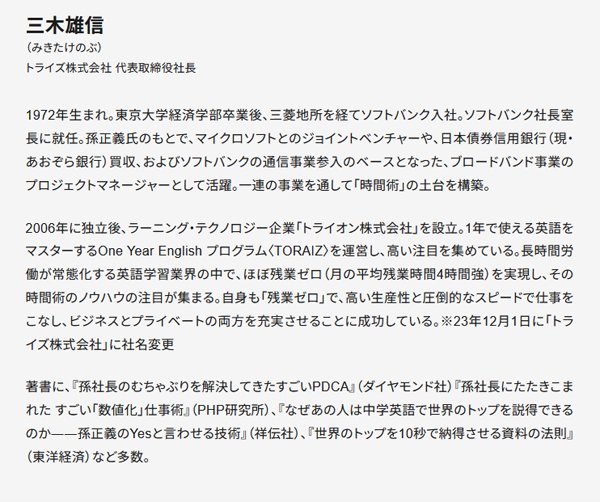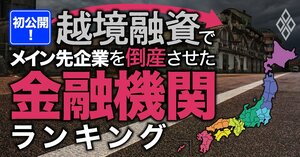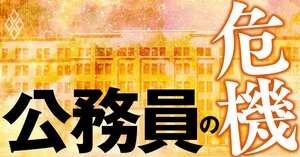第一に、このスピーチは殿堂入りした先輩プレイヤーや球界関係者、取材記者、何より野球ファンとのコミュニケーションを意識した台本が書かれていて、イチロー氏もそれを前提にスピーチしていることです。
イチロー氏は一瞬台本を見た後にも必ず、聴衆に視線を戻していました。また、先輩プレイヤーや関係者に言及する際にも必ず、該当者に視線を向けています。
台本はよく練られていて、随所にユーモアが散りばめられています。先述の文章からにもあった「So easy on the hazing」(いびりは、ほどほどに)の他にも、「without baseball, you would say this guy is such a dumbass」(野球がなければ私は、こいつはただのアホだなと言われたでしょう)といった表現は、聴衆の笑いを誘うだけでなく、スーパースターとしての威圧感を和らげ、親しみやすさを醸し出す効果がありました。
また、日本人メジャーリーガ―のパイオニアである野茂英雄氏への憧れ、あるいは自ら過去の苦悩を正直に語った場面もあり、聴衆との感情的なつながりを深めています。
この結果、イチロー氏に対して「冷めたい人」といった印象を持っていた野球ファンが、「he came across warm and likable」(彼は温かくて人当たりがいい)とコメントするなど態度を変えている点は、スピーチひとつでイメージを刷新できることを示しています。
第二に、イチロー氏の人生観についてメッセージ性がありました。例えば、「夢と目標の違い」について以下のように明確に整理し、続きをリードしています。
Dreams are fun, but goals are difficult and challenging.
夢は楽しい。しかし、ゴールは困難でチャレンジングだ。
スピーチが単なる回顧録や感謝の列挙ではなく、若い世代や聴衆に向けた普遍的なメッセージとなっているのです。
第三に、メジャーリーグで日本人が殿堂入りしたこと自体が、画期的な出来事でした。さらに母語ではない英語で、冗談も交えながら19分間のスピーチをやり遂げたことは、米国の移民文化や多様性を表す姿勢として高く評価されたのだと思います。
イチロー氏は、「野球がなければ、私はただのアホだった」と率直に語りました。こういう発言ができるのは、努力と実績で上り詰めた確固たる自信があるからでしょう。
イチロー氏のスピーチは、「英語ができないから無理」と諦めがちな日本人にとって、極めて現実的かつ勇気を与えるモデルです。まずは自分の専門性を磨くこと。その力を武器に一歩外へ出れば、環境も言葉も後から必ずついてくる。そんなメッセージが、あのスピーチ全体に込められていたと思います。