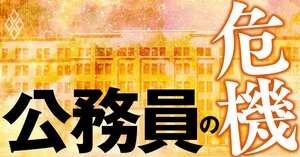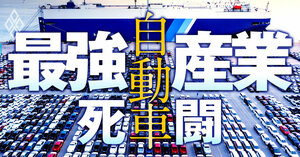賃金構造基本調査を基にすると、実質賃金は、
大企業はプラスだが中小企業ではマイナス
実質賃金のデータとして通常使われるのは、毎月勤労統計調査だ。しかしこの統計では、従業員数5人以上の事業所と20人以上の事業所を区別しているだけだ。
賃金構造基本調査は、企業を大企業(常用労働者1000人以上)、中企業(同100~999人)、小企業(同10~99人)に区分している。
この区分によって、24年の賃金の対前年増加率を見ると、次の通りだ。大企業が5.3%、中企業が3.8%、小企業が1.8%。
したがって、これを基にした実質賃金上昇率は、消費者物価上昇率が3%とすると、大企業では有意にプラスになる。そして、中企業ではなんとかプラスになるが、小企業は、ほぼ確実にマイナスになる。
日本では、名目賃金の水準が企業規模によって大きく違う。つまり大企業が高く(2024年で、男女計、年齢計で月収36.5万円)、次に中企業(同32.3万円)、小企業(同29.9万円)となっている。賃金上昇率もこの順ということは、企業規模による賃金格差が、ここ数年の賃上げによって拡大していることを意味する。
産業別でも大きな差、高い電気・ガスや金融保険
学歴、正規・非正規別の格差も広がる
次に産業別の状況を見ると、賃上げ率が高いのは次の業種だ。まず、電気・ガス・熱供給・水道業(6.7%)、金融業、保険業(4.4%)。これらの産業の賃金水準はもともと高い。それに加えて賃金上昇率が高いので、他産業との賃金差が拡大することになる。なお、不動産業、卸売業、小売業でも賃上げ率は高い。
これに対して、サービス業では、次のように賃上げ率が概して低い。学術研究、専門・技術サービス業(1.3%)、生活関連サービス業、娯楽業(2.5%)、教育、学習支援業(-0.3%)、医療、福祉(2.8%)、複合サービス事業(1.6%)といった具合だ。
賃上げ率は、学歴別でも大きな差がある。高校卒が2.5%、専門学校卒が2.2%なのに対して、大学卒は4.4%だ。したがって、物価上昇率が3%近くであれば、大学卒の実質賃金は上昇するが、高卒・専門学校卒では低下するという結果になる。
また、雇用形態別で賃金上昇率を見ると、男女計で、正社員が3.7%増に対して、それ以外は2.9%となっている。男性で見ても女性で見ても正社員の方が高い。
恩恵は社会的に恵まれた層に偏る
零細サービス業は賃金それほど上がらず
このように賃上げ率は、いくつかの側面から見て、「社会的強者」の場合に高く、「社会的弱者」の場合に低くなっている。
以上で見た格差は相関しているものもある。例えば、電気・ガス業や金融業は、企業規模で見ても大企業が多い。だから、これらの業種で賃上げ率が高いのは、企業規模が大きいことの結果なのかもしれない。
またこうしたセクターでは、大卒者の比率が高いかもしれない。そうだとすれば、これらの業界で賃上げ率が高くなる大きな要因は、大卒者の賃上げ率が高いということになる。
さらに、参入規制が影響を与えている可能性も無視できない。