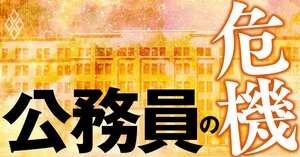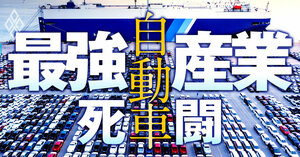こうした問題については、さらに分析を行うことが必要だが、結果的に見て、こうした分野の学歴の高い人たちの給与が上昇していることは間違いない。つまり、ここ数年の賃上げの恩恵は、社会全体に平均的に及んでいるのではなく、特定の人たちに偏って生じているのだ。
これらの人々は、社会的強者と言ってよいだろう。これらの人々が、賃金がより高くなり、他の人々との間で賃金格差が拡大していると考えることができる。
それに対して零細サービス業、飲食店・宿泊業などの場合には、これまでも賃金が低かったのだが、最近の賃上げ率も、経済の平均に比べて顕著に高いとは言えない。むしろ低い場合が多い。
これらの分野では人手不足が厳しいと言われるのだが、それにもかかわらず、賃上げ率が高くない。つまり、マーケットが労働需給のアンバランス調整機能を果たしていないと言うことができるのではないか。
賃金格差は生産性引き上げの力の差か
価格転嫁できる力の差か?
こうした賃上げ格差が生じるのはなぜだろうか? 一つの原因として考えられるのは、生産性引き上げの可能性に差があることだ。
生産性を引き上げるためには、投資を行うことによって資本装備率を高めることや、新しい技術の導入、事業効率の引き上げなどが必要だ。そのためには、資金調達力があること、従業員の能力が高いことなどが必要だ。そして、こうした条件に恵まれているのが電気・ガス業であり、金融業であり、大企業であるという解釈ができるだろう。
ただ、それだけでなく、取引における立場の強弱も影響を及ぼしている可能性が大きい。生産性が上昇しなくても、賃上げを販売価格に転嫁することによって賃上げを実現することができるが、これは大企業であれば行いやすい。取引上の立場が強いからだ。
それに対して、中小や零細企業が大企業の下請けである場合、賃上げを売り上げに転嫁しようとすれば、取引そのものを失ってしまう可能性が高い。したがって転嫁ができない。こうした事情が賃上げ格差の原因なのだとすれば、大きな問題だ。
政府は、中小企業の転嫁を容易にすることによって賃上げを促進するとしているが、一方でそうしたことが広く行われるようになれば、コストプッシュ・インフレが進む恐れがある。この問題にどう対処すべきかは、極めて難しい問題だと言わざるを得ない。
経済の効率向上も人手不足解消も
日本経済の問題を解決したとは言えず
以上で見たことは、最近時点における賃上げが、日本経済の効率性を高めるように働いているわけではないことを意味する。「人手不足が問題」と言われているが、これが特に顕著なのは、零細企業による対人サービスの分野だ。あるいは介護などの分野だ。
本来であれば、こうした分野の賃上げ率が高くなり、その分野での労働不足を解消するようにならなければならない。ところが実際には、そのような動きになっているわけではない。
現在の日本で働いている賃上げのメカニズムについて、より正確な分析と適切な対処が必要だ。
(一橋大学名誉教授 野口悠紀雄)