「そもそも○○って何?」
という問いを話し合う
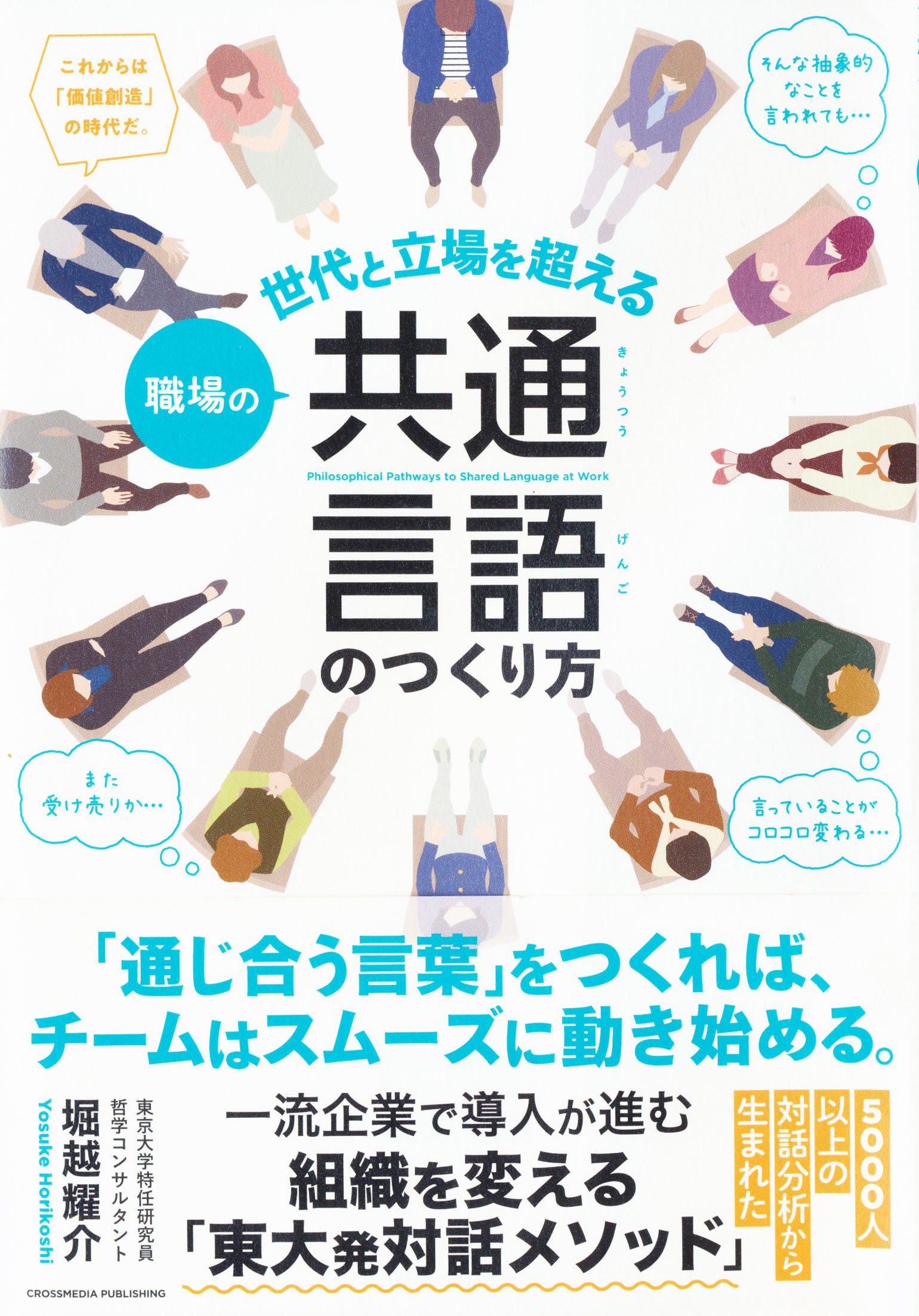 『職場の共通言語のつくり方』(堀越耀介 著、クロスメディア・パブリッシング、税込1848円)
『職場の共通言語のつくり方』(堀越耀介 著、クロスメディア・パブリッシング、税込1848円)
責任、価値、主体性、信頼といった、職場でよく用いられる言葉は、使う人それぞれが違った意味やニュアンスで使っていることが多い。それが「伝わらない」「意図通りに動いてもらえない」「話が噛み合わない」最大の原因だという。
そこで哲学対話では、「そもそも主体性って何?」といった問いを話し合い、その言葉の意味やイメージを共通化する。正解に辿り着く必要はなく、話し合いによって共通するものと異なるものが明らかになることに意味がある。違っているならば、それを前提に話せばいいからだ。
「そもそも○○って何?」の他にも、関連する言葉や、似ているけど意味が微妙に異なる言葉などを挙げたり、同じ言葉にいろいろな種類があることを認識したりもする。例えば、「信頼」という言葉を「どういう面を信頼するか」によって「経験への信頼」「性格への信頼」「意図への信頼」「関係への信頼」に分類するなどの話し合いが、実際の企業向けワークショップでは行われているそうだ。
こうした哲学対話を積み重ねることで、組織の結束が高まるとともに、当事者意識も育つ。哲学対話は「本質」を探るものなので、知識や経験の差が障害にならない。新人から新鮮な意見が出たりもするだろう。さらに、哲学対話の副産物には、各人に、物事の本質を問う「思考のクセ」がつくこともある。
休み明け、ちょっとした会話でも、「そもそも〇〇ってなんだっけ?」といった本質的な問いを挟んでみてはいかがだろうか?
情報工場
2005年創業。厳選した書籍のハイライトを3000字にまとめて配信する書籍ダイジェストサービス「SERENDIP(セレンディップ)」を提供。国内の書籍だけではなく、まだ日本で出版されていない、欧米・アジアなどの海外で話題の書籍もいち早く日本語のダイジェストにして配信。上場企業の経営層・管理職を中心に約8万人のビジネスパーソンが利用中。 https://www.serendip.site




