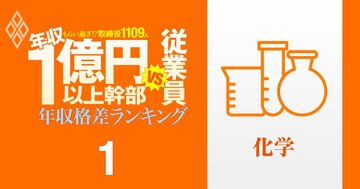Photo by Tohru Sasaki
Photo by Tohru Sasaki
旭化成が構造改革のギアを上げている。2025年5月に発表した中期経営計画では、石油化学や電子材料などのマテリアル、医薬品や医療機器のヘルスケア、住宅の3本柱での事業の入れ替えやM&A(企業の合併・買収)の加速を掲げ、27年度に営業利益2700億円を目指す。旭化成はM&Aを駆使して事業領域をこれまで大きく変えてきた。特集『化学サバイバル!』の本稿では工藤幸四郎社長を直撃。M&A戦略の要諦に加え、今後半導体などの電子材料やヘルスケア、住宅部門で進める「次のM&A」の方向性を聞いた。また、足元で三井化学と三菱ケミカルグループとの3社連携で進んでいる、石油化学事業の構造改革の進捗や将来像についても明らかにしてもらった。(聞き手/ダイヤモンド編集部 金山隆一)
西日本のコンビナート再編
「3社連携をやり遂げる覚悟」
――プラスチックなどの原料となる基礎化学品エチレンの生産設備を巡り、旭化成と三菱ケミカルグループの設備がある水島(岡山県)と三井化学の堺・泉北(大阪府)の設備を再編する3社連携の議論が大詰めです。現在の進捗は。
3社ともやり遂げようというコンセンサスは変わらず、1年近くやってきたので年内か年度内に説明できるように進めています。ただ、千葉や川崎と違ってコンビナートが離れているのでセンシティブな部分がある。後で「話が違う」とならないよう確認しながら進めています。大枠は出来上がっています。
――水島か大阪か、どちらかに集約するのでしょうか。
それは言えませんが、どちらかだけを残す覚悟を持ってやっています。そもそも、撤収には費用がかかります。残った設備を(3社が)どれくらい必要とするかによっても負担は違ってきます。公平で合理性の高い決断にするために汗をかいています。
――水島の設備は三菱ケミカルと旭化成がそれぞれ持っていたものを一つに統合した歴史があります。旭化成は川崎ではアクリル樹脂やその原料など4事業の撤退を発表し、マテリアル事業では電子材料などを中心に据える経営方針です。三菱ケミカルや三井化学からするとくみしやすいのでは。
われわれは誘導品で三井化学や三菱ケミカルに比べ競争力のある製品を持っていないのは事実です。だから(電子材料などの)他分野に行きます。これからもまだまだ構造改革を進めるべき製品も幾つか残っています。3社連合が良い形になる努力をする覚悟は持っています。
――川崎の撤退後はどうしますか。
川崎は水素やイオン交換膜の拠点にしようとしています。そのために補助金も獲得しました。新しい製造拠点ができるタイミングに合わせて4製品の撤収をしていきます。従業員の再配置も含めて緻密な計算をしています。
――中期経営計画では、ヘルスケア、住宅に比べて、マテリアルに含まれる石油化学事業が構造改革の中心になります。
石油化学を含むマテリアル、住宅、ヘルスケアという業態が異なる三つの領域を経営する旭化成は化学業界の中でも異質の存在だ。これまでもM&A(企業の合併・買収)を駆使し、事業構造を変革してきた。次ページでは工藤社長に、買収巧者である旭化成のM&A戦略の要諦や、今後成長の主軸に据える3領域経営の加速に向け、買収についての考え方や方向性を明かしてもらう。また、構造改革を進める具体的な領域や、次代の経営を担う人材に求められる資質などについても幅広く語ってもらった。