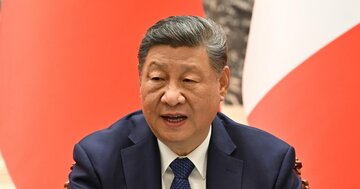富国強兵のため外を向いた明治時代
外圧を受け国際貢献に迫られた1980年代
先進国で日本ほど「国際化」の必要性が語られている国も珍しい。
米国や欧州では経済の論理として国境の壁は著しく下がり、モノ、人、サービス、資本が縦横に動き回る。日本と同じ島国であっても、英国は世界を制覇した歴史の重みが残っており、ロンドン・シティの金融市場に象徴されるように、英国の視野は世界に広がる。
現代の英国もユーロへの加入など、国家主権の制限には慎重であるが、移民政策や外国投資受け入れ政策などでは極めて開明的である。先進国の経済構造からして、マーケットを広くとり人を増やさなければ将来はないことが、長年にわたって認識されて来たからである。
日本にはこれまで何回も「国際化」のうねりがあった。鎖国下の日本では選択的に外国の文化・技術を取り入れてきたが、1853年のペリー提督の来航を通じる米国の強い圧力のもと、開国を余儀なくされた。
その後、明治4年から2年にわたった岩倉具視ほか閣僚の半分をメンバーとした遣米欧使節団は富国強兵を唱え、欧米列強から文化・技術を大幅に取り入れる政策に踏み切った。
これが日本の国際化の第一のうねりなのだろう。しかしこの「国際化」も、国境の垣根を下げ、自然な交流を図るということではなく、富国強兵政策に必要な技術の取得という色彩が強かった。
終戦後の日本は国内経済再建に邁進したが、「国際化」の第二のうねりは1980年代である。この際には、国際化というよりむしろ「国際貢献」という掛け声のもとに国を開き、外国に出ていくという概念であった。
世界第二の経済大国となった日本は、米国との膨大な貿易黒字と米国議会の強い反発を受け、市場開放を進めざるを得なくなる。