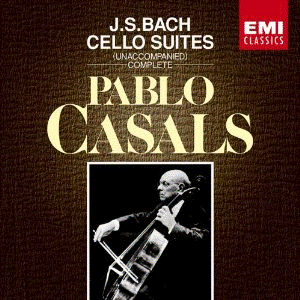21世紀は改めて科学技術の時代と感じることが多い今日この頃です。
例えば、iPS細胞の発見と関連の研究開発は病気の克服に大いに希望を抱かせます。
コンピュータの活用は、ビジネスチャンスを拡大し、世の中を便利にしています。それに、日々の生活がストレスの少ない社会になるようにと、様々な試みが随所で行われています。例えば、コンビニのドアが開くと、ちょっとした音楽で客を歓迎してくれます。電車の駅でも発車を知らせるのはベルの音ではなく数小節の音楽です。
実際、街には音楽が溢れています。鋭角的なリズムと大音量と電子の音が中心です。そんな喧騒は街の活力の表れでしょう。そして、街に溢れる音楽の一つひとつには、その音楽を流す店主の意向もあれば、その音楽の作曲者や演奏者の思いもある訳です。が、全体としては騒音にしか聞こえません。合成の誤謬の古典的な例にも思えます。
そんな時には、街を通り抜けて地元に戻り、スイートホームに辿り着いて、静謐な音楽を聴いてみたくなりますよね。街の雑踏に溢れる音楽とは完全に異なる音宇宙を感じてみたくなりますよね。
と、いうわけで、今週の音盤は、パブロ・カザルスによるJSバッハの「無伴奏チェロ組曲」です(写真)。
ムダな音は一つとして存在せず
バッハの無伴奏チェロ組曲は、音楽の本質を1台のチェロを通じて雄弁に伝える音楽の物語です。
音楽の本質とは何か、というのは深遠な命題です。が、敢えて単純に言えば、それは旋律と伴奏(和音)とリズムの3つの要素から成る音の連なりです。そして、それを美しい音色で演奏することで聴衆に感動を伝える訳です。
実は、バッハに限らず、音楽に真摯に向かう音楽家ならば常に音楽の本質を究めるべく、最小の音数で音楽を成立させることに挑戦して来ました。現代の例で言えば、エリック・サティ(本コラム第60回)を創始者とするミニマルミュージック、ブライアン・イーノらのアンビエントミュージックもこの流れです。