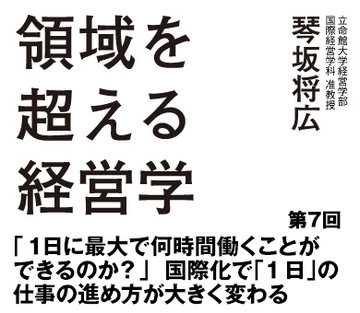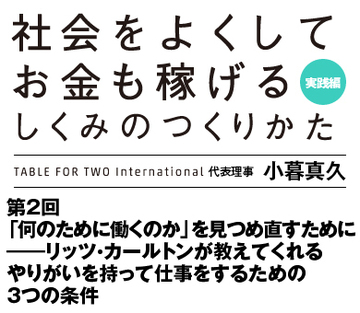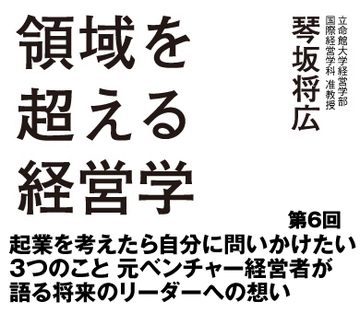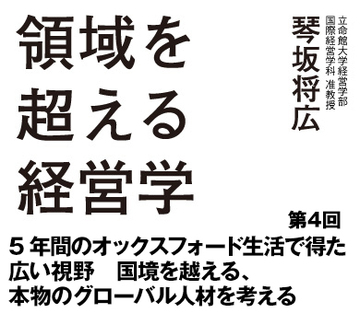研究の“お作法”を無視した博士号に価値はない
自分勝手に、自分流で仕事をしても、成果さえ出せば誰も文句を言わないという、経営者や経営コンサルタントという立場に8年もいた私が、この研究の“お作法”を理解するのは本当に大変でした。
とくに修士課程のときには、実務の世界とはかけ離れた学術理論の体系をゼロから学び直す必要があり、苦悩したのを覚えています。
それは、連綿と続く経営学の探究の系譜が、一昼夜では理解し得ない深淵で広大な体系をすでに築き上げていたからでした。しかも、そうした気の遠くなるような作業の末に「世界がどこまで理解しているのか」を知ることは、真の探究への出発点にしか過ぎないのです。
さらに、オックスフォード大学で修士課程から博士課程に内部から進級するには「Distinction」、直訳すれば「卓越」という意味の上位10%程度の成績を取ることが必須でした。つまり、修士の学生のほとんどは、たとえ希望したとしても博士には進学できません。
そのため、ただ学位を取得するだけではなく、良い成績で学位を取る必要があったことが、苦闘に追い打ちをかけていたのを思い出します。
そこには、計り知れない重圧がありました。ある程度は、そうした重圧のかかる環境に私は慣れていましたが、それに押しつぶされてしまいそうになる同僚も数多く見ることとなりました。もしかしたら、昨今話題に上がる方は、そうした重圧に押しつぶされてしまった1人なのかもしれません。
しかし、もちろんそれは言い訳にはなりません。
オックスフォード大学では、レポートや論文をコピー・アンド・ペーストするような行為は、専門家の目だけではなく、ソフトウェアも用いて監視されていました。厳しい指導と、管理監督があるからこそ、その下で研究に励む者も、研究倫理とお作法の重要性を知り、それを絶対的に守ろうとする意識が生まれるのでしょう。
「そうした健全な研究の体制ができているのか」
今は大学院生を指導する立場となった自分も、今回の悲しい出来事を知るに際して、深く自分自身に対して問いかけ直しているところです。そして、この問いかけこそが、今回の事件を契機として、すべての研究機関と研究者が今一度ゼロベースで問い直さなければならない課題なのだと思います。
そして、こうした苦行とも言える探究を永遠と繰り返す作業をくぐり抜けたからこそ、『領域を超える経営学』の58ページにも記したように、「学問としての経営学の知恵を愛することを学び、教える人」と意訳することもできる博士号(Doctor of Philosophy in Management Studies)という資格が価値を持ち、意味を持つものだと思います。
だからこそ、そうした取り組みをせずに、世界中の同僚を欺き、不正にこの資格を手に入れたと思われる人物がいるのであれば、それがどの分野であれ、多くの研究者は極めて強い嫌悪感を示すのです。
実際、私もくだんの問題に関しては、どうしても情状酌量の余地を見出すことができないままでいます。