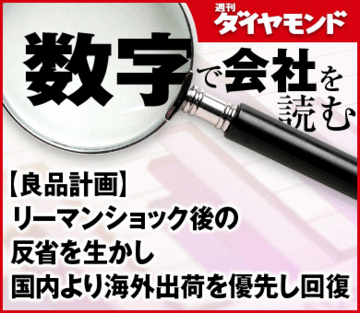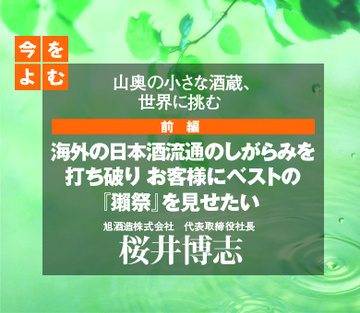桜井 私が目の当たりにしたのは、まさに急激な勢いで伸びておられた局面だったんですね。ほかのPBの追随を許さない圧倒的な存在感でした。
松井 確かに、ダイエーの「セービング」をはじめとして、流通大手各社がいっせいにPB商品を立ち上げた背景には、日本の消費市場が変わりつつあるという各社の共通認識があったと思います。
ところが当時、大手メーカーは自分たちのナショナル・ブランドを売ってもらったほうがいいわけですから、小売り側がPB商品の開発・供給をもちかけても消極的で、結局はそのほかの中小メーカーに製造してもらわざるを得ませんでした。結果として、どうしても“安かろう、悪かろう”という製品になって、お客様の支持を得られなかった。つまり、品質を犠牲に価格を3割安くしただけで、あの頃に登場したPB商品はひとつも生き残ることができませんでした。
試行錯誤の末、ビジネスモデルの
構築も進んだなかで、まさかの挫折
 旭酒造の桜井博志社長 撮影:住友一俊
旭酒造の桜井博志社長 撮影:住友一俊
桜井 そういった中で無印良品が躍進していったのは、明らかに同業他社のPB商品とは一線を画していたからですね。
松井 我々の商品コンセプトのひとつは「わけあって、安い」であり、具体的にイメージしたのは、「百貨店の商品に匹敵する品質を保ちつつ、その7掛けの値段で販売しよう」というものでした。素材や製造工程、パッケージなどを見直しながら合理的に価格を抑えて、けっして品質や機能をないがしろにしないように努めたのです。
そしてもうひとつ、我々は創業当初から「モノしか見えないモノを作ろう」という哲学を貫いてきました。たとえば、創業当時に売り出して今でも販売している「洗いざらしのシャツ」という商品があります。綿100%で色は無地、糊づけもされていなければアイロンさえもかかっていない。値札を取ってしまえば、パッと見た限りはどこの商品かわからなくもなります。しかし、非常に着心地がよかったり、吸湿性に優れている、というワイシャツの機能だけで勝負しているのです。
言い換えれば、品質のよさでしか我々は勝負できない、ということです。おそらく今日まで無印良品が生き残ってこられたのは、「わけあって、安い」というコンセプトと、「モノしか見えないモノを作ろう」という哲学があったからこそでしょう。そこが、他社とは決定的に違いました。堤清二というオーナーと、彼を取り巻く日本を代表するクリエーターたちが、肌感覚で持っていた先見性の賜だと思います。
桜井 なるほど。私たちが<獺祭>というブランドを作り上げていった際にも、中身である日本酒の味わいはもちろんのこと、ラベルにおいてもとにかくムダを排除してシンプルさを追求していきました。<獺祭>の文字は山口県出身の書家による直筆ですし、従来からの慣習に則ってラベル専門会社にデザインを依頼することも止めました。