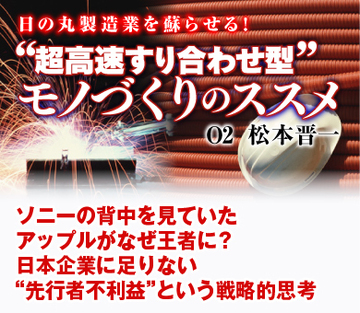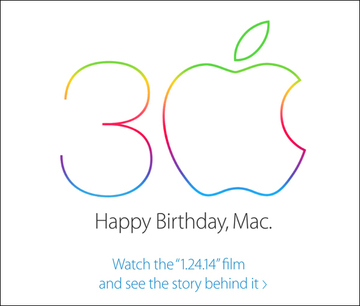ワールドカップが始まった。日本では深夜から朝の出勤時間に試合が行われ、日本代表に限らず世界中のチームが繰り広げる素晴らしい熱戦を見るには、少し難しい。
筆者の友人は、朝の試合を見るため、会社の会議室を開放して、近辺のサッカーを見たい人を集めた観戦「朝会」を行うという。出勤時間を大幅に遅らせることもなく、かつみんなで楽しめるという一石二鳥のアイディアには、たとえブルーのユニフォームの代わりにスーツを着ていたり、手元にビールと「シュラスコ」(ブラジル伝統の肉料理)がなかったとしても、楽しめるものだろう。
米国西海岸も、試合が行われるブラジルとは時差があり、ちょうど試合は昼間にあたる。米国ではそこまでサッカー人気が表立っていないようにも見えるが、そこは様々な国から人々が集まって構成されている国だ。街中のカフェやダイナーには大型テレビが設置され、ランチから夕方の時間帯にかけて、サッカーが放映されており、盛り上がりを見せている。
Apple TVを使って、
ネット経由で観戦中
米国のサッカー人気と同じように、こちらも表立っていないアップルのテレビへの取り組み。噂こそあるが、アップルの「テレビ」という存在はまだ登場しておらず、今後出てくるかどうかもわからない。手元にあるのは、黒くて小さなセットトップボックス「Apple TV」だけだ。しかし今回のワールドカップでは、このApple TVが大活躍している。
米国西海岸で暮らす我が家では、薄型テレビに接続したApple TVで観戦している。メニュー画面に用意されたスポーツ専門チャンネル「ESPN」のアプリを開き、ライブストリーミングやアーカイブ映像を楽しむことができるのだ。
ちなみに、このApple TV向けのアプリ内で映像を楽しむには、ケーブルテレビの契約が必要で、月額料金をESPNに支払って視聴したいと思っても、その方法は存在していない。このトリックは既にソチオリンピックの時に経験済みだった。