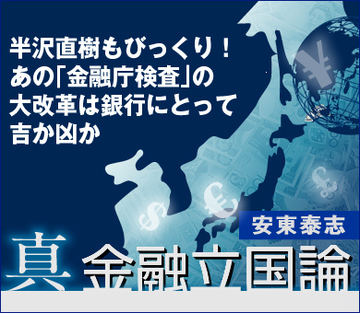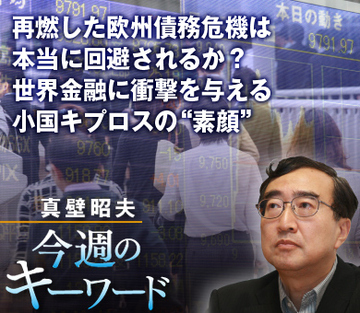銀行界の宿願だった、預金保険料の引き下げ議論が本格的に始まった。銀行としては、一見すると継続的なコストの圧縮につながる明るい話題なのだが、関係者にはもろ手を挙げて喜べない事情があった。
 「預金保険料の引き下げと金融改革は別議論」という銀行界の主張は、果たして届くか
「預金保険料の引き下げと金融改革は別議論」という銀行界の主張は、果たして届くかPhoto by Ryosuke Shimizu
預金保険料とは、銀行が入っている預金者を守るための保険の対価だ。仮に銀行が経営破綻しても、この預金保険料の積立金を取り崩すことで、預金者は1000万円までの預金が保護されるペイオフ制度が取られている。
1995年度まで銀行は預金額の0.012%を保険料として支払えばよかったが、90年代後半の金融危機で事情が一変。旧住宅金融専門会社(住専)の処理などで預金保険の積立金が96年度にはマイナスに転落。その後も北海道拓殖銀行など度重なる銀行の経営破綻で、積立金の流出は続いた。
そこで危機対応として、96年度から保険料率は0.084%へ7倍まで引き上げられた。現在もこの水準が続いており、業界全体で支払う預金保険料は年間6000億円に上る。この負担の軽減が、かねて銀行界の望みだったのだ。
その大きなチャンスが2010年度に訪れた。02年度に最大4兆円まで膨らんだ積立金のマイナスが、プラスへ転じるタイミングだったのだ。銀行界は「翌年度からの預金保険料引き下げを当局へ持ち掛けた」(地方銀行関係者)。
ところが、10年9月に日本振興銀行が経営破綻し、初となるペイオフが発動。再び積立金が流出したことで、その機運は一気にしぼんでしまった経緯がある。そのため、今回の動きは銀行界にとって「ようやく」という思いが強い。