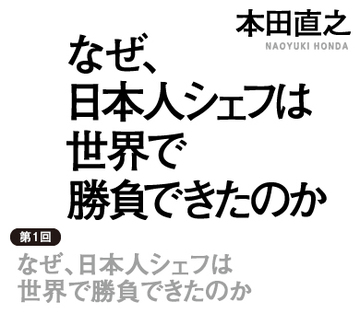世界を駆けるNOBUのファミリービジネス
――マツヒサ ジャパンはどのようにして生まれたのでしょうか?
ノブ NOBUは1994年にニューヨークでスタートし、その後ミラノ、ロンドンを経て、98年には青山で東京店がオープンしました。
NOBUでは、日本酒が竹の徳利で出てきます。NOBUで提供する日本酒は、新潟県佐渡の北雪酒造が作っている大吟醸だけです。今でこそ大吟醸というグレードは多くの人に知られていますが、当時のアメリカでは認知されるどころか、まだ存在すらしていませんでした。そこで僕は、一般的な徳利ではなく、竹の徳利でサービスしたいと思ったのです。そのために、京都で竹の徳利をつくり、ニューヨークやロサンゼルスへ輸出していたのです。
 竹の酒器
竹の酒器Nobu /InterContinental Hong Kong
そして、結果的にこの竹の徳利がマツヒサ ジャパンで一番最初につくったものになりました。そして日本から世界各地のNOBU店舗とやりとりする商社をつくる必要性から、2000年に会社として正式に発足しました。今では食器はもちろん、ドレッシングや稲庭うどん、お茶など、いろんなものを扱うようになりました。いわば日本と世界のノブをつなぐ窓口として機能しています。現在は15年目ですね。
――代表取締役であり、ノブさんの娘である松久純子さんは、どのようにしてマツヒサ ジャパンにジョインされたのでしょう?
純子 私は1998年に新卒でエアラインの会社に入社して、客室乗務員として働いていました。当時、東京にはまだNOBUの店舗はありませんでした。しかし青山に出店する時に、勤めていた会社を辞めてジョインすることにしました。父のお店で働いたことはなかったけれど、子どもの頃から料理人としての父の姿は見てきたし、何よりもレストランの雰囲気やお客さんと接する環境が私には居心地がよくて、好きなんです。それに客室乗務員と同じく、レストランもホスピタリティのお仕事です。
――お父さんと働くというのは、どんな感覚なのですか?
純子 まさしくファミリービジネスですよね。いっしょに働くことに対する不安はありませんでしたが、会社を運営することへの不安はとても大きかったですね。会社員として働いたことはあっても、伝票や請求書の書き方すら分からない状態でした。最初は本当にドタバタでしたが、途中から福本さんに入っていただけて、とても心強かったです。
福本 私たちはもともと大学の同級生なんです。同じサークルに所属していました。新卒ではそれぞれ別の会社に就職し、私はリクルートで広告営業をしていました。でも学生時代に一度訪れたロサンゼルスのMatsuhisaでの体験が鮮烈で、もともと「食」に関わる仕事がしたかったこともあり、2年で退職し、「NOBUのチームに入りたい」と強く思って転職しました。青山にあったNOBU東京がオープンして少し経った頃、最初はアルバイトから始めました。本当にお皿洗いからです。
ノブ 今は制度としてはないけどね、お皿洗いから修業するというのは。きっとあっちゃん(福本)がジョインした頃は、いわゆる「下積み」を重視する風潮が残っていたのだと思います。現場を知るという意味でトレーニングしていたんでしょうね。
福本 そうですね。でも、その時の経験は今に生きています。とくに現場の人とお話する時、厨房で働いていた頃のことをお話すると、一気に距離が縮まることがあるんです。
ノブ 制度として良いか悪いかは別として、僕の世代はまさに皿洗いやデリバリーで下積みをしていたものでした。そうしたポジションを知らないよりは知っていたほうがいい、とは思いますね。