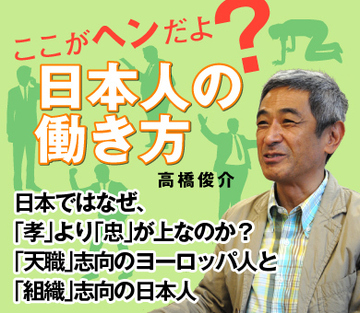早くから合議制の重要性を
認識していた徳川家康
いわゆる“西上作戦”の過程で行われた三方原の合戦で、信玄率いる武田軍は徳川家康軍を一気に撃破しました。野戦で無敵を誇った家康の唯一の敗戦は、この信玄との合戦でした。家康は自らの敗将姿を絵に描かせて残し、生涯の戒めとしたそうです。一方で信玄の戦略を徹底研究し、武田氏滅亡後は武田家の家臣たちを積極的に召し抱え、登用したのです。
天下人(征夷大将軍)になった家康は、徳川幕府の運営をすべて「役職ポストを複数制とする」というシステムに委ねました。そのため、幕府のトップマネジメントグループも「年寄」と呼びました。当時の村落共同体においては、名主や庄屋を年寄と称していましたが、それをそのまま採用したのです。年寄は3代将軍家光の時代になって「老中」に改められますが、人間の能力に限界を感じていた家康にとって、年寄制度とは合議制であり集団指導制であり、同時に「分権と責任体制」を示すものだったのです。
分権というのは家康の権限の一部を信頼できる幹部に委ねることである。しかしその責任の追及において家康は、
「分権された仕事について失敗したときの責任は、おれ(家康)とおなじものがある」
という考えを持っていた。しかも複数制にしたそれぞれのポストについて、
「月番制」
というのを導入した。たとえば町奉行にしても三人いれば一ヵ月交替で仕事をする。まわりからみて比較ができるからだ。
三人の岡崎奉行についても町の人間から見れば、
「今月の作左様はほんとうにきびしい。前月の高力様のほうがよかった。高力様はほんとうにホトケ様だ」
という具合だ。こういういわば世論はその後の人事異動の参考にもなる。したがって家康は一定の距離をおいて、組織を、そして部下を見ていたといっていい。そしてそれが德川幕府を約三百年(二百七十年)も持続させる大きな理由になる。德川幕府の長期政権維持の構造はこの当初からの、
「組織の分断支配」
にあったといっていいだろう。(58~59ページ)