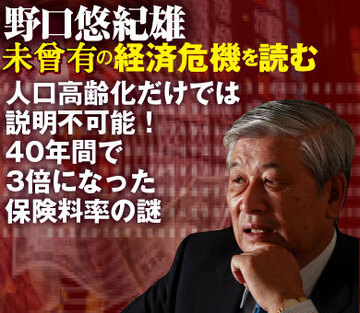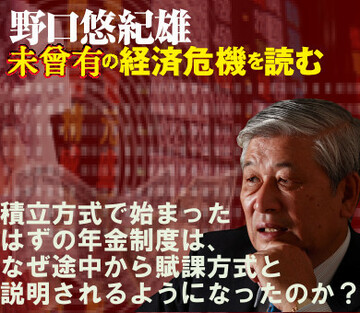前回で述べた総需要・総供給曲線の議論においては、財・サービスとして単一のものが考えられており、その中身が区別されていない。しかし、1980年代以降の日本経済を分析するには、最低限、「財」と「サービス」を区別する必要がある。この場合には、「財の価格」と「サービスの価格」を考えることになるわけだ。
そして、つぎのような単純化の仮定をおこう。すなわち、「財」は製造業によって生産され、貿易可能である。つまり、「財の生産者」としては、「輸入」(を通じた海外の生産者)も含まれるわけだ。他方、「サービス」は非製造業によって生産され、貿易可能でない。つまり、2セクターのモデルを考えるわけである。
そして、労働者は両部門を自由に移動できるものとする。製造業の賃金と非製造業の賃金があるが、労働が両部門間を自由に移動できるため、均衡において両者は等しくならなければならない。そこで、以下では、製造業の賃金と非製造業の賃金は同一であるものと考えよう。
生産は、(古典派モデルのように利潤最大化行動の結果として決まるのではなく)、「コスト・プラス方式」(または、マークアップ方式。生産費用に一定のマージンを加算して販売価格を決める方式)で行なわれるとする。すなわち、生産要素の投入は固定的であり、販売額とコストの差が利益になるとする。
新興国の工業化が
総供給曲線を下にシフトさせた
まず最初に、1960年代の高度成長期から80、90年代にかけて、いかなる変化が生じたかを分析しよう。
高度成長期においては、「財」部門が超過利潤を享受していた。こうなるのは、資本や経営資源が必ずしも両部門を自由には移動できないからだ。
ところが、新興国(最初は韓国、台湾など。後に中国)が工業化し、日本で生産している「財」と同じものを低賃金で生産できるようになった。生産物は、日本国内にも輸入される。これによって「財」の価格が低下する。また、新興国企業との競争のため、日本の製造業の賃金も低下する。その結果、製造業と非製造業で賃金格差が発生する。しかし、日本国内の労働市場は自由市場なので、製造業から労働力が流出し非製造業に流入し、賃金格差は消滅する。
この結果、つぎのことが生じる。
(A1)「財」の価格は最も大きく下落する(基本的には新興国製品と同じレベルまで)。賃金は下落するが、「財」価格ほどではない(労働力が製造業から流出するため)。「サービス」の価格は不変(サービスの生産量が増えるために下落する可能性もあるが、サービスに対する需要が弾力的であれば、あまり変化はない)、または上昇する(サービスへの需要が増えるため)。
(A2)賃金平準化の結果として労働者が製造業から非製造業に移動するため、製造業の就業者と生産量は(少なくとも相対的には)縮小する。他方で、非製造業の労働者と生産量は拡大する。