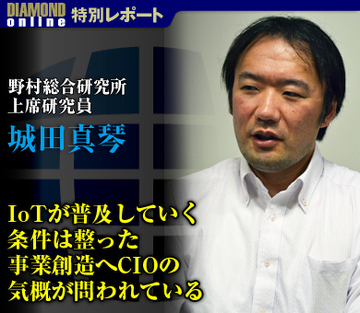ITの重要性は年を追うごとに高まっているが、それに比例してCIOも重用されるようになっているかというと、残念ながらそうではない。むしろ、多くの企業では、CIOの社内プレゼンスは低下傾向にあると考えるべきだ。
海外と日本では異なる
CIOの経歴
そもそも、日本の企業で、ITの経験に長けた専任のCIOを置いている会社は少ない。北米では、株主にCIOが説明をしなければならない場も多く、IT部門でキャリアを築いてきた人材が任命されている企業が多い。
 山野井聡(やまのい・さとし) ガートナー ジャパン リサーチ部門日本統括バイスプレジデント
山野井聡(やまのい・さとし) ガートナー ジャパン リサーチ部門日本統括バイスプレジデント
これに対して日本では、営業や財務、マーケティングなど、さまざまな部門を経験した後に、CIO的な立場を任され、しかも、ほかの部門との兼務というケースが非常に多い。
つまり、日本ではCIOという肩書きを持っていても、ITの専門家ではない人が多いということだ。実際、情報システムユーザー協会が過去に行った調査でも、日本のCIOでバックグラウンドがITという人は、約2割しかいなかった。
日本企業において、ITの専門家ではないCIOをサポートするのが、IT部門長だ。専務や常務クラスでITとほかのビジネス部門を兼務しているCIOが、IT部門長と上手に意思疎通を図れてバディを組めている会社は、むしろ良いケースと言える。
一方、CIOが自分の知識不足を補完するためにベンダーにすべてを任せるというケースは、まずうまくいかない。最悪の場合、その会社のITに精通しているのはベンダーのみということになりかねない。
CIOは、ITの可能性をCEOに訴えなければならない。クラウド、ビッグデータといった、はやりのキーワードを使ったところで、それをどれだけビジネスに生かせるのか、説得力のある言葉で説明できなければならない。