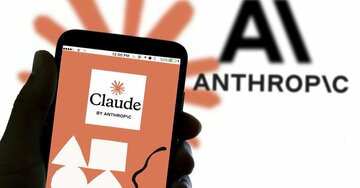今年3月17日、全米第5位の証券会社であるベアー・スターンズが事実上の破綻に追い込まれ、金融システム不安発生の懸念が台頭した。それは、先進のファイナンス技術で世界を席巻した「“金融帝国”=米国」の終焉が訪れたことを物語るイベントだった。それに伴い、米ドルは一時、1ドル=95円77銭まで売り込まれた。
その後、連邦準備理事会(FRB)の緊急利下げや、潤沢な資金供給によって金融市場が持ち直していることもあり、ドルには、ヘッジファンドなどの投機筋からの買い戻しが入った。また、ドル急落に備えて、「日米欧の中央銀行が、協調してドル買い支えの秘密合意を結んだ」との報道も飛び交った。このような経緯を経て、ドルは足許で狭いレンジを入ったり来たりする、いわゆるボックス相場の展開になっている。
これで、ドル下落のリスクは本当に去ったのか? 実は、そう考えるのは尚早である。投機筋の買い戻し=ショートカバーと、協調介入の思惑で戻っているドルの堅調な展開が、どれだけ続くかには疑問符がつく。
また、米国が抱えるサブプライム問題やそれに続く信用収縮、景気の後退などのリスク要因が解消されたわけではない。むしろ、多額の債務を抱えて身動きができなくなりつつある。ファニーメイ、フレディマックなどの住宅金融公社の懐は、住宅ローン延滞率の上昇で悪化している。
特に、今年の年末にかけて、「両者の資金繰りが厳しさを増す」との観測が現実味を帯びてくると、米国の金融市場が、再び大きく下落することも考えられる。そのとき、基軸通貨であるドルが、どれだけ売り圧力に耐えることができるか、それが試される局面が訪れる可能性は高いと見る。
“金融帝国”アメリカの黄金期は終焉か?
ドルの「上値」は限られる可能性も
今年3月、欧米、特に米国の市場関係者は、一様に不安な表情を浮かべていた。昨年8月まで堅調な収益状況を誇っていた、米国の投資銀行大手のベアー・スターンズが、事実上、破綻した。それは、1990年代中盤から続いてきた、「金融帝国=米国の黄金期」が終焉を迎えたことを意味するからである。
米国では人件費水準が高いため、知識集約度の低い“モノ”を作って金を稼ぐことが難しい。それを自覚した米国は、先進の技術や金融工学の手法を駆使して、「ファイナンス=金融」で儲ける術を編み出した。
その後、米国におけるファイナンス技術には一段と磨きがかかり、世界の投資資金の多くを集めるまでに至った。集められた多額の資金に借入金を加えてレバレッジ(てこ)をかけ、手元資金の数倍の資金を運用する運用方式へと進化して行った。さらに、運用成績を引き上げることを狙って、オプションや先物など金融派生商品(デリバティブ)を使い、一層、投資規模を拡大して行ったのだ。