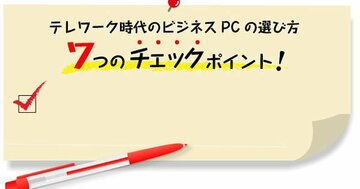ダイヤモンド・オンラインplus
「総合物流の王者」が大きな変貌を遂げつつある。人口減少や脱炭素など物流を取り巻く社会環境が大きく変わりつつある中で、社会に受容される持続可能なサプライチェーンとは何なのか。日本通運は、DXを切り口に、個別最適を乗り越えたオープン型の「デジタルプラットフォーム」の構築に向けて戦略のかじを切った。

不動産を中心とした生活総合産業を展開するタウングループ。オンライン接客なども進む中、賃貸物件仲介事業を担うタウンハウジングでは、一都三県で直営100店舗体制を確立。2025年までに全国で300店舗出店を目指す。一方で、賃貸物件の管理事業を主体とするアレップスでは「PM(プロパティマネジメント)事業部」や「資産活用部」を充実。グループの総合力を生かし、多面的にオーナー収益の最大化を図る。

エス・エー・エスは長年、勤怠管理システム「勤労の獅子(きんろうのしし)」を提供。導入企業は勤怠管理業務の削減や、活動時間の見える化による生産性向上など、さまざまな導入効果を上げている。また同社はコロナ禍以前から、テレワークや時差通勤を積極的に導入し、いち早く働き方改革を実現、その知見も含めて商品を展開してきた。働き方の多様化が加速する中で、「勤労の獅子」はどのような成果を上げられるのか? 同社の青山秀一社長と担当者に訊いた。

「公共トラックターミナル」としての機能提供により、日本の物流を支えてきた日本自動車ターミナル(JMT)。経済活動におけるEC(電子商取引)化が急速に進む中で、立地優位性をはじめとするポテンシャルが開花。トラック事業者にとどまらない顧客層の開拓が進んでいる。

2021年2月10日、USEN-NEXT HOLDINGSは「社長発掘プログラム " CEO's GATE "」(以下、社長発掘プログラム)を開始した。同社では「100人の社長、100の事業会社を創造し、1兆円企業グループを目指す」という中長期ビジョンを掲げている。このビジョンに合わせ、USEN-NEXT GROUPで社長になりたいという人を100人募集するというプログラムだ。

東日本旅客鉄道(JR東日本)とKDDIは、「交通」と「通信」という二つの社会インフラが融合した「分散型まちづくり」の共同事業化に向けて動きだした。その狙いと、両社がプロジェクトに込める思いについて、JR東日本の表輝幸・執行役員事業創造本部副本部長と、KDDIの藤井彰人・執行役員ソリューション事業本部サービス企画開発本部長に聞いた。

首都圏・北関東とのアクセスが良好で、国内有数の広大な工業団地を持ち、「本社機能移転強化促進補助」など、独自の優遇制度も手厚く用意している茨城県。過去10年間の企業立地面積と県外企業立地件数は、全国トップ※1だ。県の積極的な誘致活動を背景に、本社や研究所を移転する企業が増えており、新型コロナウイルス対策による“脱東京”の流れも、転入者の増加を後押ししている。多くの企業を引き付ける、茨城県のポテンシャルと魅力を探った。

ISO認証などの審査・登録を行う一般社団法人日本能率協会は、認証取得を希望する企業への営業アプローチを強化するためウェブマーケティングを開始。MA(マーケティングオートメーション)で作成した見込み客リストをもとに、BPO(業務の外部委託)で電話によるアプローチを掛けるという手法で、コロナ禍においてもウェブ経由での引き合いを増やすことができた。

顧客や従業員の体験(エクスペリエンス)データと業務(オペレーション)データをバリューチェーン全体でつなぎ、顧客や従業員に寄り添った真のデータ経営を実現するにはどうすればいいのか。「デジタル時代の『エクスペリエンス経営』の実践」をテーマに開催されたオンラインセミナーの内容を紹介する。

保管したモノの出し入れをICタグにより自動で記録管理する「CABIMATCH(キャビマッチ)」。貸し出し・返却の記録漏れを防ぎ、現場に張り付いていた貸し出し業務担当者の負担を軽減、このご時世テレワーク体制の強い味方にもなる。

コロナ禍により在宅勤務が日常化し、社外でデータを取り扱う機会が増える中、会社の機密情報をいかにして保護するかが大きな課題となっている。堅牢なセキュリティ対策が難しいテレワーク端末でも、ユーザーの業務効率を低下させることなく情報漏えいリスクを抑えたい ―― そんなニーズに応えるのが、ファイル暗号化ソリューション「DataClasys」だ。

TACT(タクト)が提供するのは、新しいコミュニケーションの形、AIによるコールセンター業務だ。音声認識と音声合成の技術を使ったシステムで、クライアントのニーズに合わせてAIプログラムを構築、問い合わせの完了率を向上させる。コールセンターの運営で培われたノウハウを基に、緻密なチューニングで音声認識率や回答の精度を上げるのが同社の強み。すでに豊富な導入実績を誇っている。

新型コロナウイルスの感染拡大によって、企業のオフィス戦略は大きく変わった。テレワークの定着とともに、スペースが余った自前のオフィスを縮小する一方、契約形態がフレキシブルな空間をサテライトオフィスとして活用する動きが広がっているのだ。“ニューノーマル”を生き抜くため、企業が取り組むオフィス新戦略の最前線に迫る。

2020年12月15日、ダイヤモンド・オンラインとKDDIはWebセミナー「激動の2020年がヒントになる ~いまこそ”真のDX加速”~」を開催した。新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的流行は、私たちの働き方をわずかな期間で大きく変えた。デジタル技術を活用した「テレワーク」という働き方が当たり前になり、どこにいてもチームのメンバーとコミュニケーションを取りながら働くことが当たり前になった。COVID-19が収束した後、私たちの働き方はどうなるのか、企業はどうすれば成長していけるのか。東京大学名誉教授、学習院大学国際社会科学部教授の伊藤元重氏が語った。

働き方改革の進展とコロナ禍によって、業務のデジタル化を進める企業が増えている。ところが平成30年度に総務省が行った調査によると、デジタル化によってマイナスの影響を感じている人も少なくないことが分かっている。生産性を向上させるために導入したシステムが、逆に現場では重荷になってしまっているのだ。なぜそのようなことが起きるのか。解決策はないのだろうか。

裁判手続のIT化が進められている中、多くの法律事務所ではデジタル化が遅れている。一般企業と同様、法律事務所でもデジタル変革が求められている。世界中で利用されているSalesforceをベースに、法律事務所の業務に合わせて開発されたLEALAであれば、簡単に導入可能だ。業務効率化や経営の安定化を図るためにも、LEALAを利用して真のデジタル化を目指すことが重要である。

顧客が求める砂を調達して提供するルナサンド。強固なロジスティクスを背景に、青森の採砂場から高品質の「ルナサンド」を全国に配送している。近年は物流事業を拡大し、福島の震災復興の現場でも活躍。衛生管理事業も開始し、サスティナブルな未来を見据えた事業にも取り組んでいる。

環境への責任と持続可能性をビジネスの重要な鍵として位置付け、信頼性の高い航空会社として知られるカタール航空。エアバスA350をはじめとする燃費効率のよい双発機への戦略的な投資により、危機的な状況下でも継続的な運航を可能にした。

「ユースエール認定企業」という言葉を聞いたことがあるだろうか?若者の採用や育成に積極的で、雇用管理の状況も優良な企業に対して、厚生労働大臣が認定した企業のことだ。中小企業にとっては、求職者にPRできるよい機会となり、求職者にとっては、隠れた優良企業を探すよい指標となるものだ。実際に認定された企業を訪ねて、人事担当者とそこで働く若手社員に職場の様子を聞いてみた。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、人々の働き方が大きく変化した昨年。PCを使ったテレワークが当たり前になる中で、企業はどんなところに注目してPCの購入を検討すべきか? 具体的なチェックポイントやおすすめPCについて、PCメーカーのマウスコンピューターに取材した。