ダイヤモンド・オンラインplus

部品や工具、検査機器など、あまり目立たない領域ではあっても、世界の産業の発展になくてはならない製品やサービスを提供している日本の中堅中小企業は多い。そうした企業は、今後の成長についても堅調な数字を予測している。その成功要因と継続的な成長のカギを探る。

変化が速く、不安定で、破壊的なプレーヤーが既存のビジネスを脅かす現代は、ビジネスのスピード(ビジネスアジリティー)が重要となる。伝統的な企業も自らの力で自社を変革させなくては生き残れない。変革を成し遂げるためには何が必要か? 欧米先進企業のDX最前線をよく知り、ビジネスフレームワークSAFeを提供するスケールド・アジャイルのクリス・ジェームス氏と、長年、国内外の企業へのテクノロジー導入を支援し、SAFe認定パートナーの一社となったTDCソフトの上條英樹氏が語り合った。
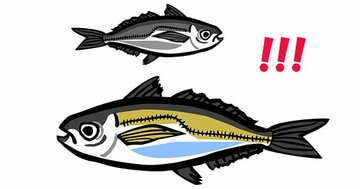
社員の健康を守る「健康経営」に取り組む企業が増えてきたが、社員が利用するPCなどの端末の健康管理はどうだろうか。セキュリティー対策が脆弱な端末はサイバー攻撃の格好のターゲットになる。タニウムは企業のあらゆる端末をリアルタイムに可視化するサイバーハイジーン(衛生管理)のプラットフォームを提供。経営リスクとなるサイバー攻撃から企業を守るソリューションとして注目されている。

「モノ」重視から「コト」重視へと時代が変化する中、知的財産という見えない資産をコアコンピタンス(競争力の源泉)とする企業が増えている。儲かるビジネスを構築するために、知的財産はどのようにマネタイズされるべきなのか?知的財産戦略コンサルティングで多くの実績を持つ、正林国際特許商標事務所の正林真之所長に聞いた。

企業の働き方改革の推進でテレワーカーの増加が見込まれる中、野村不動産が2019年10月から始めたサービスがサテライト型シェアオフィス「H1T(エイチワンティー/Human First Time)」だ。業界最安水準で使いやすい料金設定とハイグレードなデザインが大きな魅力。都内主要エリアや郊外ターミナル駅に展開するオフィスネットワークも付加価値を高めている。

ジューテックホールディングス(=ジューテックG)は創業100周年も近い老舗企業。住宅産業が新築需要の減少で曲がり角を迎える中、業務の透明化を推進して業界の革新に挑んでいる。メイン事業の資材販売のみならず、住宅産業に関わるさまざまな分野に進出。上場も果たすなど、成長を続けている。

建物に明かりをともす電気設備工事の会社として"夜景を変える"をスローガンにしている。業界では珍しく、女子・文系学生を積極採用。独自の教育・研修システムで施工管理を行う現場代理人を育てる。安定した受注力を誇り、働き方改革にも力を入れている。

PCは一括購入するのが当たり前── そう思い込んではいないだろうか。確かにこれまではそうだったかもしれない。しかし、クラウド化の波とともに状況が変わった。コストを抑えながら、社員一人一人の働き方に合ったPCを支給し、しかも面倒な設定不要ですぐに使えるサービスが登場した。それがDaaS(Device as a Subscription)である。

東京都墨田区の錦糸町に日本における「延長保証」のスタンダードを築き上げた草分け的企業がある。テックマークジャパン株式会社は、1930年頃に米国で始まったワランティサービスの種を、日本の市場に合うようカスタマイズし芽吹かせた。現在、延長保証は家電量販店だけでなく、自動車や住宅設備機器、AIスピーカーなど、その活用の幅はとどまることを知らない。日本国内での普及の契機となった「マーケティング手法」への発想転換の立役者で、延長保証の活用法と可能性をまとめた日本初の書籍の著者でもある同社代表に話を聞いた。

MBO(経営陣が参画する企業買収)を経て、2016年に東証一部に再上場した後、2ケタ成長を続けるソラストが、さらにダイナミックな変革を目指している。それは、「サービス業のデジタルカンパニー」への進化だ。いかにして、その変革を達成するのか。同社取締役専務執行役員の川西正晃氏が語った。

創業14年目を迎えるデュアルタップ。資産運用型マンション「XEBEC(ジーベック)」の企画・販売が主力事業だが、海外不動産事業も積極的に展開。マレーシアの経済特区で政府系企業と提携して進出企業の支援を開始するなど、総合不動産業としてグローバルに成長を続けている。

「環境を創る 未来を創る」を企業理念に、害虫駆除・防除に対して予防・早期発見というユニークなアプローチで取り組む「8thCAL(エシカル)」。同社の岡部美楠子社長と昆虫学者の丸山宗利・九州大学准教授が、生き物が共存・共生できる社会の可能性について語り合った。
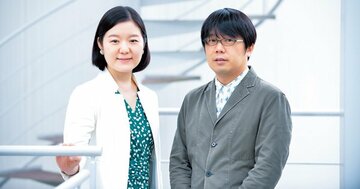
日本の米作りが変わろうとしている。ICTの力を導入して安全で安心な作業環境を創造し、大規模栽培の効率化や栽培管理の適正化を確保する。関東の有数の穀倉地帯である茨城県南部に挑戦を訪ねた。

武蔵コーポレーションの認定収益物件「ReBreath(リブレス)」は、1棟単位で買い取った中古の賃貸マンションを、一定期間自社で保有しながら改修して再生したものだ。建物保証に満室保証や滞納保証まで付けてオーナーに販売する。

大切な土地を有効に活かしながら次世代に継承したい──。そんな思いをかなえるのが、積水ハウスの3・4階建て併用住宅「ベレオ・プラス」だ。土地のポテンシャルを最大限に引き出すフレキシブルな設計提案力など、その魅力を紹介しよう。

アドビがビジネスモデルをクラウド化・サブスクリプション化する大変革を実行したことに伴い、PDFを作成・編集するためのソフトウエア「Acrobat(アクロバット)」もクラウド型に進化した。組織の生産性やユーザーエクスペリエンス向上のためのソリューションとして、グローバルで導入が進んでいる。

コスト削減を目的に、総合オフィスソフトを「WPS Office」に置き換える企業が増えている。定番のオフィスソフトに比べて、ライセンス費用の削減が期待できるためだ。作成したファイルの互換性の高さはもちろん、使い慣れたUI(ユーザーインターフェース)や独自機能も用意されており、コスト削減とともに業務の効率化も図れそうだ。

野村不動産は今年11月、従業員10名未満の企業に向けて、新ブランドであるサービス付小規模オフィス「H1O(エイチ・ワン・オー)」の提供を開始した。オフィスのコンセプトは、働く人の気持ちに作用し、「個」のポテンシャル(生産性や付加価値を生む力)を最大化する“ヒューマン・ファースト”。「H1O」誕生の経緯とオフィスの特長、今後の供給計画などについて、同事業を推進する宇木素実執行役員に聞いた。

「注文住宅なのに思い通りの家がつくれない」「人手が足りないが外部人材に仕事を任せるのは不安」。一般の人はもちろん、業界関係者にとってもジレンマだらけの建設業界に、そのジレンマを打ち破るスタートアップが現れた。名古屋のスタートップ、スタジオアンビルトだ。建築家やデザイナーなど、プロのスキルをオンラインで“直販”し、ブラックボックス化した業界に新風を吹き込む。
