記事一覧
「就活病」の学生のメンタルを、先輩社員や採用担当者がフォローする方法
企業・団体における、24卒生(2024年3月の学校卒業者)の採用活動が佳境を迎えている。新型コロナウイルス感染症は、「2類相当」から「5類」に移行し、就職活動を大きく変えたウィズコロナの時代も新たなステージに入った。インターンシップ改革、オンライン面接の平常化、早期化する内定出し……就職戦線が変化するなか、Z世代の就活生たちはどのようなメンタルで就活を行っているのだろう。そして、人材獲得に腐心する採用担当者は、どのように彼ら彼女らに向き合うべきだろう。書籍『内定メンタル』の著者であり、地方学生向け就活サービス「ジョーカツ」でのセミナーの講師などで全国の就活生とつながりを持つ光城悠人さんに話を聞いた。

シニア社員の“パラレルキャリア”が個人と組織にとって大切なのはなぜか?
ここ数年、「キャリア自律(Career Self-reliance)」という言葉が目立つようになった。コロナ禍や慢性的な労働力不足によって体力をなくした企業は先行きが不透明となり、雇用される側は、仕事のスキルを上げて、エンプロイアビリティ(雇用される能力)を高めなければならない。昨年2022年10月刊行の書籍『個人と組織の未来を創るパラレルキャリア ~「弱い紐帯の強み」に着目して~』の著者・中井弘晃先生(明海大学 総合教育センター/専任講師)は、「キャリア自律を促進する方法のひとつが、人との交流を伴う“学びのパラレルキャリア”の実践」だと論じる。個人と組織の双方にメリットのある「パラレルキャリア」とは何か? 中井先生が教壇に立つ明海大学(千葉県浦安市)のキャンパスで話を聞いた。

“コミュニケーションと相互理解の壁”を乗り越えて、組織が発展するために
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第9回をお届けする。

LINEの「HRBP(HRビジネスパートナー)」が事業成長のために行っていること
人・情報・サービスをつなぐコミュニケーションアプリ「LINE」。日本国内の月間アクティブユーザー数は約9500万人におよび、生活を支えるプラットフォームとして欠かせない存在になっている。そして、そのアプリを運営・開発するLINE株式会社においては、サービスの継続&成長を人事・組織面から戦略的に支える「HRBP(HRビジネスパートナー)」が欠かせない存在になっている。HRの水先案内人となる「HRBP」の役割とは? 各事業部のマネージャーに伴走する方法とは? HRBPチームをマネジメントする、LINE株式会社HR Business Partner室の大野道子さんと小向洋誌さんに話を聞いた。

企業の成長を実現していく“ワケあり人材”採用&登用のススメ
働き方改革やダイバーシティ&インクルージョンの推進で、企業にはさまざまな人が在籍し、それぞれのスタイルで働くようになった。しかし、まだ、就労時間や場所に何らかの制約があり、希望する職に就けない人も多いのではないか。「就労時間や場所に制約あり」――そんな“ワケあり人材”に、企業はどう向き合い、ともに、どのように成長していけばよいのか。経営コンサルティング会社での勤務を経て、現在は成熟企業の事業創造支援などを行う筆者(東加菜さん/michinaru株式会社 マーケティング・広報担当)が論考する。
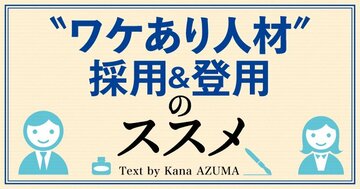
人的資本、オンライン、内製化……「研修」はこれからどうあるべきか?
コロナ禍によって、企業における「研修」はオンラインの受講が一般化し、研修動画のオンデマンド視聴なども増えている。また、コロナ禍前から研修の「内製化」が進む一方で、人的資本経営やダイバーシティ&インクルージョンの推進によって、研修の内容も多岐にわたっている。ウィズコロナ、アフターコロナの時代で、企業内の研修はどうなっていくのか。部下育成研修などで講師を務めるほか、さまざまな経営者や人事部と接点を持つ永田正樹さんに、「研修」の現況とこれからの意義を「HRオンライン」で語ってもらった。

学生と企業の“長期的なつながり”となる「リレーション採用」の価値
今年も、多くの企業・団体で新卒採用の広報活動がスタートした。会社説明会の開催やエントリーシート(ES)の受け付けなど、学生との接触が進み、内々定も出し始めている。コロナ禍が落ち着くなか、企業・団体の採用意欲は高まり、今後、“売り手市場”は続いていくだろう。そうした状況下、中小企業のみならず、大手企業でも、“自社の求める人材”をどう確保するかが重要になっていく。“自社の求める人材”の確保に向けて、「リレーション採用」という新しい手法を提唱し、サービスを提供している株式会社インタツアー 代表取締役社長 作馬誠大さんに、学生とのミスマッチを防ぎ、質の高い採用活動を展開するポイントを聞いた。

研修の内製化に欠かせない『研修開発ラボ』とはいったい何か?
昨今、人材育成における研修は、「内製化」が進みつつある。研修会社がつくった研修を実施するのではなく、それぞれの企業・団体が、自社の持つ課題や施策に合わせて、オリジナルの研修をつくるというものだ。しかし、多くの人事(研修)担当者にとって、研修を企画し、開発することはハードルが高く、どこからどう始めればよいか分からないという声が多い。そんな悩みを解決する講座『研修開発ラボ』(立教大学経営学部・中原淳教授監修)――その、およそ5カ月にわたる模様を「HRオンライン」がレポートする。
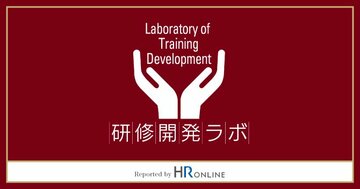
“出戻り社員”が、会社と本人を幸せにする理由と、お互いが成功する方法
「人的資本経営」のカギを握る「アルムナイ」。企業が自社の退職者である「アルムナイ」とどのような関係を築いていくかは、人材の流動性がますます高まるこれからの時代において重要だ。アルムナイ専用のクラウドシステムを提供するなど、アルムナイに関する専門家である鈴木仁志さん(株式会社ハッカズーク代表取締役CEO兼アルムナイ研究所研究員)が、企業の「辞められ方」、従業員の「辞め方」を語る連載「アルムナイを考える」――その第4回をお届けする。
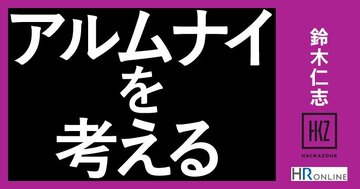
ダイバーシティ&インクルージョンに必要な「エンパワメント」と「当事者性」
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第8回をお届けする。

パワハラをなくすために、今日からできる、上司と部下の向き合い方
「労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」の全面施行から約1年――コロナ禍でリアル対面のコミュニケーション機会が減ったこともあり、部下の指導に腐心する上司・管理職が多くなっている。指導のひとつの手段としては「叱責」もあるが、ビジネス心理学を専門とする水口政人教授(龍谷大学・文学部)は、パワーハラスメントのない職場づくりと良好な人間関係のために、安易な叱責は不要と説く。「HRオンライン」が、龍谷大学(京都市)のキャンパスで水口先生に話を聞いた。

経験学習における“リフレクション”は、どうすれば効果的に行えるか?
人材育成の手法のひとつである「経験学習」において、「具体的経験」に続くステップが「内省的観察」だ。「リフレクション」と呼ばれる、その行動は、研究者によって多くの捉え方があり、実践することがなかなか難しい。日々働く中で、効果的なリフレクションを実現するために、個人はいったいどうすればよいのか? 人事担当者向けのセミナーなどに多数登壇している永田正樹さんが、経験学習における“リフレクション”について解説する。
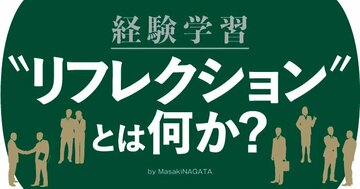
「育休」から「育業」へ――いま、企業経営者や人事担当者に必要な視点とは?
少子化や女性活躍、企業の採用力向上など、さまざまな課題解決に欠かせない施策として期待されているのが、企業・団体で働く人の育児休業(育休)取得率のアップだ。「育児・介護休業法」の改正など、政府はさまざまな推進を続けながら、女性従業員とともに男性の取得率アップ(2025年までに30%達成)を目指している。そうしたなか、昨年2022年に、東京都が「育休」に変わる「育業」という言葉を公表して世間の注目を集めている。施策の最前線にいる、東京都子供政策連携室の中島知郎さん(子供政策連携推進部・子供政策推進担当課長)にお話を聞いた。

30代40代のミドル社員が身につけたい“両利きのキャリア”とは何か?
昨今、「両利きの経営」というコトバがビジネスシーンで目立っている。既存事業の「深化」と新規事業に向けた「探索」を両立させるという経営姿勢のことだ。「キャリア自律」が重要視される時代において、「深化」&「探索」行動は、組織のみならず、個人にとっても大切なものだろう。経営コンサルティング会社での勤務を経て、現在は成熟企業の事業創造支援などを行う筆者(東加菜さん/michinaru株式会社 マーケティング・広報担当)が、「両利きのキャリア」について論考する。
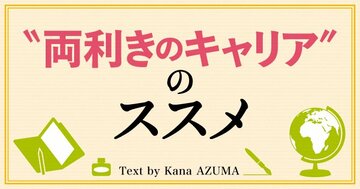
25卒採用“インターンシップ改革”で、人事担当者が知っておきたいこと
2022年4月、国公私立大学と経団連(一般社団法人 日本経済団体連合会)の代表者によって構成される「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」が、報告書『産学協働による自律的なキャリア形成の推進』を公表した。これをきっかけに、新卒採用における企業のインターンシップのあり方が大きく見直されることになった。注目されるのは、25卒生(2025年3月卒業予定の学部生・院生)から従来のインターンシップが4類型に整理され、「インターンシップ」の名称を使うには5日間以上のプログラムとフィードバックなどが必要になる場合もあることだ。今回の“インターンシップ改革”の内容と影響、そして、企業の経営層と人事担当者は、どのように、その準備と対応を進めればよいのか――ダイヤモンド・ヒューマンリソースHD首都圏営業局局長の福重敦士さんに話を聞いた。

JTの内定者懇親会が教えてくれる、内定者同士の“つながり”の大切さ
あと2カ月ほどで“23卒生”が社会に飛び立つ。その23卒生の採用活動において、「内定者フォローや辞退防止のために実施したこと」を企業に聞いたところ、従業員501名以上の大規模企業も500名以下の中小規模企業も、回答の1位が「内定者懇親会」だった。コロナ禍で、内定者向けのイベントや内定式が対面では行いづらくなっている昨今、「内定者懇親会」はどのような内容で、どう開催されているのか――内定者同士に加え、人事担当者と内定者の関係を構築することで参加学生の入社意欲を高めている日本たばこ産業株式会社の三島紀子さん(日本マーケットCountry P&C Recruitment)に話を聞いた。
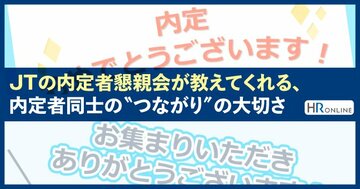
孤独と向き合って自分を知った大学生と、これからの社会のありかた
学生をはじめとした若者たち(Z世代)はダイバーシティ&インクルージョンの意識が強くなっていると言われている。一方、先行き不透明な社会への不安感を持つ学生も多い。企業・団体はダイバーシティ&インクルージョンを理解したうえで、そうした若年層をどのように受け入れていくべきなのだろう。神戸大学で教鞭を執る津田英二教授が、学生たちのリアルな声を拾い上げ、社会の在り方を考える“キャンパス・インクルージョン”――その連載第6回をお届けする。

従業員の“キャリア展望”を高めるために、会社は何をすれば良いか
「従業員にキャリアの展望がない」という声をさまざまな会社で耳にする。「役職につきたくない」「出世したくない」といった若手従業員の意向も気になるところだろう。どうしたら、従業員が社内でのキャリアの目標を描いていくことができるのだろうか。今回は、株式会社ビジネスリサーチラボの代表で、『現場でよくある課題への処方箋 人と組織の行動科学』(すばる舎)の著者である伊達洋駆さんに、従業員が仕事への意欲とともに“キャリア展望”を高めていくための人事のアプローチや注意点について聞いた。

コロナ禍の就活生が、“アナログ手帳”の制作で得たコミュニケーション
新型コロナ感染症拡大による1回目の緊急事態宣言が発令された2020年4月――その春に大学に入学した学生たち(現在、主に3年生)が、現在、就職活動(就活)を行っている。デジタルネイティブな彼・彼女たちZ世代のスケジュール管理はスマートフォンで行うのが当り前だ。しかし、就活においては「手帳」が重宝される傾向もあり、“大学生による、就職活動生のための手帳”である「シン・就活手帳」が今年度も完成した。サポート役を担った著者が、学生たちと歩んだ、その制作過程を振り返る。
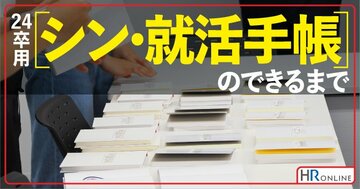
メンタルダウンした管理職に、企業はどう向き合い、本人はどうすればよいか
50代の「働かないおじさん」問題が取りざたされているなか、30代・40代の「働く管理職」のメンタルダウンが増えている。待遇に見合わない“責任の重さ”や同僚・若手社員の離職による“過重労働”など、その要因はさまざまだ。企業経営者や人事担当者は中間管理職のメンタルをどうケアし、心の病(やまい)にいかに対応していけばよいか――メンタルダウンの当事者であり、自らの経験から「心の病気に向き合うメソッド」を提唱する人事コンサルタントの佐々木貴則さん(ハートフルデイズ 代表)に話を聞いた。

