米国(18) サブカテゴリ
第5回
新聞社から不動産売買や求人・求職などの3行広告を根こそぎ奪いつつあるクレッグズ・リストというネット企業をご存知だろうか。米国ではすでに紙媒体から“天敵”扱いされている。

第16回
グローバリゼーションをスシという切り口から分析した『The SUSHI ECONOMY』が米国でベストセラーとなっている。著者のアメリカ人ジャーナリストに、スシ経済の醍醐味を聞いた

第36回
米政府が、住宅市場の低迷で資金繰りが悪化している2公社(ファニーメイとフレディマック)の緊急救済措置を発表した。だが、資本注入は当面難しく、危機が去ったとは言い難い。
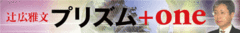
第6回
町村官房長官の談話として「オバマ候補はマケイン候補に勝てない。それは彼が黒人だからだ」との報道が飛び込んできた。その後すぐに否定したようだが、これが日本政府の発言として世界に流されてしまった。

第33回
過去のアメリカ大統領選について、選挙以前の時点でのニューヨーク・タイムズ記事数の推移はどうだったのか?ここでも、選挙の結果を正しく、しかも「大接戦であった」ことまで予測していたのだ。
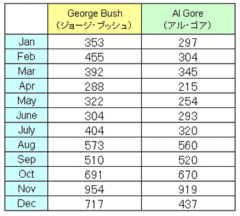
第35回
洞爺湖サミットが9日閉幕し、G8は「第3次オイルショック」「食糧危機」「米プライム・ローン危機」「新興国の成長神話の崩壊」と、連鎖的に増幅する世界的危機に対してまったく無力であることを露呈した。
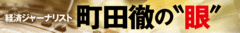
第36回
北海道洞爺湖サミットが閉幕した。なんといっても、環境問題における「長期目標」の達成ほど、福田首相を喜ばせたことはないだろう。だが、これは果たして本当に「合意」なのだろうか?
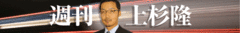
第35回
輸出入を制限する経済制裁は、すり抜ける方法はいくらでもある。しかし、金融機関がいっせいに同調すれば、金流は遮断される。北朝鮮が干上がってしまう効果的な制裁は、金融制裁である。
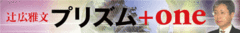
第36回
今年6月の米国の自動車販売台数は、ガソリン価格高騰などにより前年同月より大幅に減少した。現在、世界最高峰にあるわが国メーカーも安閑としていられない。
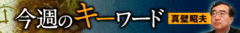
第1回
米国が北朝鮮の「テロ支援国家指定解除」の手続きに入ることを決めた。これによって日本人拉致問題の解決が遠のくと懸念されている。しかし私はむしろ「拉致問題」は解決に向けて進展する可能性があると思う。

第13回
原油相場のあまりの高騰ぶりに、近い将来の“暴落”を予測する声が高まっている。しかし、国際エネルギー機関(IEA)の幹部は、原油安の時代への回帰はもはやないと断言する。

第32回
前回、ニューヨーク・タイムズの検索がアカデミー賞の結果を事前に予測していたように見えると述べた。政治的な動きについても同じような予測がありうるのか、大統領選を例にとって見てみよう。
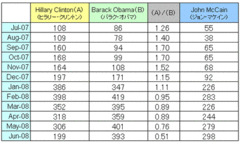
自らの技術と事業を守るために存在してきた特許が、研究開発の成果を移転するためのマネーに変貌しつつある――。好評シリーズの英語バージョンをお届けする。
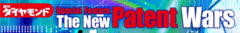
第35回
したたかな戦略でもって、各国の報道機関のみならず、全世界の人々を騙してしまった北朝鮮。今回の「爆破ショー」は、金正日政権のメディア戦略の勝利以外の何ものでもない。
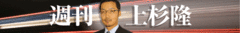
第31回
今回はニューヨーク・タイムズの記事数から、アメリカの映画賞である「アカデミー賞効果」について考えてみる。やはりアカデミー賞は、作品の評判を増幅させる役割を持っているのだろうか。
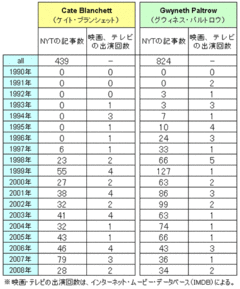
第9回
米国中央銀行・政府は、インフレ抑制のためにドル防衛姿勢を打ち出した。景気低迷の米国にはインフレ対策としての利上げの余地がほとんどないなか、なぜドル防衛か。
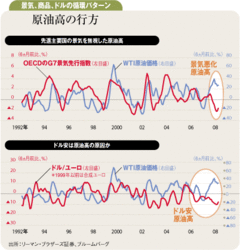
第3部
今国会での米国の特許法改正は絶望的となった。訴訟コストの拡大など課題は山積しており、各国との制度的調和も求められている。特許制度改革は焦眉の急である。

第30回
これまでの分析をさらに進めて、販売戦略に関する重要な情報をニューヨーク・タイムズの記事分析から抽出、表を作成し、各項目の構成比を見比べてみると、興味深いことがわかった。
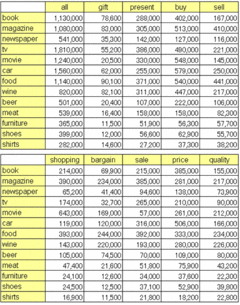
第2部
米国では、特許出願の急増に伴い訴訟が頻発、企業などが敵対的訴訟を仕掛ける“パテント・トロール”も散見される。このビジネスリスクに、企業はどう対処しているのか。
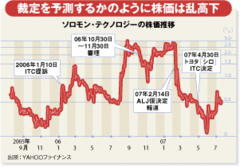
第36回
警戒水域に入ったインフレ上昇 「過ちの70年代」との違い
トリシェECB総裁の記者会見はサプライズだった。「1970年代の過ちを繰り返してはならない」と語っていた彼が、7月に小幅利上げを行なう可能性を示した。
