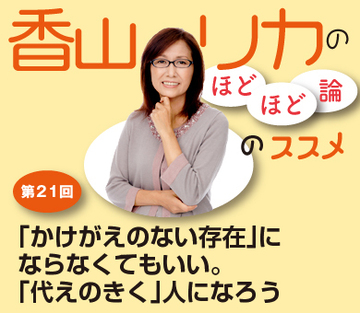香山リカ
東大卒→年商100億円のCEO→インドで仏門に…なぜ男はカネと名声を捨てたのか?
年商100億円超のIT企業でCEOを務め、誰もが羨む社会的地位を築いていた小野裕史氏。しかし、彼は2022年10月にすべてのキャリアを捨ててインドで得度を受け、小野龍光へと生まれ変わった。そんな小野氏の過去に、北海道で僻地医療に携わる精神科医・香山リカ氏が迫る。※本稿は、小野龍光、香山リカ『捨てる生き方』(集英社)の一部を抜粋・編集したものです。

「漫画家脅迫事件」の犯人が感動した刑事の言葉「君は地頭はいいのに…」
「自分はなんてダメな人間なんだ」と打ちひしがれ、自らを“肯定”できずにいる人も多い。インド仏教徒の小野龍光氏と精神科医の香山リカ氏は、自らの仕事を通して人々の“自己肯定感の低さ”に触れる機会が多いという。そんなふたりが、宗教と自己肯定感について語り合う。※本稿は、小野龍光、香山リカ『捨てる生き方』(集英社)の一部を抜粋・編集したものです。

イライラがすーっと消えていく…ブッダが教える「ほんの10秒」の習慣が実践的すぎた!
煩悩や欲にとらわれ、悩みながら生きるのは人の運命。たとえそうだとしても、その煩悩を少しでも軽くする方法はあるのだろうか?かつて、IT企業でCEOを務め、数字や他人からの評価を気にして生きていた小野龍光氏は2022年にインドで得度を受けた。過去の名声を“捨てた”小野氏に、精神科医の香山リカ氏が煩悩との付き合い方について問う。※本稿は、小野龍光、香山リカ『捨てる生き方』(集英社)の一部を抜粋・編集したものです。※本稿は、小野龍光、香山リカ『捨てる生き方』(集英社)の一部を抜粋・編集したものです。

第38回
リスクマネジメントが過剰な社会 なぜ、「正義」ばかりになったのか?
去年の10月から連載をスタートした香山リカさんの「ほどほど論のススメ」が今回でついに最終回を迎えます。どうして今、「ほどほど論」が必要なのか? 38回の連載を振り返りつつ改めて考えていきます。

第37回
なぜ、人は100歳の言葉に共感するのか?「普通に生きる」お手本が欲しい
お年寄りと話していると癒されることってありますよね。何気ない言葉を通して「人生でいろいろあっても何とかなるんだ」という実感が伝わってくるせいでしょうか? 今回は最近ブームの「アラ90」本について香山リカさんが語ります。

第36回
望んだはずのことなのに、なぜ、「理想」はいつも破たんしてしまうのか
「よかれと思ってやったことが、うまくいかない」。そういうことは日常的にあるような気がしますが、これが社会や世界といった規模で起こっているとしたら……どうなってしまうのでしょう。

第35回
香山リカと「カネ」の話をしよう 最終回「プライスレス」思考の落とし穴
カネのために働くか、やりがいのために働くか。これはすべてのビジネスパーソンが一度は悩んだことのある問題ではないでしょうか?今月は「カネ」について思索を続けている香山リカさんの、これで最終回の「カネの話」です。
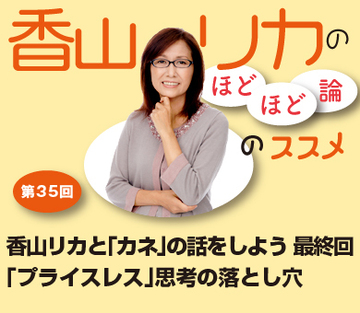
第34回
香山リカと「カネ」の話をしよう2中年クリエイターvs.新世代クリエイター
「学生の頃も、すっかり大人になった今も、マンガとゲームを買うだけのおカネがあればいいんです」と、ちょっと恥ずかしそうにいう香山リカさん。そんなとことん「おカネ」に無頓着な香山さんが、あえて「カネ」について語る第2回目。

第33回
香山リカと「カネ」の話をしよう1
実は「カネの話」にはトラウマがあるんです……と話す香山リカさん。確かに、香山さんの口から「カネの話」はめったに出てきませんが、そういわれると気になって仕方ありません。好奇心半分、スケベ心半分でずんずん聞いてみました。
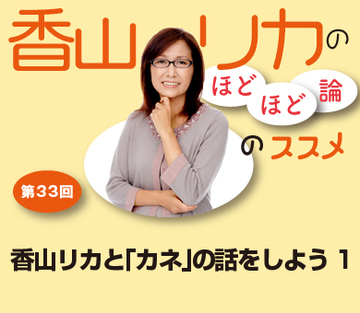
第32回
クリーンすぎる人間関係に注意
IPO(新規株式公開)が失敗に終わり、ユーザーの利用頻度にもかげりが見え始めたといわれるFacebook、一時は身売りの噂も流れたmixi――。めまぐるしく移り変わっていくSNSの世界に、香山リカさんが見いだした人間関係の普遍的法則とは。
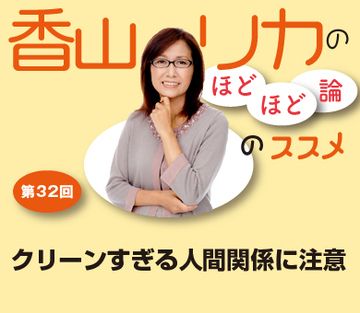
第31回
「ノマド」にとまどう「いい話にはウラがある」という感覚がなくなっている?
最近はやりの「ノマド」。パソコンを持ち歩き居心地のいいカフェで、仕事仲間の集まる共有オフィスで、「遊牧民(ノマド)のように」自由に働く。最近では「社内ノマド」を許容する会社も増えてきているとか。ゴリゴリのインドア派・香山リカさんはどう見ているのでしょう。
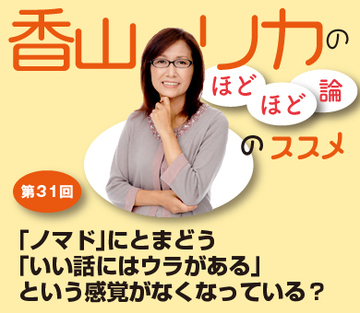
第30回
フレッシュ・シーズンの読書特集人は「○○するな」より「○○しなさい」といわれたい
これまでにたくさんの著書のある香山リカさん。前々回から担当編集者に「読まされている」ビジネス書のページをめくるうち、自分の書いた本の中にある恐ろしい法則を見つけてしまったそう。今回で最後になる読書特集で香山リカさんがたどりついた結論とは?
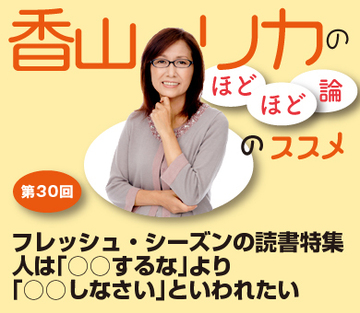
第29回
フレッシュ・シーズンの読書特集成功談の落とし穴
人生でつらい時、仕事で大変な時、ふと手に取った本で成功者の言葉に触れ、「また明日から頑張ろう」と気を取り直すことは多いはず。確かに、その道で名をあげた人の言葉には励まされることが多いのですが……。先回から、おっかなびっくり人生初体験のビジネス書に挑戦している香山リカさんの「読書特集」第2回目。
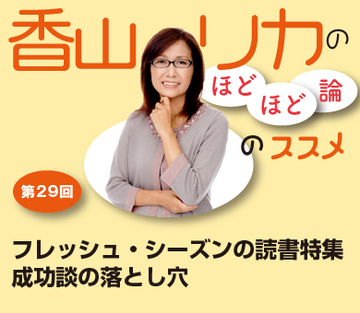
第28回
フレッシュ・シーズンの読書特集なぜ、人はビジネス書を読むのか?
入学、就職、転職などを迎え、「よし、勉強しよう!」と意気込んでいるフレッシュ・パーソンは多いはず。案の上、先日都内の大型書店に行くとレジの前は超超長蛇の列でした。そこで今回に続く数回は「読書特集」と題して、「これまでビジネス書を一冊も読んだことがない」という香山リカさんに、その「不思議」な世界を分析していただきます。
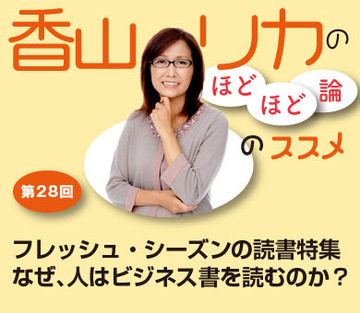
第26回
人はそう簡単に変わらない。すべてを変える必要もない
「たった30分で人は変われる」。こんなコピーを巷で見かけることがあるが、そう簡単に人は変われるものではない。行動が少し変わる程度のものである。自分を変えようとするあまり、自分の長所まで消してしまうのはもったいない。
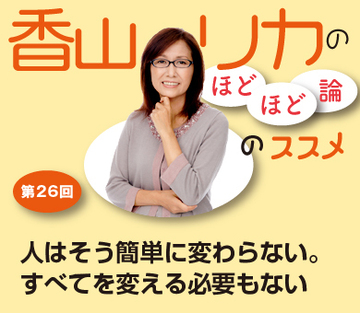
第25回
自分とすべての意見が一致する人はなかなか見つからないもの
現代は、かつてのような「体制vs反体制」「保守vs革新」という単純な図式は成り立ちにくくなっている。また、自分とすべての意見が一致する人はなかなか見つからない。むしろ、それぞれの課題で同じ意見をもつ人が結びつくほうが健全である。
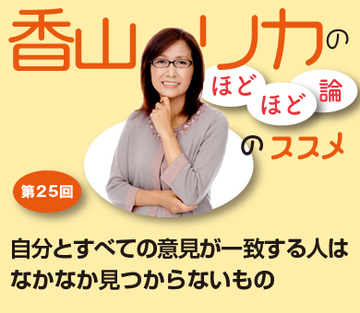
第24回
社会活動に取り組む人になぜ「聖人君子像」を求めるのか
自分の名誉やお金のためではなく、社会に貢献しようと働いている人に対し、世間の見方が厳しいのではないか。彼らはあたかも聖人君子でなければいけないような見方である。彼らも私たちと同じ普通の人である。彼らは完璧の人格者でなければいけないという偏った見方は、社会を窮屈にしてしまう。
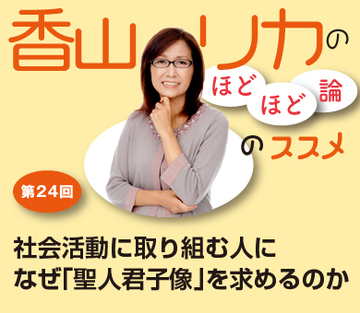
第23回
人は専門家に明解な言葉を求めるが、専門家になればなるほど曖昧な話し方になる
社会が複雑になると、だれもが専門家に正しい意見を求めたくなる。その一方で、専門家であればあるほど、その分野について100%正しいと言えることが少ないことを知っている。この両者の認識の違いが大きなジレンマとなる。果たして明解な答えが得られない社会で、人はどう行動すべきだろうか。
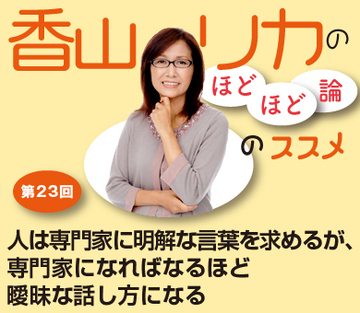
第22回
万人に通用する方法論はない。「臨機応変」は果たして死語なのか
新しい治療法が開発されたと聞くと、すぐにそれに飛びつく人がいる。科学的な方法論の限界を指摘されると、すぐに精神論に走る人も同じである。方法論は世にさまざまあるが、本来、万人に通用するものはないはずだ。誰もが固有の存在であることを、自ら忘れてはいないだろうか。
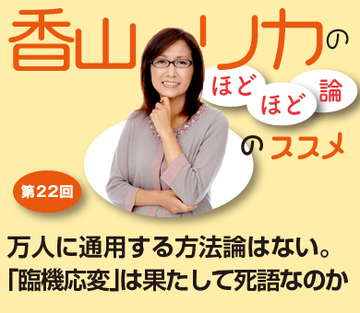
第21回
「かけがえのない存在」にならなくてもいい。「代えのきく」人になろう
社会にとってなくてはならない存在になりたい。多くの学生が就職を前にこのように言う。しかし、必ずしも「かけがえのない人」にならなくても社会に貢献できるのではないだろうか。「代えのきく」人という生き方もあるのだ。