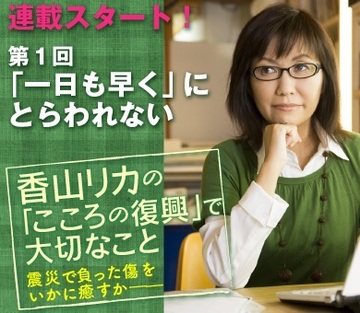香山リカ
第17回
震災から6ヵ月が経過したいま構築すべきは多様性のある社会
震災から半年が経過したいま、一人ひとりに問われるのは、自分のことと社会全体のことの両面を考えること。未曾有の危機を感じた今こそ、自分の安全を守ることと同時に、共助の精神を取り戻したい。大好評の本連載も今回で最終回。この半年を振り返って香山リカさんの語る、求められる社会とは。
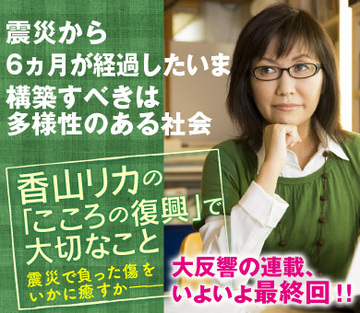
第16回
人が抱える悲しみや苦しみを表に現れた態度だけで決めつけるのは危険
自分の感情や考えを表に出すことはこれまでの日本人が得意とするところではなかったが、最近は変わりつつあるようだ。今回の震災でも大きな悲しみや苦しみに直面したとき、それを態度や行動に出やすい人と出にくい人がいる。だが、行動に表れている人だけが苦しんでいるのではない。人の気持ちを推し量る想像力が求められる。
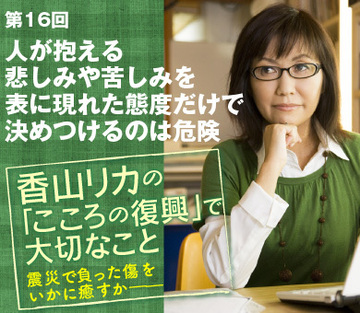
第15回
「支援の和」を支えるために、いま必要なのは「認め合う和」
被災者の大変さと支援する人の苦労に目を奪われがちだが、支援している人を支えている人の苦労も相当なものがある。しかし、それらの人は自分たちより大変な人がいると慮って、自分の大変さを口に出せないストレスを抱えることになる。支援の輪が広がるためには、このような人まで「認め合う和」が広がる必要がある。
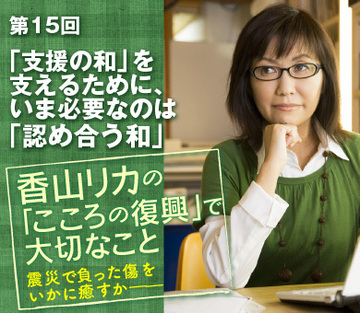
第14回
東日本大震災で明らかになった多くの日本人が望む善意の形
今回の震災で、奇しくも日本人の多くの善意が顕在化した。その基本にあったのは、立場の強い人が弱い人を助けるという「上から目線」でなく、「お互いさま」の精神である。知らない人にも「お互いさま」の気持ちを抱き、顔が見える支援が広がった。この日本人らしい草の根的な支援が集まることで、復興への大きな力となる。
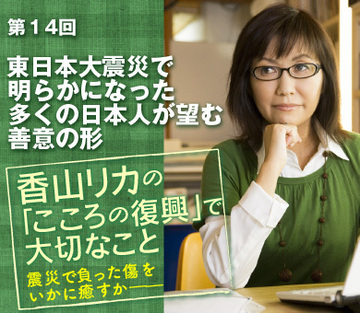
第13回
震災の「見えない被害」の総和は計り知れない
今回の震災の被害額は約16兆円にのぼるという推計が発表された。しかし、これら経済的損失だけで今回の震災を語ることはできない。被災した人はもちろん、直接の被災はなかった人も大きな不安と恐怖を抱えることになった。これら多くの人が精神的に受けたストレスの総和は計り知れない。
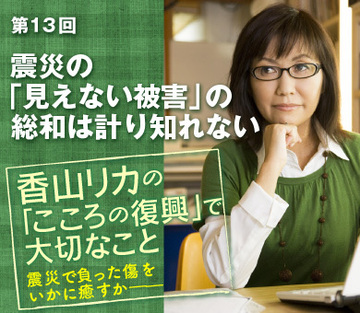
号外
前回のコラムについて――お詫びと補足
前回のコラムについて多くの方から批判的なご意見をいただき、言いたかったことの真意がうまく伝わっていなかったことに気づきました。私の言葉足らずが招いたことです。お詫びと補足をさせてください。
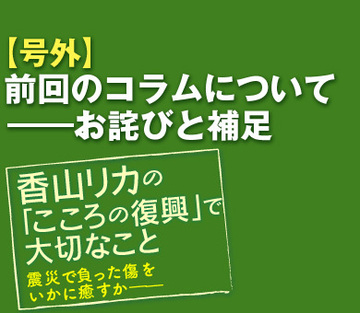
第12回
小出裕章氏が反原発のヒーローとなったもう一つの理由
人々の不安を助長している原発問題。一方でこれまでリアルな社会では引きこもっていた人たちが、ネットでこの問題を熱心に語り出した。奇しくも原発問題が、リアルな社会で力を発揮できない人の存在を浮き彫りにしたのだ。
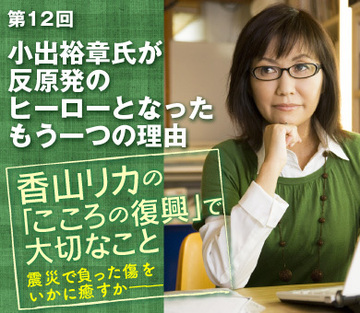
第11回
AKB48のブームは持続するのになぜ被災地支援は持続しないのか
震災から100日が過ぎても被災地ではいまだ瓦礫の山が詰まれているが、今後はボランティアの不足が深刻化しそうだ。いまこそ、持続可能な支援が求められる。ボランティアの募集などでは人々の善意に訴えるのみではなく、企業の販促活動のような支援プロモーションを展開してもいいのではないか。
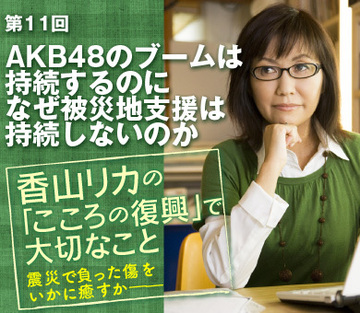
第10回
果たしていま、総理大臣に強いリーダーシップが必要か
菅首相の退任が決定的となり、強いリーダーシップの必要性が叫ばれている。しかし、そもそも安心感を与えてくれるリーダーがいま必要だろうか。私たちは、悪い情報も開示することを求める一方で、リーダーの言葉に安心感を得たい。この矛盾した思いから生まれる、次のリーダーに求める資質とは何か。
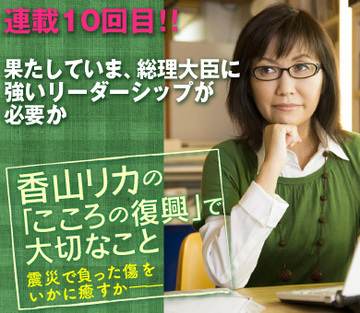
第9回
震災で浮き彫りになった、日本人が求めた「豊かな暮らし」の脆さ
救援物資の中には、必ずしも被災者の好みでないものも多い。それは「贅沢な発想」と切り捨てられない。選択の自由が無数にあった日本では、画一的な製品しか与えられない情況がストレスになる。今回の震災では、豊かな国を築いてきた日本の脆さが浮き彫りになった。
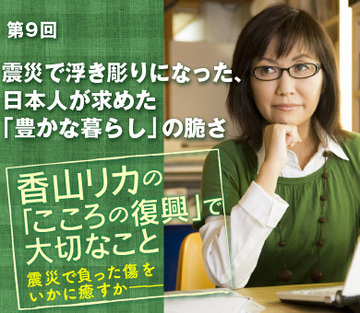
第8回
起きてしまった現実を「なかったこと」にして、乗り越えられるのか
日常生活に戻ることは心のケアという意味では健全である。しかし、震災をあたかも「なかったこと」としてしまうことは果たしていいのだろうか。目を背けたくなるような現実と常に対峙することは、自らをいたずらに傷つけてしまう。その一方で、時間をかけてでも、起きた現実を受け止める必要がある。
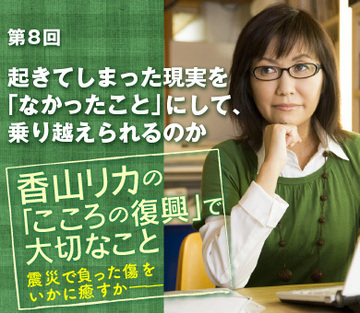
第7回
「不謹慎にも笑ってしまう」のは日常を取り戻すうえで健全である
「こんなときだから」と普段の世間話などが封じ込められるのは危険です。逼迫した情況でも、人は普段と同じような世俗的なことを考えてしまうものです。そういう世俗的な部分を持ち合わせていることを認め合うほうが、健全です。
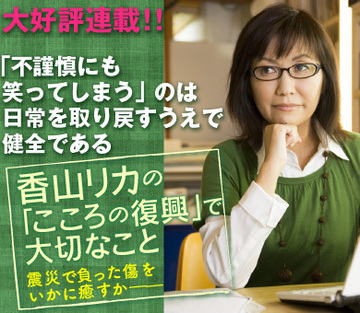
第6回
復興の役に立てないからといって、あなたの価値が下がったわけではない
いま震災の復興と無関係の仕事をしている人が沢山います。それらの人は、「こんな仕事をしていていいのか」と考えるかもしれませんが、それでいいんです。震災があったからと言って、仕事や人の価値がかわったわけではありません。
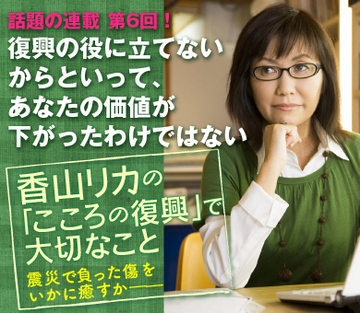
第5回
不安の正体は原発問題。いま「原発鬱」とも呼ぶべき症状が増加している
震災から2ヵ月。多くの人が抱える不安は原発の問題である。これは、白黒つかない問題に対する、日本人の脆さが浮き彫りになった。この原発問題から来る心理的ストレスは、「原発鬱」とも呼ぶべき現象となっている。
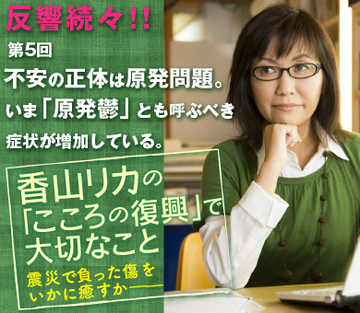
第4回
「かわいそうな被災者」という勝手なイメージを押しつけてはいけない
被災地の人はかわいそう。こういうステレオタイプの見方をすることによって、被災者一人ひとりが抱える苦しみや悲しみがおざなりになりがちです。「頑張ろう」の一言も、受け取られ方はまちまちなのです。
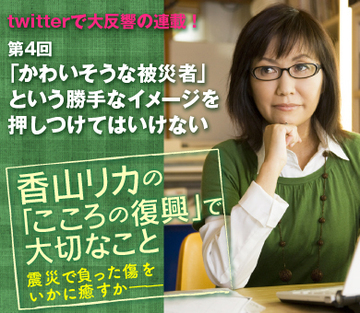
第3回
大きな出来事があったからといって人は急に変わらない
大きな不安や恐怖に直面すると、その反動から気持ちが高揚することがある。精神医学では「葬式躁病」と呼ばれる。いま日本で、この症状に見舞われている人が多い。本来、人は急に変われない。その自覚が必要だ。
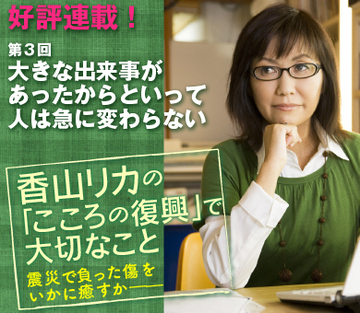
第2回
被災していない人にも「共感疲労」という苦しみがある
今回の震災で、実際に被害にあっていない人も多くの精神的なストレスを抱えている。これは「共感疲労」と呼ばれる現象である。多くの人が共感疲労にもかかわらず、無理をして行動しようという動きも見られる。
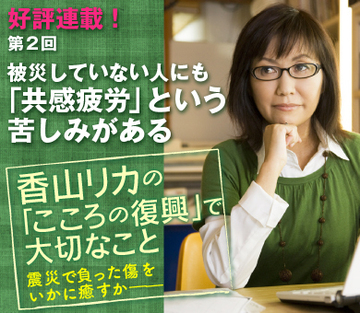
第1回
東日本大地震が及ぼした心的影響は計り知れない。震災に遭った人はもちろん、震災の報道を見続けている多くの人が、いまも不安感や恐怖感を感じている。連載の1回目では、この震災という現実がいかに大きいものであったかを振り返るとともに、「一日も早い復興を」という言葉を多用し過ぎることの危うさも指摘する。